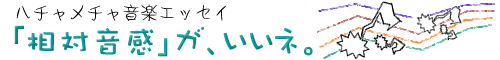●イカクは、音楽ではない
さて、いきなりだが、僕は喜納昌吉さんの音楽に大きな力を感じる。そして、彼の血となり肉となっている沖縄の古謡にも、身震いするほどの感動をおぼえる。1996年のアトランタ・オリンピックの文化イベントに、喜納昌吉さんが五大陸のうちのアジアを代表してコンサート出演した。その時ふと思ったのは、「ああ、なるほど、彼の音楽ならアメリカ人の耳をして極東アジアを代表する音楽に聞こえるのだろうナ」ということだった。アジア音楽としてのアイデンティティーを、日本の多くの人間より外国人が感じ取ったことの証明である。
そのことを、大半の日本人は気づかないし、気づいたとしてもさほど多くの関心を寄せない。喜納さん自身は沖縄の伝統楽器「三線(さんしん)」を持ったり、ギターに持ち替えたりするが、その演奏形態はロックバンドだ。彼の演奏する音楽が好きか嫌いかは、この際問題ではない。問題なのは、彼の音楽のようなアイデンティティーをハッキリと持っていて、それゆえに骨太な「唄」になっている音楽を、この国で他に見つけることができるだろうか、ということだ。
「民族性のないところに、調和なんかない。アトランタで感じたのは、民族のアイデンティティーが世界的に失われてしまっていることだ。根源的なところの民族性を大切にしたい。歌とか、踊りとか、祭りとか・・・・」(96年8月13日「朝日新聞夕刊」)
喜納さんの発言には大いに民族主義者っぽいところがあって、ノホホン日本人をやっている僕など、思わずドキリとさせられるのだが、こと音楽文化という点ではうなずける。
話はガラリと変わって、僕がもっぱらテレビ観戦しているアメリカのメイジャーリーグ・ベイスボールでは、球場にさまざまな音楽が流れる。ヒデオ・ノモがロスアンゼルス・ドジャース在籍中に先発登板した時には、決まって「スキヤキ・ソング」つまり「上を向いて歩こう」がオルガン演奏で流れたものだ。また、これは勝手に僕だけが感じていることなのかも知れないが、ニューヨークのボールパークでは、さすがに多民族都市を意識してか、かつての名画「その男ゾルバ」のテーマ曲(映画の舞台はともかく、とてもギリシア風の音楽)やら、イスラエルのキブツの音楽だと記憶している「ハバナギラ」、さらにはロシア移民が増えたこともあるのだろう、「カリンカ」なんて民族色豊かなBGMが流されたりする。これは、スポーツの場面にさりげなく登場する音楽文化のほんの一例である。
さて、一方の日本におけるスポーツと音楽文化の相対関係は、これはちと目を覆うばかりだが、ブラスバンド=軍楽隊の相関関係が戦前から続いてきたとしか思えないありさまだ。ちなみに学生のハイソサエティオーケストラというジャズのビッグバンドにあこがれもし、やがてそれとは別の理由で僕も入学することとなった大学が、今日の野球応援バンドの花形「コンバットマーチ」を生んだ恥ずべきガッコウだということも、最近になって知った。日本のプロ野球で我が物顔にノサバッている私設応援団と言われる連中の“非音楽的騒音”のヒドさは言うまでもないが、アレなど高校野球離れもしくは学校ごっこ離れできない連中の単なるウサ晴らし騒音に過ぎないことは明らかだ。
野球の最大の醍醐味とは、強打者のバットがウナリを上げる音だし、キャッチャーミットに破裂音を生じさせる豪速球ピッチャーの投球だ。つまり日本のボールパークでは、野球というスポーツが奏でてくれる“音楽的白球の音色”を傍若無人な応援行為が一切かき消してくれているのだ。アリガタヤ。
また、静岡県浜松市のタコあげ祭りや長野県の御柱祭などで吹き鳴らされるラッパなんぞは、明治以降の挙国一致・富国強兵・我田引水・唯我独尊・言語道断・信賞必罰・抱腹絶倒・焼肉定食・本日開店などの四文字熟語のありったけを使いまくってもまだおツリが来るほどの“ぽっと出”の歴史でしかなく、あれでは祭りの伝統そのものを汚しているとさえ、僕は思う。
日本の野球やサッカーなどの応援風景を見ていると、総じて「若い人のリズム感の良さにはついていけない」などという大人たちの常識がウソのように聞こえる。ヒドイのだ。もちろん、リズムオンチの若者だけが、ああしたスポーツ施設に集まってくるワケではない。サッカーJリーグのサポーターたちのリズムオンチぶりもなかなかのものがある。
「タテノリ」とでも言うのだろうか、彼らのリズムパターンはサポートソングが変わってもまるで一様で、お蔭でゲームでの選手の動きさえも一本調子に見えるほどだ。タテノリでやられる「聖者の行進」なんざ、ヒタイに張り付いたハエみたいに気持ちが悪くはないのだろうか。あのニューオーリンズジャズの名曲の魅力は、裏打ちのリズムにこそあるのに。もっとも、若いヤツらはリズム感がイイと発言している一部の大人たちは、きっと昔からリズム感がなかっただけで、僕などどうして若いヤツらはああもリズム感が貧弱なのだろう、と思っている。
このように、スポーツの場あるいは一部の祭りに登場する「音楽らしき音」は、最初の内の「景気づけ」から徐々に「音によるイカク」へと脅威を拡げている。僕など「イカクはイカンよ」、と思う。考えてみると、日本のスポーツ観戦そっちのけの応援や、祭りで吹き鳴らされる奇妙なラッパなどは、その場の圧倒的な雰囲気の掌握、つまり存在誇示のために行なわれるワケで、彼らもまた「その場の権力」となりたいのだった。
権力はやがて権威となり、時代の空気を創り出していく。日本で、西欧古典音楽が圧倒的権威を持って教えられ、それ故に「音楽の授業ってつまらない」と思われている現状を考えると、エヘラエヘラと笑ってばかりはいられない。
●西欧音楽は、なぜ権威となったのか?
タイトルをつけておきながら、いきなり「イケネ、こんな専門的なハナシができるワケがない」と、あきらめた。あきらめはしたけれど、ヘタな鉄砲も数撃ちゃ当たるのコトワザにのっとって、イイ加減なことを書く。
ヨーロッパのいわゆるクラシック音楽が今日のように世界の権威となったのは、あのいまいましい五線譜とピアノがあるからだ。あのいまいましい五線譜とピアノがあるからこそ、芸能だった音楽がゲージツに変身しちまったのに違いない。
で、西欧音楽は遠慮ってものを知らないから、「アタシャ、芸人なんだから、ゲージツなんてえ術は使いません」とおっしゃらはらほろひれた偉大な落語家のようなシャレッ気もなく、「ワシこそが芸術じゃ」と歴史上にノサばっている。つまり、口承などというあまりにも人間的なイイ加減な方法でなく、「正しく記録」され、「正しく再演」されるノウハウを持った最初にして最高の音楽という「うぬぼれ」が、今日の西欧音楽偏重主義の根底にはあるのだろう。
さて、なんだか矛盾してしまうが、日本の音楽教育の欠点をえぐり出してやろうと考えている自分自身が、いちばんその悪影響を受けているのかも知れない、ということに気づかされる。つまり、ある程度楽譜音楽に慣れてしまうと、今度はその楽譜が自分自身の音楽を楽しむ時の邪魔になることだってあるのだ。
ハーモニカ少年だった頃に思いっきり自由に吹けていたはずの音楽が、楽譜と出会ってからずいぶんと不自由になった記憶が、僕にはある。つまり、楽譜は、コレ以外の音を出すでない!という権威として、僕の前に出現したのだった。
さらに、子供だった僕が「知ってる曲は吹ける曲」というのと同じぐらいに自信があったハーモニカの音色に関しては、学校教育の中で教えられた記憶がない。小学生かあるいは中学あたりの音楽の筆記試験に、おそらく必ず出たであろう「音楽の三要素は?」という問題。答えが「メロディー・リズム・ハーモニー」であることはほとんどの人が知っているし、僕らの受けてきた音楽教育はまさにそういうことだったはずだ。
ところが、コンサート会場で名手の弾くたった一音のピアノの音だけで、あるいはポルトガルのファドの歌手の一声だけで、背筋にシビレのような感動を覚えるのはなぜだろうか。同じドの音を弾いたとしても、習いたてのバイオリンの音に幻滅を感じ、名手の音にゾクゾクと興奮するのは、なぜだろうか。
音楽には、明らかに「三要素」といわれるもの以前の重大な要素があるではないか。学校教育で習ったアレは、ひょっとしたら作曲家の論理であって、作曲されたものを楽譜化し、教育しようとするものの論理であり、「音楽学者」の論理なのではなかったのだろうか、などと考えたりする。
僕は、一時期それこそ「歌うお兄ちゃん」としてオペラにも熱中していたので、若い頃には他人様の結婚披露宴に招かれた場合、決まって「オーソレミオ」をア・カペラで歌った。ちょっぴり酒が回って眠気を催した参会者も、マイクなしでタタキ起こすことができたのが唯一の自慢だ。美声に驚愕されたワケではない。
もちろん、テレビで「世界三大テノールの共演」なんていう番組があればカブリつきで見る。なにしろ、歌曲はカンツォーネと心に決めているのだ。そこで、カレーラスの華麗さ(ダジャレではない)と繊細さに酔い、ドミンゴのスケールを賞賛し、鍛え抜かれた男どもの美声にうっとりとしてしまうのだが、パバロッティだけは何度聞いても別格に感じられてしまう。僕はいつも、脇にいるワイフとともに「この太っちょの女タラシ!」と叫びつつ、メロメロ状態となる。
何度も何度も彼らのコンサートを聞く内に、他の二人には伝統あるオペラ歌手としての最高の教育を受けた結晶のようなものを感じるのに、パバロッティはなぜかそこから逸脱しているように聞こえてならないのだ。天性とでも言うのだろうか、あるいは地声、素声で好きなように歌ってる(実際にそうでないのは想像できるが)感じなのだ。つまり、教育から逸脱した天賦の才とは、こういうことを言うのだろうナ、と感じさせる人なのだ。「パバロッティは楽譜が読めない」などという噂話が上ったのも、彼の類稀な歌手としての自由度に原因があったのだろうと思う。
1996年の秋、静岡県浜松市で「世界音楽フォーラム」という国際会議があり、僕は偶然にもその報告書のようなものを手に入れた。いわば世界中の音楽教育の権威が集まっての会議だ。そこで議論されたテーマのキーワードを思い出すと、「多文化社会と音楽」やら「多文化化する日本」などという、会議に参加した日本の音楽教育関係者が赤面しないではいられないはずの議題が取り上げられていた。いったい日本の音楽教育の、どこがどう多文化化しているのだろう。相変わらずの西欧音楽崇拝主義、西欧音楽至上主義がマンエンしているだけのことなのではないだろうか。
なんでも、今日につながる西洋音楽の日本伝来の最初は、キリスト教の伝来とともにあって450年前にさかのぼり、本格的には明治維新がキッカケで、明治政府がドイツ・ロマン派の音楽を導入したことに始まるのだそうだ。で、このドイツ・ロマン派の音楽というのは、メロディーの伴奏をリズムが受け持つもので、そのメロディーの根源には「詩」があった。言葉とは、それほどまでに音楽の重要要素だったワケで、そういう背景のもとに北原白秋や西条八十などの偉大な詩人が生まれたのだと、いつか「朝まで生テレビ」に出演なさったCFソングの作曲で知られるコバヤシアセーさんが言っていたのを、つい5分37秒前に思い出した。フムム、そうかと思いつつ、同時に、今日の楽譜やピアノに代表される西欧音楽に権威を与えたのも、この頃だったのだと思う。西欧音楽に追いつくために、つまり手っ取り早く模倣ができるために、あの「絶対音感」教育が生まれたのだろう。 |