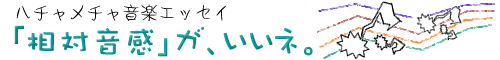●『絶対音感』が売れたワケ
本書の冒頭でもふれたように、新聞の書評欄で『絶対音感』の書名を見つけた時、ちょいと音楽に関心のある人なら三通りの反応をしたのだと思う。「ちょっと気になるタイトルだし、好奇心いっぱいの読書家のアタシにとって読みごたえがありそう」と考えた一般的な音楽ファンにして本好き。「フムム、コイツは天下の一大事。音楽に関しちゃ何事も真摯な態度で臨むことを旨としているアタシにとって、コレは見逃せませんゾ!」と考えた音楽信奉者。「おお、性懲りもなく音楽アカデミズムについて書けば、まだまだ需要はあるのネ」と考えたのは、僕なんぞのようなヘソマガリだ。僕の友人にフルカワさんという人物がいて、先日久しぶりに会った。釣りキチにしてゴルフ下手、ジャズ狂にして酒好き、ワガママにして女好き、そして何より僕の感化を受けて「四十にして立つ」とばかりピアノを始めてしまったオジサンだ。
「読みましたか?」
「ホイホイ、読みました」
「どうでしたか?」
「アタマに来て、途中でヤメました」
「どうしてまた、そんな悲惨なコトに!」
「だって、音楽の本だと思って買ったら、違うじゃありませんか」
「ハイ、アレは科学書ですから。だいだい、どうして買う気になったんです?」
「そりゃ、『絶対音感』ときたら、ゼッタイ買いますよ!」
「どうしてゼッタイ買うんですか?」
「そりゃアナタ、僕はこれでもピアノを弾く人間のハシクレじゃないですか。忘れたとは言わせませんゼ」
もう10年近くも前のある晩、僕がフルカワさんに連れられて分不相応な銀座のバーに行ったと思いねえ。で、そこにはフロアの真ん中にドカーンとグランドピアノが置いてあり、僕はフルカワさんに告白した。
「ピアノって、考えてるほどムズカシクないですヨ。基本を無視すりゃ、誰にだってできる。幸い客も少なくなったし、後でスキを盗んで、僕も弾いちゃおうかナっと」
単なるロクデナシの酔いどれコピーライターとばかり思っていた目の前の相手が「ピアノ弾いちゃおうかナっと」と発言したため、フルカワさんの目は充血の度を増し、「今ヤレ、スグヤレ、トットトヤレ、ホイ!」ということになった。
ヘイヘイと僕はピアノの前に座り、本当ならCマイナーの「マイ・ファニー・バレンタイン」を、黒鍵なんぞ使っていられるかってんでAマイナーに移調して、ピロピロポロビレシュビダバダと弾いた。もちろん、大した腕前でないことは自分にだって分かっている。だいいち、右手がメロディー、左手でコードという「即決安直それ行けゴー!」のロクデナシ・ピアノは今も変わりがない。
ピアノを弾いていたら、どっかのオジサンから声が掛かった。
「オウ、兄ちゃん、ウマイねえ」
少なくともその時分までは「兄ちゃん」と呼ばれる容姿だった。
「兄ちゃんのピアノで、歌いたいナア」
結局、ド演歌の伴奏をテキトーにやったら、感謝された。
席に戻った僕に、フルカワさんが真顔になって言う。
「アタシャ、明日っからヤリます。ピアノをヤリます!」
かくしてフルカワさんは、僕のピアノの一番弟子となった。
実は、このハナシには続きがあって、僕が席に引っ込んだ途端、一見してそれと分かるオアニイサンが、高そうなジャケットをピシッと着こみ、若い衆を脇に従え、ピアノの前に進み出て、突然何かのピアノ曲を弾きまくったのだった。それも酔っ払いの僕たち二人にとっては、まさに「バカテク」の腕前だった。
これはまた劇的な音楽的出会いとばかり、演奏の終わったおアニイサンに向かって
「ヤンヤ、ヤンヤ、ブラボーめ、もう一曲!」とハヤシ立てたら、脇の若い衆が僕らの席までやって来て、「ザケンジャネエ!殺すゾ、テメエラ!」とおっしゃらはりましたので、シュンとなって黙ってしまった二人でした。
カシを変えてフルカワさんと語り合ったのは、あのオアニイサンがいかにソノ筋のヒトであり彼の親御さんの職業はともかく、お金に恵まれた良家のオボッチャマには変わりなく、ピアノは基本が大事で、基本の習得には金が掛かると教えられる出来事だった。
で、フルカワさんいわく。
「あそこまではなれないけど、アンタの弾き方ならネ」
つまり、「相対音感だけがイノチ、テキトーに弾けばそこそこカッコがつくよバージョン」の僕のピアノがフルカワさんのお気に入りとなったのだった。
さて、もう一度ハナシを元に戻すとしよう。『絶対音感』はなぜ売れたのか。
僕の友人のフルカワさんの例をいまさら持ち出すまでもなく、実は「絶対音感」というコトバそのものが、日本の一般音楽愛好家のあいだにまでもしっかりと「権威的」あるいは「学術的」音楽の強迫観念として根付いているからなのだ。
僕らが与えられた戦後音楽教育と、いわば音楽を糧として生き永らえているヨーロッパ音楽信奉者たちの「音楽学」普及啓蒙活動の偉大な成果として、『絶対音感』は売れたのだった。ウ〜ム、ウラヤマシい。
●ハーモニカ少年と学校音楽
ところで、僕の世代が受けたのは戦後民主主義教育というヤツである。義務教育を受けていた主に1960年代、僕らの音楽教材はいわゆる「文部省唱歌」が中心だった。「春の小川」「ふるさと」などは、僕らにとって学校音楽のスタンダードナンバーだし、フォスターやスコットランド民謡などというのもあった。
一方、チマタにはミソラヒバリの唄が流れ、ちょっと進んだ小学生ならプレスリーなんていうのを聞いていたガキがいたかも知れない。
そして、子供だった僕らの世代が、親たちの世代と違いを見せたのは、テレビ番組の主題歌を次々とおぼえて歌えるようになってしまうことだった。ヨチヨチ歩きの頃は、音楽情報はラジオで得ているだけだったが、子供たちはいよいよ新しい時代の音楽ソースを手に入れたのだった。
まだ、若者(お兄さんたち)がフォークギターやエレキギターにとりつかれてサカゲ立ってしまう前だったから、歌に伴奏がつくというのは、上手な子のハーモニカか学校の先生のオルガンぐらいというのが相場で、その分だけ音楽の授業は楽しく、鍵盤楽器をどうにか弾きこなすオンナ先生には、尊敬にも似たあこがれを持っていたおぼえがある。
さてここで、恥知らずにも自慢話をひとくさり。
天才少年というワケにはいかなかったが、ハーモニカ少年だった僕は、一度聞いた曲をすぐに吹いてしまう特技の持ち主だった。小学校の林間教室では、夜のフォークダンス演奏係として吹きまくる名誉もサズカった。マイクに向かって吹いた「オクラホマミキサー」が、キャンプファイヤーの薄明かりの中、深い森に反響するのはたまらない快感だったことをおぼえている。
きっとそんな子供が、どこの学校にも1人や2人いたのではないだろうか。教師にしてみれば、まだむやみに重かった電気蓄音機やアコーディオンなどを遠路はるばる持参しなくてもいいわけで、僕などは結構「使える便利なヤツ」だったのだ。
父親のハーモニカ好きが伝染して、見よう見まねで吹きはじめ、童謡曲集などがあると、1ページめから最後まで吹きまくる、なんてこともしょっちゅうだった。
もっともその当時は当然のことながら楽譜など読めなくて、譜面の下の歌詞を読み、「あ、これ知ってる」という曲だけがレパートリーとなった。つまり、歌える曲が吹ける曲というワケだ。
他の子供が「ド」なら「ド」の音だけをニゴリなく吹こうと四苦八苦しているときに、だいたいこのあたりの音と決めたら「ブカッ」と出してしまうハーモニカのコツをさっさと体得してしまったのが、なによりこのハーモニカ少年の強みだったように思う。「イイカゲン・イズ・ザ・ベスト」がハーモニカの極意だった。
そういうワケで、学校の音楽の授業でハーモニカがあると、僕はふだんの僕の流儀ではなく、学校用の奏法でくちびるをすぼめ、なんとも貧弱な音を鳴らすことになる。あのキャンプファイヤー御用達という栄光に比べ、ちょっとした挫折感さえあった。
ちょうどそれは、ミソラヒバリやプレスリーは好きだけど、学校でする音楽とは違うということが分かっているのと同じだった。
学校でする音楽ということに関して、また別のエピソードがある。僕には4才年上の姉がいて、おそらくその姉が中学生の頃のことだったと思うのだが、学校から帰った姉が得意げに教えてくれた。「今日、音楽の先生が言っていたけど、○○○○の発声法はサイテーなんですって。もっと声はおなかから出さなくちゃいけないのヨ、確かに○○○○って貧弱な声よネ」
○○○○が誰だったかは忘れてしまったが、テレビでも売り出し中の日本の若い女性ポップス歌手で、僕や姉などは昨夜までウットリと聞いていたはずだった。でも、姉の口から聞いた中学の音楽の先生の一言は重たくて、それ以後、その女性歌手がテレビに登場してもなんとなく軽蔑じみた気持ちを抱いてしまうようになった。
それにしても、テレビは次々と僕らの知らない新しい音楽を紹介し、学校音楽はどんなに新しくても数十年前の音楽を教えるばかりだった。ベートーベンやバッハは、それがどんなに偉大な作曲家だったとしても、義務教育期間の子供だった僕らにはえらく退屈にしか聞こえないし、ロシア民謡やスコットランド民謡は教材になるのに、どういうワケか日本の民謡を音楽の授業でとり上げることもなかった。
成長してから、僕がしばらく抱いていた音楽というもののイメージは、間違いなくこの時代に培われたものだ。
1.まず、音楽は、西欧がエライ。
2.民謡などの民族音楽は、音楽的にも文化的にも先進国といわれる国のものはとり上げるが、それ以外はあまり価値がない。
3.ピアノで弾けなかったり、五線紙の楽譜に表記できない音楽は、ちょっとレベルの低いものである。
4.音楽は、自由に楽しむものではない。正しくするものである。
5.いい音楽とは、学校で教える音楽である。
6.音楽とは、勉強したもののみが鑑賞でき、勉強したもののみが演奏できる芸術である。
自己流が好きだったハーモニカ少年は、どういうわけかうまく立ち回り、学校の音楽の成績の方もまずまず優の部類だった。
ただ、ト音記号をなぞって書き方を練習したり、♯(シャープ)や♭(フラット)のある楽譜の読み方や、コレは何調であるかというような段階になると、どうも好きではない学科になってしまった。
たとえば、こんなことがあった。学校で習った曲が好きになり、家に帰ってさっそくハーモニカを吹き鳴らした。ハーモニカ少年にできない曲はないのだ! ちゃんとおぼえたての曲だって一発でできるのである。
「ブカブカブーブー、ブカブーブー・・・・」
ひとわたり吹き終えてエツに入り、音楽の教科書を見る。すると、いま吹き終った曲の楽譜には、ト音記号の横におぼえたばかりの♭が付いているではないか。しかも、2つもである。
それにひきかえ、僕のハーモニカはごくごくシンプルなものだ。半音の装置など付いているワケもない。五線に♭のあるところをたどっていくと、歌詞の「なかまたち〜」の「な」の音と「あそんでる〜」の「る」の音は半音下げなくちゃならない。それなのに、僕のハーモニカには半音装置はないのだ。
エエイ、コレはいったいどういうコトなのだーッ!
もっとよく確かめてみると、曲の出だしの音がもう違っている。僕は「ソ」の音で始めたのに、楽譜を見ると「ファ」の音で始まっているではないか。
幼いハーモニカ少年は、ここでハタと悩む。学校の歌にしてはいい歌だと思ったからハーモニカで吹いてみたんダイ。ちゃんとおぼえたメロディーで完璧に吹けたじゃないか。それなのに、楽譜を見るとまるで違っている。何なんだ、コレは! これだから、学校でやる音楽はムズカシい・・・・。
もちろん、ちょっと音楽を知っている人やギターなどをやっている人にとってはカンタンなタネ明かしだ。僕の耳が勝手に「相対音感」を働かせ、ごくごくシンプルな移調作業を無意識のうちにやっていただけのことなのだった。
しかし、幼いハーモニカ少年には不可解千万、五里霧中、暗中模索のパズルでしかなかった。
「これだから、楽譜のある音楽はムズカシい!」
〜 次号につづく 〜 |