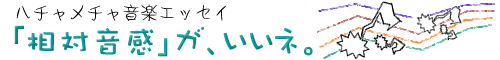●くたばれ!音学ギョーカイのアカデミズム
僕はすでに、日本の義務教育下の音楽と英語の授業は似ていると書いた。結果として、日本の学校教育の成果では、満足に英会話すらできない。その証拠が、僕であり、読者のあなたである。英会話に多少なりとも不自由しなくなる能力を養ってくれるのは、学校以外に自宅で聞いたラジオ番組だったり、英語の歌だったり、自腹を切って出掛ける海外旅行や英会話学校である。
また、音楽を楽しめる能力を育ててくれたのは、日本の学校教育の成果ではない。学校が教えてくれるのは、西欧偏重の「音楽学」に通じる音楽がほとんどであり、たいていの場合、音楽を楽しむ能力はテレビやラジオにまかせっぱなしなのだ。
で、「音楽学」としての授業を通しても、楽譜すら満足に読めるようにはならない。
「なにをヌカすか、五線譜にはじまってト音記号、#、♭、オタマジャクシの知識まで、教科の中で教えられたハズじゃ!」
ホントにこう思っている人がいたら、オメデタいとしかいいようがない。ためしに、街を行くかつての少年少女に聞いてみればいい。
「あなたは楽譜が読めますか?」
十中八九の人が、こう答えるハズだ。
「とんでもない!専門家じゃありませんから」
そうだ、専門家でもない限り、楽譜など読む必要性が生じないのはあたり前のことだ。残りの一人か二人は、こう答える。
「ええ、なんとかネ」
この「なんとかネ」と答えた人に、さらに質問をしてみれば、学校教育の無残な成果がもっと明確になる。そう答えた人の大半が、子供の頃ピアノ教室に通っていたり、あるいは吹奏楽部などの課外活動をキッカケにおぼえたり、自分自身の趣味でギターなどの楽器を楽しむうちに「読譜能力」を養ったりした人たちである。好きこそものの、でおぼえた人たちであって、けっして学校教育の音楽の授業で楽譜が読めるようになったワケではない。ところが、音楽の授業の筆記試験では、これら楽譜に関する問題がしつこく出され、いやおうなく圧倒的多数の「音楽ギライ」を生みつづけていく。
またまたためしに、東大の入学試験日に、赤門前でアンケートを取ってみればいい。学校以外での音楽教育を受けていないことを条件に、ごくごくカンタンと思われている楽譜を用意し、それを声に出して歌わせてみせるのだ。きっとテレビ局が喜びそうなネタになることウケアイである。
余談になるが、例の一流大学卒ばかりの高学歴信者で固められた宗教団体が政治に打って出たとき、僕の住んでいる街の駅前で選挙活動をしたことがある。全員だったかどうかは忘れたが、教祖の顔を模したカブリモノをして、教祖自らが歌っているというテープに合わせてモソモソと踊るパファーマンスに出くわした。いま思うと、まるで今日の裁判の状況をあらわすように「証拠、証拠、ショーコ、ショーコ」と歌っていたのが笑えるが、それよりなにより、あの音楽的な貧しさに気づかない人間の集団というのに、当時僕はア然としたものだった。さすがにベンキョーの虫の集団である。さぞかし、学校の音楽の成績も良かったに違いないと思う。
それにしても僕には、どう考えても学校の音楽教育での狙いがわからない。もちろん、情操教育としての音楽の果たす役割の大きさというのは十分すぎるほどわかっている。この僕自身、音楽のない生活なんて想像もできないのだから。では、いったいどんな狙いがあるというのだろうか。コムズカシいハナシになるが、ごカンベンいただきたい。
近代社会の中で、音楽が重要な役割を果したのは、ひとつには宗教儀式の中での演出という意味合いが大きかった。西洋社会では、キリスト教の教会音楽はまさにそれだし、こうした環境の中から生まれた大作曲家こそが、学校教育を通じて僕らが知ったクラシック音楽の中枢をなしていると言ってもいい。さらに、教会と結びついたところにいた王侯貴族がパトロンとなって生まれた音楽というのも、音楽学の歴史で習ったおぼえがある。日本の音楽教育史を書物でひもといてみると、西欧音楽中心主義というのは明治期から始まり、一方で戦前には国威発揚のために軍歌まで導入されたという反省もあって、戦後は、ともかく古今東西の「いい音楽」にふれさせることを最大の目的にしている、らしい。学校で音楽を教えているセンセーがたに、この考えに異論をはさむ人はまずいないだろう。問題なのは、この「いい音楽」の判断基準であり、「音楽にふれる」とはいったいどういう内容をさしているのか、である。第一章の「ハーモニカ少年と学校音楽」で書いた部分を、もう一度ぬき出してみる。
1.まず、音楽は、西欧がエライ。
2.民謡などの民族音楽は、音楽的にも文化的にも先進国といわれる国のものはとり上げるが、それ以外はあまり価値がない。
3.ピアノで弾けなかったり、五線紙の楽譜に表記できない音楽は、ちょっとレベルの低いものである。
4.音楽は、自由に楽しむものではない。正しくするものである。
5.いい音楽とは、学校で教える音楽である。
6.音楽とは、勉強したもののみが鑑賞でき、勉強したもののみが演奏できる芸術である。
これはべつに、学校音楽の指導マニュアルに書かれているワケではないし(見たことはないけれど)、教師が授業でこういったワケでもない。しかし、学校の音楽教育を受けて得た、僕自身の一時期までのいつわらざる感想なのである。つまり、こう教わったと言っていいワケだ。あなたにも心あたりがあるのではないだろうか。
で、モロモロ考えてみるにつけ、僕にはその「元凶」がどうしても「譜面大事主義」と「ピアノ主役主義」「音学主義」にあるようにしか思えないのだ。
もちろん、最大の原因は音楽教師にある。彼らに、譜面やピアノを離れて、音楽の楽しさを伝えるだけの能力がないのだ。また、音楽教師量産工場の音楽大学などの教育機関にも、華道や茶道などにも勝るとも劣らぬほどの「家元制度」のような空気がマンエンしていて、たがいをセンセーと呼びあう馴れ合い社会、つまり「音学ギョーカイのアカデミズム」を後生大事にしているニオイがフンプンとするのだ。そういう社会では、西欧の古典音楽のみを音楽と言い、今日街を流れる雑多な「軽音楽」とは一線を引いて差別する。それがあたかも正しいおこないだと信じて。
小学校や中学校の音楽の授業を受ける生徒たち全員が、音楽大学をめざしたり音楽の教師や音楽のプロをめざしているのなら、きっと譜面も音学もあっていいだろう。ピアノを授業にとり入れたっていいハズだ。しかし、音楽教師自身、ピアノ教室や町の音楽教室に通ったあげくに、ようやく音楽大学に入った身の上を忘れているのではないだろうか。学校教育だけで、自分たちの音楽的素養なり知識を得たという人がいるなら、お目にかかりたいものだ。
学校教育でできる音楽教育というのが、もっと他にあるのではないだろうか? あなたがたの教育成果とは、入学式や卒業式での校歌斉唱を難なく実行させることぐらいのものなのではないのだろうか? 分かった!あなたがたは、あなたがた程度の「音学」を大切にする、極めて「非音楽的」なミニチュアを育てたいのではないだろうか?
●結局、ジャズはスゴイ
ハーモニカ少年、歌うお兄ちゃんを経て、大学入学のために東京にやって来た僕は、あっという間にジャズ信奉者に変身してしまった。長いあいだ捜しつづけてきたホンモノの音楽、楽器で遊ぶ「音楽遊び」の究極のスタイルというのを見つけた気持ちになった。
キッカケは学生時代のレコードだったが、広告屋になった頃から足しげくコンサートに通うようになった。バブル経済に浮かれるちょっと前のことだったから、今日のような法外なチケット料金ではない。2、3千円で、たいていの一流ミュージシャンのコンサートが聞けた。ソニー・ロリンズ、アート・ペッパー、ハンク・ジョーンズ、エルビン・ジョーンズ、ジョニー・グリフィン、マイルス・デイビス、チック・コリア、ハービー・ハンコック、ベニー・グッドマン、ベニー・カーター、フレディ・ハバード・・・・・
。20年ほどの歳月が、このうちの多くの巨星を帰らぬ人にした。
ジャズという音楽では、たとえばたった12小節のブルースが10倍にも、20倍にもなって演奏される。最初の12小節はテーマといわれ、原曲に忠実に演奏されるが、そこから先は12小節を一つの単位(コーラス)として、1コーラスのもっている曲調を手掛かりとし、さらにはコード展開(和音の流れ)を再現しつつ、あとはどうなとお好きにおやり、という具合で展開される。言ってみれば、音楽による俳句のようなものだ(フムフム、ワレながら大胆な仮説である)。道理で日本人にジャズファンが多いはずだ。
季語というものがあるとすれば、それがテーマで、テーマは必ずある色調を帯びた和音をともなう。1コーラスは4小節づつに性格があって、3分割されていると考えてもらいたい。五線紙の1行には4小節書かれていることが多いが、それだとたった3行の音楽、それがブルースである。
で、このブルースを俳句としたら、仮に最初の4拍4小節で「古池や〜」とやる。次の4拍4小節で、もう一度「古池や〜」とくり返す。最後の4拍4小節で、残りの「かわず飛び込む水の音」を一気にやる。音楽学的にいえば、「A」「Aダッシュ」「B」というヤツだ。文章的にいえば、「起」「起」、「承・転」がなくて「結」というカッコウだ。 基本的に、ジャズは「音遊び」だ。だから、「古池や〜」というもとの音は、テーマ演奏が終わってさあこれから遊ぼうゼ、となってからは「去年オイラがおっこちた古池がサ〜」という風に変化したり、「芭蕉センセーは池だっていってるけど、オイラにゃどう見ても水たまりぐらいにしか見えない小さな古池でネ」という風に形容されたりもする。これが、ジャズにおける基本的なインプロヴィゼーション(即興)というもので、一般的にはアドリブともいわれているアレだ。
先にも書いたが、ジャズはまさしく即興性と呼応性の音楽だから、こういう誰かのアドリブに対して、バンドの別の演奏者はすぐに呼応する。「ホーホー、それからどうした」てな具合だ。
もう、コレは「音を楽しむ」音楽そのものだ、と思った。こういう音楽を知らなかったそれまでの自分をうらめしく思った。そうとわかったら、いても立ってもいられないということになるのが、かつてのハーモニカ少年のサガだった。
ジャズをやろう。どこかのジャズのサークルに入れば、練習のキッカケになるかも知れないが、じゃいったい何をやる? 考えたあげく、ピアノしかないということになった。理由はいろいろあるが、自己完結型の楽器として、一人で楽しむ分にはピアノがいちばんと思ったからだ。ジャズで、ソロピアノというのはあるが、ソロトランペットとかソロサックスというのはあまり聞かない。ピアノなら、リズム&ハーモニー&メロディーの一人三役ができるハズだし、ハーモニカ少年のアタマにはピアノがムズカシい楽器だという社会通念も、こうなるとどこかに消し飛んでしまうタチなのである。
こうして、中古ピアノを手に入れた。30歳をちょっと過ぎた頃のことだった。予想通り、周囲の友人たちは好奇の視線を送るばかり。「バカやってやがら〜」という感じである。ところが、今やすっかりピアノを弾くオジサンと化した僕には、コレが楽しい。ギターでおぼえたコードの知識をフルに生かして、左手はコード、右手はメロディーというパターンでやる。古いポピュラー曲集をひっぱり出してかたっぱしからやるのは、ハーモニカ少年時代と同じだ。また、「C」と「F」と「Gセブンス」、「Aマイナー」と「Dマイナー」と「Eセブンス」をさっさとおぼえたのは、歌うお兄ちゃん時代のギター速習法と同じだ。
さて、そういう初期段階をさっさと通過すると(ウマくなったという意味ではない)、ちゃんとしたジャズのピアノ譜が欲しくなるのが当然の雲行き。銀座の楽器店にすっ飛んで行き、「サルでも弾けるジャズピアノ」というような「ピアノ後発人間ご用達」本を探す。確かに、「やさしいジャズピアノ入門編」とか、「はじめてのジャズピアノ」とかの教則本はあるのだが、こういう本のページを開いてみると、そこにはピアノ初心者のド胆を抜く恐怖の二段譜のヒットパレードいやオンパレード。例の、左手用の「ヘ音譜」が下段、右手用の「ト音譜」が上段になって、「ピアノをやるならセットでどうぞ」というアレである。思わず怒った。
「てやんでい、こちとらピアノ初心者でい。チマチマ左手を動かせる能力があったら、初心者用の教則本なんぞ探しちゃいねえやい!」
つまり、「はじめてのジャズピアノ」とは、いままでいろいろピアノの曲はやってきたけれど、ジャズをやるのは初めてという人向けの本であって、ピアノも初めてなどというようなヤカラに準備する教則本はない!ということなのであった。
ピアノを弾きたい傷心のオジサンとなった僕は、悔しまぎれにギターコード(ピアノコードでもあるのだが)の載っているジャズスタンダード曲集を買って家に帰ることとなった。
家に帰ってつくづくと曲集をながめてみると、ジャズのスタンダード曲といわれるものに、なんだかやたらと♭が多くついていることに気がついた。一つがついていれば「F」の曲だというのは、キーとなるギターコードが「F」と指示されているからわかる。ところが、「Bフラット」「Eフラット」「Dフラット」などというコードの曲まであって、ギターで弾くのも面倒クサい、ましてピアノじゃ弾き方も分からないというコードのオンパレード。それでも、コツコツとやりましたヨ、僕は。で、そのうち慣れというものは恐ろしいもので、たいていのコードにはサッと指が行くようになる。
ところで、その時期にハタと気がついたことがある。これほどまでに「楽器の王者」いや「音楽の王者」として君臨しているピアノなのに、そのしくみ(鍵盤の並び方など)がきわめて不合理だ、ということである。ギターで「ファ・ラ・ド」の和音つまり「F」のコードを弾き、左手のカタチをそのまま2フレーム高くスライドさせると「G」のコードになる、ということを以前に書いた。いわゆる「バレーコード」と呼ばれているもので、これを知った途端、その人のギター知識や能力は飛躍するという合理的なしくみだ。ピアノには、それらしいことがまるでないのである。すなわち、「速習法」がないのだ。「速習法」がない以上、コツコツとおぼえるしかないワケで、正直いって、コレは僕には向いていないナ、ということになる。
しかし、向いてはいなくても、ピアノが弾けるオジサンにはなりたい。
そうこうするうちに、知り合いが「バンドやろうゼ」と声をかけてきた。もちろん、ジャズをやろうということだ。声をかけてくれた友人のカワベさんは、大学時代の「ジャズ研」経験者で、あの巨大なウッドベース所有者でもある。そのまた彼の知り合いに、世が世ならプロになっていた、というイケダさんがいて、この人はピアノを弾くという。それを聞いた瞬間、僕はハーモニカ少年と歌うお兄ちゃんの二つの時代のあいだに眠る「サックス狂時代」の夢を再び思い出し、玄関のドアを飛び出すと、お茶の水楽器店街へと走って行ったのであった。
|