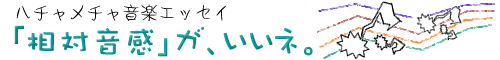●唄を失くしたこの国で
1998年冬の長野オリンピックは、世界のごく一部のスポーツファンを感動させ、メダル大好き日本のスポーツファンを大いに満足させた。ごく一部というのは、あれは地球上の「寒冷地限定五輪」と名付けるべきイベントで、日本国民や北半球の人間が大騒ぎしているほどには「世界最大のイベント」というフレコミに疑問が残るからだ。
さて、その長野オリンピックの開会セレモニーを垣間見て、予想通りにガッカリさせられた。もともと舶来ミュージカル大好き、だから翻案演出ばかりしてたら大家になっちゃっただけの人物が演出するというので、オリジナリティに期待する気持ちはさらさらなかったが、あそこまで陳腐とは予想もしていなかった。大ゲサな音量には満ちあふれていたが、音楽的な表現力には大いに欠け、なによりもこの国の今をリアルにアピールできる魅力的な「お祭りの唄」のカケラも存在しなかったのだ。
僕なんぞ、ああこういう場にふさわしい「お祭り音楽」が日本にもちゃんとあるのにねえ、などと残念な思いをした。もうちょっと古びてしまったかも知れないが例えば、ウルフルズの「ガッツだぜ」が流れる。トータス松本クンがお約束通りにステージ中央でバタリと倒れる。すると会場から手拍子足拍子の声援。再び立ち上がったトータス松本クンが、旧倍の力を得て、さらに熱唱。会場は興奮のルツボと化し、やがて開会宣言!
さぞかし盛り上がったことだろうけれど、ま、これも個人の好みのことだから仕方がない。あの手のイベントを手掛けるためには、やっぱり文部省(今じゃ文部科学省だっけか?)のお墨付きが必要なのであり、官の見守るイベントはあの程度ということにさっさと見切りをつけない僕が悪いのだった。
ところで、スポーツにはナショナリズムがアッケラカンと介在して、それが故にもっと盛り上がるというのは当たり前のハナシだ。「寒冷地限定五輪」などとは違って、こちらは本物の世界規模の大会「ワールド・カップ・サッカー」が98年にフランスで開催された。
あれを見てつくづく気がつくのは、奇妙なことだが平均的な日本人の音感の良さである。
試合開始前、対戦する両国の選手がフィールドに一列となり、国歌斉唱の場面。カメラは当事国の選手にアップで迫り、それと同時にかすかに選手の歌声が聞こえてくる。
おお!バティストゥータが、デルピエロが、ジダンが、ロナウドが、大写しになって歌っているではないかいな!
そして、聞こえてくるなんと調子っぱずれの歌声よ!
その時、つくづく僕は思うのだった。天は二物を与えない!いや、才能豊かな彼らはルックスも良くて、だから三物めは与えられないと言った方がいいのかも知れない。
これに比して、我がニッポン選手の音感の良さよ!だいたいこの国では、プロのスポーツ選手はTVの特別番組で芸能人と競演する「歌謡大会」に出ることが、大きなステータスなのだ。
デブを職業的使命とする力士たちや、「しまって行こうゼ〜!」などと絶叫することを競技の一部として成長してきた野球選手の、まるで音楽とは対極の立場にいそうな人びとの意外なまでの歌のウマさよ!
ワールド・カップ強豪国のア然とするほどの調子っぱずれに対して、日本のスポーツ選手の、これは「相対音感」の良さを表わす好例なのではないだろうか。ひいては、この「相対音感」の良さが、日本全国をカラオケ天国にしちまったのではないかいナ、などと僕は思っている。
それにしてもトゥールーズで、ナントで、リヨンで、スタジアムの6、7割を埋め尽くした若い日本人サポーターたちの「君が代」大合唱には、僕は複雑な思いを禁じ得なかった。あれは、国歌なのだろうか。あれは、国民の気持ちが相和し、鼓舞する共通の意志でまとめられたメッセージなのだろうか。とんでもないことだ。「相対音感」に優れた現代の日本人は、それと裏腹に「唄」の持つメッセージ性、つまり言葉の力を失っているように思えてならない。でなければ、あんな国歌を平然と歌えるはずもない。
しばしば国同士の戦争にも擬せられるワールド・カップをTV観戦していると、僕にも人並みの愛国心あるいは同胞意識がメラメラとわき上がり、「それ行け、ソウマー!」「打てっ、ゴン!」などと絶叫している。しかしながら、「いざ決戦!」の直前に意識を鼓舞する国歌斉唱では、なんとも複雑な面映ゆさを感じてしまう。
「おいおい、コレって国歌なの?」
「だって天皇サンちのご家族賞賛ソングでしょ?」
「あんまり縁はないからなあ」
「これがある間は、どうしたって自虐史観から抜け出せんゾ」
「もっと景気のイイ国歌にしちゃ、どうだい?」
「果たして、国の歌はボクの歌と言えるのだろうか?」
いきなり音楽の話題から逸れてしまったようだが、コレだって立派な「唄」の問題、つまり音楽の問題なのだ。
同様に、1996年のアトランタ・オリンピックを見た時、僕が驚いたことがある。アトランタを州都とするジョージアの州歌が、いつの頃からかオールドファンにはたまらない「我が心のジョージア〜Georgia
on my mind〜」になったと知らされたことだ。盲目の黒人歌手レイ・チャールズが歌い、世界的大ヒットとなったあの名曲である。州歌が、民衆文化から誕生した例である。
僕は今、「月刊メジャー・リーグ」(ベイスボールマガジン社)で英語実況に関するコラムを連載するほどのベイスボール狂だが、そもそもアメリカ野球に魅入られたのは、7回の表を終了した時点で観客全員が総立ちとなって歌う「野球場に連れてって〜Take
Me Out To The Ballgame 」の歌の魅力もキッカケの一つだった。日本の熱狂的なタイガース・ファンが歌い続ける「六甲おろし」の全国共通ソングみたいなものだと思えばいい。ただし、アレほど軍歌調ではないけどネ。
僕はひたすら長嶋さん1個人のファンなので、タイガース・ファンの思い入れはよく分からないが、それでも仲間たちのあいだに共通の「唄」を持つ彼らを祝福したい。
●唄と音楽のはざまで
オリンピックやワールド・カップが商業主義なくしては成功しないように、現代では音楽の状況にも同じことがいえる。音楽の送り手側の最大の関心は「売レル」「売レナイ」であり、大多数の受け手の関心は「ハヤッテル」「ハヤッテイナイ」ということにつきてしまう。残念なことだ。いまや音楽は「製品化」され、「パッケージ化」され、そのギョーカイは巨大産業になった。
僕はこれを、必ずしも否定的な見方でとらえているのではない。商業主義は、同時に音楽の大衆化をもたらしてくれたのだ。かつてその時代はちょっと魅力的ではあったけれど、「深窓の令嬢」たちだけがタシナむ特権的趣味ではなくなったのだ。
小づかい程度で買えるCDやカーラジオやTVといったメディアを通じることで、北海道凸凹町の青年も、沖縄県○×村の少女も、同じ歌を同じように歌うことができる。あるいは、イギリスの最新ヒット曲を、僕をふくめた日本のオジサンがたちどころにおぼえてしまうことだってできないことではない。
メディアの発達とコマーシャリズムは、音楽の普及という意味で最大の武器になっている。
それにしても僕は、どういうわけか、コマーシャライズされた音楽の多くに「唄」を感じることができない。「唄」のないところに音楽の喜びもまたない。
僕は音楽とはセンじつめれば「唄」なのだ、と思っている。
そして、「唄」のないところに音楽という空気は生まれないと思っている。
ついでにいえば、音は空気を伝わって人間の耳に入ってくる。絵画を視覚芸術、音楽を聴覚芸術とはよくいわれる。音楽とは、そのさまざまな音の表情の連続性を、時間的に体験するものといえるだろう。そういう継続的な時間の中で、人間の時間・空間感覚にある種の異変を起こしてくれるものがきっといい音楽なのだろう、と僕は考えている。「ワタシはダレ?ココはドコ?イマ何時?」などというドラッグ効果を、いい音楽は持っているのだと思う。
そういう意味で、パッケージ化され、コマーシャライズされた大量生産の音楽には、日本中の駅前広場がどこも同じに見えたり、似たようなプレハブ住宅がどこに行っても立ち並んでいるのと同じような印象を持ってしまう。
音楽的要素の同じパーツ、同じ色彩、同じ素材がやたらに耳につくばかりで、時間・空間感覚の異変はちょっと起こりずらいのだ。
しかし、今日の日本で、音楽ギョーカイを巨大産業化させ、それを支持している圧倒的多数の人びとは、僕なんぞとはずいぶん違う見方をしているようだ。「売レル」あるいは「ハヤル」のにはそれなりの理由があって、音楽だ、唄だなどとシチメンドクサいレベルの問題は関係ない、と。「それなりの理由」とは、あくまでマーケット理論に裏づけられた「それなりの理由」なのだから、あまり深く考える必要などないのだ。答えはカンタン。「ま、いいじゃん」という空気が、時代全体そして今日的音楽を支えている。
それにしても、「売レル」「ハヤル」というのは、つまり音楽の受け手の側の価値観の均一を意味しているワケなのだから、百万枚あるいは2百万枚も売れるCDが年間にいくつも生まれる現状は、やはりなんだか気持ちがワルい。
一見、自由そのもので、なにものにもしばられないはずの若者たちでさえ、実は「ユニフォーム化された価値観」で音楽を選んでいるのではないか、と思う。ルーズソックスと茶髪と眉剃りとブランド漁りとCDランキング。この四者はどこかイコールで結ばれる気さえする。
このことは、音楽の送り手にも、受け手にも、共通して言えるのではないか、と僕は思っている。
ファッションがそうであるように、音楽の受け手がどういう音楽を選ぶかというのも、その人にとって重要なアイデンティティーの問題であるハズだ。
ところで僕は、長く広告の仕事をしてきた。新聞・雑誌などのマスメディアと呼ばれるものや、SP(セールスプロモーション)というもっと直接に販売促進にからむ仕事もこなしてきた。要するにロクデナシの何でも屋の二流コピーライターだ。
この広告で、でき上がった作品の質以上に広告効果を決定づけるのは、「露出」という問題だ。もちろん、写真用語ではないし、ヒトケの少ない裏通りでコートの前を開いちゃったりするアノ行為でもない。
どんなイイ製品も、そしてどんなイイ広告表現も、それをカタチにした作品(たとえばポスターなど)が、目立つ場所に、目立つ時間に、対象となる性別や年齢層の消費者にくりかえし見たり聞いたりしてもらえること・・・・それがなければ、戦略としての広告は成功しないのだ。
かつて、「歌は世につれ、世は歌につれ」という言葉があった。広告も同じで、元気のいい製品や会社のまわりには、元気のいい広告があって、時代とともにその元気の一翼をになってきた。
しかし、音楽の現状を広告屋の視点で分析すれば、明らかに「歌はプロモーションにつれ、露出につれ」ということになる。
ミリオンセラーを記録するヒット曲のほとんどが、あらかじめCFソング契約されていたり、TV番組のテーマ曲になってふんだんな露出をした結果というのが相場なのだ。
現代は広告の時代だ。A社のBという製品が売れるか売れないかは、大きく広告にかかっている。同じように、Aという歌手のBという歌が売れるか売れないかも、また大きく広告にかかっている。
工業製品のように、音楽は売られる。工業製品のように、音楽は買われ、消費される。
だからいま、音楽はけっして主体的に選ばれてはいない、と僕は思う。ヒット曲は、仕組まれた戦略のもと、生まれるべくして生まれているのだ。そういう意味で、自然発生的に大ブームとなるような音楽は、ここしばらく出ていないのではないかと思う。
それは、広告屋も含めTV屋さん、各種企業、カラオケ屋さんたちの陰謀である。つまり、「ヒット曲はカンタンに作れる」というセオリーと、「音楽の魅力=ヒットの理由じゃないもんね=PRがすべてを決めるんだもんね」の三段逆スライド方式セオリーによって、この国のとりわけ若い人たちの音楽的な想像力が操られているのだろうと思う。
〜 次号につづく 〜 |