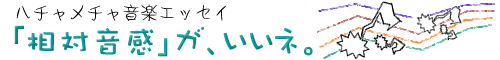●日本版「ピアノ・レッスン」の悲劇
カワベさん、イケダさんなどと始めたバンドは、当時ゴルフに熱中していた僕でも、バンドをとるか、ゴルフをとるかと質問されれば、即座に「バンド!」と叫んだに違いないほど面白かった。朝一番のティーインググラウンドの第1打は、どんなゴルファーも緊張の極を味わうが、僕の場合、バンドはその比ではない。「せーの!」で始まるある1曲のテーマが終わり、さてサックスのアドリブソロ直前になると、1人の聴衆もいないのに、僕の心臓は口から出てきそうになる。十代の頃、自分の思いを初めて女のコに打ち明ける直前の気分そのものなのだ。
「どう伝えよう、どうしゃべろう、どう歌おう」
もっとも、この緊張のおかげで、僕のサックスはちっとも進歩がない。
さて、バンド活動が始まると、僕のピアノ活動はいい加減なものになったが、頭の中に一つの陰謀が張りめぐらされるようになった。
「自分はついにサックスを手に入れた。ジャズピアノをマスターするには大変な訓練が必要だから、僕にはちょっと荷が重すぎる。セガレにピアノをしこたま習わせて、いつか2人でデュオをやろう!」
こうしてわがセガレは、好むと好まざるとにかかわりなく、ウムをいうヒマなど与えられず、僕のキョーハクとハゲマシとオダテとホメソヤシなどなどを背負って、ピアノ教室に通うことになった。セガレが4才のときのことだ。
結局のところ、セガレは7年間ピアノと格闘し、小学校5年の終了時に、父親である僕がアッと驚く「ピアノ放棄大宣言」をして、ピアノの牢獄からオサラバしてしまった。まったく、親のエゴはわがセガレには通じないのだった。
僕の落胆は大きかった。バイエルからやりはじめ、やがて発表会の季節になると、子どもピアノでお決まりのブルグミュラーを弾くようになり、ついにはベートーベンの曲をものにするまでに成長したセガレだったが、どうも「やらされている」という意識が最後まで抜けなかったというのが実情だった。観察していると、セガレにとって課題曲などを練習することは苦痛ではないようだった。むしろ、いかにも気に入ったという感じの曲のときには、子どもながらにガンガン弾きまくる。ト音記号だけの楽譜から、例の下にヘ音記号の五線譜がくっついた2段の譜面が中心の教材になった頃、同時に指練習の教材までふえて、ピアノのお稽古はいよいよ「ピアノ訓練」という様相になってきた。僕が歌うお兄ちゃんだった高校生時代に、例の「マママママママママー」の発声練習を部員たちにさせるために猛特訓したのと似たようなヤツである。それをセガレは両手でやる。さらに、これでもか、これでもか、とバリエーションが指示され、この先どんなに上達しても、このような「地獄の訓練」が待ち受けているに違いないと思わせるほど、果てしなくつづく感じだった。アッという間に、セガレが遊びでピアノの前に座る時間が少なくなった。
ある日、僕はたまりかねて、セガレのピアノの先生に打診してみた。
「センセー、セガレのヤツ、近頃ちっとも練習に身が入りません。アタクシ、なんとかセガレにジャズピアノを弾くようになるまではガンバッテもらわないとなりませんので、馬鹿オヤジに免じて、ここはひとつハードな訓練ばかりでなく、ピアノで遊ぶ楽しさってものを中心メニューに加えてやっちゃーいただけないものでございましょうか」
「おトーサマ、お気持ちはよっく分かります。ですが、どんなピアノを弾くにせよ、やはり基本とゆーものが大事でございますですからデスマスカラス」
セガレが「ピアノ放棄大宣言」をして以来、僕の家のピアノは、ほとんど音楽されないピアノと化して数年間が経過した。ピアノの上にはところ狭しと物が置かれることとなったが、コンガやマラカスといった安物の楽器の他は曲集などで、いちおう音楽の聖域といった見かけは保っていた。ピアノのフタが開きっぱなしになっているのは、「父親の夢破れたり!」をしみじみと感じるための、自分自身に対するいわば腹イセだった。
「勉強などしなくていいから、ともかく遊べ」という方針でやってきたが、「ピアノ過大期待症」のオヤジの熱い視線は、セガレには相当なプレッシャーとなっていたはずだ。そんな親心を十分に知った上で、きゃつめ、ムホンに出たのである。なだめすかしつつ、だましだまし練習させてきた7年間は、かくして終わった。
「おっ父、僕ピアノをやめます」
そうして、世の中にゴマンとある「音楽されないピアノ」のもうひとつの物語が我が家で生まれることになった。セガレとデュオを、という陰謀は、はかなくも無残に打ち砕かれたのだ。
もっとも、その数年前にも、夢は夢のまま終わるだろうという予感はあった。
ある晩、六本木のクラブでアメリカの高名なジャズピアニストのウォルター・ビショップ・ジュニア(この人物も今は故人)を見掛け、質問してみた。
「ミスター・ビショップ、僕のセガレも将来ジャズピアニストにさせたいんだが、どうしたらあなたのようになれますか?」
もちろん、酔った勢いのコワイモノ知らず発言である。ウォルター・ビショップ・ジュニアは「スピーク・ロウ」という名曲・名盤でジャズファンの多くが知っている伝説的な人物だ。彼は、面倒くさそうに僕を一瞥すると、「お前の息子は、ピアノが好きか?」と問い返してきた。
「いや、それが、あまり練習は好きではないようです」と、僕。
「だったら、あきらめろ。彼はピアニストには向いていない」
考えてみれば、あまりの正論。謝してその場を辞するよりない。ピアニストに、とかプロに、という期待は、半分ジョークの夢物語だったが、「楽器遊び」や「音楽遊び」は、セガレに伝えておきたい楽しみであることだけは確かだった。
タレントのビートたけしが、以前テレビでこんな発言をしていた。
「セガレがサッカーをやりたがっていると聞けば、なんとなく仕事のツテでベルディ(Jリーグの当時は川崎)の連中にも聞いてみた。そしたら、つぎに会った時にはミュージシャンになるんだというから、高い楽器も買ってやった。どうせミュージシャンになるんなら日本なんかで勉強していないで、イギリスとかで勉強する手があるって、向こうの学校のことを調べていたら、野郎、どうしたと思う? すっかり楽器なんて放り出して、懸命になって勉強していやがる。『おっ父、一生懸命勉強するから、どうかオレのことを外国になんか追い出さないでくれ』、だって」
スケールは違っても、僕の家庭の事情とちょっと似通ったところがある。親ゴコロは、結局子どもには理解されないのだ。今、高校3年生になったセガレは、それでもしっかりバンド兄ちゃんになってギターで遊んでいる。2002年春にアメリカ語学留学させるのも、半分はヤツの新たな音楽経験を見越してのことだ。フフフ。
しかし、それにしてもピアノのヤツめ!
●我が家から、ピアノへのレクイエム
世の中にゃゴマンと「音楽されないピアノ」があることは、読者もご存知のことだと思う。くやしいかな、我が家のピアノもそういう運命をたどり、決定的な悲劇として、その姿を消した。最大の原因はセガレの「ピアノ放棄大宣言」だが、あとは、このピアノを弾くサックスオジサンが7年ほど前に大病を患い、我が家で売れそうなモノの第一候補という栄えある名誉を授かって売り飛ばされたのだった。文学賞受賞の知らせがあと数週間早かったら、きっと今でも立派な「物置台」だったはずだ。
ところでハナシは変わるが、「ウサギ小屋」とか「ウナギの寝床」などと形容される日本の住宅事情は、ケイザイ大国といわれる今日でもちっともかわっていない。我が家だって同じだ。で、この住宅サイズを考えると、どう見ても外国生まれのあのピアノの図体はデカい。図体がデカいということは、それだけで圧倒的な存在感のあるものだ。我が家では僕の仕事場の六畳間に、ウチでいちばんエラソーな態度で、デ〜ンと黒光りして居座っていた。
では、それほどまでに存在感のあるピアノが、多くの家庭でなぜ音楽されないデクノボーになってしまうのだろう。一般論として、ピアノは、それぞれの家庭の「旬」の時期を過ぎると、まるで「音楽されない」状態となって、カバーを掛けられた上にお父さんのゴルフコンペ優勝のトロフィーやら、北海道土産の熊の木彫りの置物やらが並べられるハメになる。「ほかに使いみちがないから物置き台にでもしておくか」という扱いである。それがけっして珍しいことでないのは、あるいは、読者の自宅がぴたりこれにあてはまるかも知れないと、僕は予想するからだ。
いったいどうして、ピアノは「音楽されなく」なり、ピアノの持ち主は「音楽しなく」なってしまうのだろうか。
たいていの場合、日本の家庭でピアノを購入するタイミングは、子どものピアノ教室通いがキッカケだろう。習字、そろばん、バレエに加え、近頃ではスイミングやサッカー教室もハバをきかせている。ピアノ練習は、そんな「習い事」のひとつとして始められる。わがセガレ同様、バイエルに始まり、メトードローズやソルフェージュ、さらにはブルグミュラーの曲集に入ったあたりになると、ピアノ教室の先生主催の小さな発表会に出始めちゃったりなんかして、やがてモーツァルトやショパンに取り組むようになると、もう立派なピアノの弾き手となる。両親が目を細めつつ、ウチの子は天才ではないか、と思ったりする至福の時期だ。
一方、子どもの方は課題曲ばかりでなく、さまざまな指使いに関するノルマ(地獄の特訓)と悪戦苦闘しながら、それでもいちおうケナゲに練習に励む。
そして、「音楽される」ピアノと「音楽するための訓練する」子どもとの蜜月は数年間つづくことになる。まさに「旬」の季節だ。
しかし本来この時期のピアノと子どもとの関係は、あくまでも「やがてたっぷりと音楽する」ためのステップに過ぎないはずだった。ところが、娘なり、息子なりの成長に応じて、事態は一変してしまう。受験勉強というやつだ。
「せっかく習い始めたピアノだから、ピアノ教室をやめても週に1度ぐらいは気分転換にさわってみよう」と考えたのが、やがて月に1度となり、そのうちピアノカバーの上に物が置かれ、ついには「まったく音楽されない」無用の長物となって、使われていた時よりもさらに「邪魔だ」という理由で、ピアノの図体は大きくなっていく。結局、音楽するための立派な道具だったピアノは、さあこれからいよいよ音楽されようという段階で、粗大ゴミもしくは文化の香りのする(?)重厚なインテリアのひとつになるのである。
なぜ、こんなことになってしまうのだろうか? なぜ、ピアノから音楽は流れなくなってしまうのだろうか。ひとつには、ピアノ購入の動機が、あくまでも「子どもの情操教育の一環」と考えられているからだ。子どもの情操教育なのだから、子どもの幼・少年少女期を過ぎれば、もう情操教育などといっているヒマはない。そんなことより、まず受験勉強だ。乱暴ではあるが、こんな筋書きが容易に想像できる。
ところで、子供の情操教育を願う親の頭の中をのぞいてみると、「音楽」とは名ばかりの「音学」指向が見えてくる。この「音学」指向は、親ばかりではない。ピアノのために用意されているさまざまな教材や、それを使って教える側の問題、さらには当の生徒さえも、やがて音楽ができるようになるための「音学」と了解しているフシがある。そうでなければ、あんな難しい楽譜で、面倒な指使い練習に時間を費やしたりはしないのだ。どうして、ピアノの場合、「音楽」は「音学」になってしまうのだろう。そして、どうして人びとは「音学」時期の修了後には、もう「音楽」を楽しもうなどと考えないのだろうか。どうして、ピアノのフタは閉じられてしまったのだろうか。
僕のセガレの場合は、幸か不幸か、学習塾やら受験勉強とは無縁だったが、あのいつ終わるとも知れない地獄の指使い特訓がイヤでネを上げた(もちろん、オヤジの熱すぎる視線が煩わしかったことも大きな原因だということは、僕だって自覚している)。つまり、オヤジには「音楽」をヤレといわれているのに、実際のピアノ練習は「音学」そのものであり、身の回りにはテレビやコンピュータゲームやミニ四駆など楽しいことがいっぱいあるのだから、ピアノなんてやってられないヨ、ということだったに違いない。
本書を書きはじめてしばらくたったある日、音楽に関する面白いネタはないものかと、セガレを尋問室に呼び込んだ。もう5〜6年も前のことになる。
「おっ父、『ドレミの歌』って知ってるよネ。アレって、ヘンなんだヨ」
「ナニ?いったい何がヘンなんだ?」
「ピアノで弾くとよく分かるんだけど、『ド〜はドーナッツのミ』なんだゼ」
「なんのこっちゃ」
「『レ〜はレモンのファ』なんだゼ」
「では『ミ〜はみんなのソ』なのか?」
「ソの通り!」
「ソーなのかぁ!」
いいネタをもらったと喜んでいたが、考えてみたら喜んでばかりもいられない。ヤツの苦難のピアノ訓練時代と楽譜にしばられた音学教育のカゲのようなものが見え隠れするエピソードとも思われ、フクザツな気分となった。
ええい、もうこの際だから正直に言おう。ピアノという楽器を自在に弾く人を見て、他のどんな楽器を弾く場合よりも「スゴイな!」と感じたことがないだろうか。ピアノを弾ける人は、弾けない人に比べて、「ちょっとしたステイタス(イヤな言葉だナ〜)を感じるナ」と思ったことはないだろうか。子どもの頃、多くの人がチャレンジし、できるようになった「猫ふんじゃった」は黒鍵だけでできる曲だが、白鍵も黒鍵もよりどりみどりに取り混ぜた曲を、ムズカシそうな楽譜を見ながら弾きこなす人を見て、なにか尊敬にも似た気持ちを抱いたことはないだろうか。そういう経験が、僕にはある。
そして、ある男優が歌ってヒットした『もしもピアノが弾けたなら』という曲は、ピアノが弾けない人の単なるあこがれではなく、「弾けっこないけどネ」というあきらめや、「弾けることはスゴいこと」という過大な思い入れが塗りこめられた曲なのではないだろうか。
音楽はスゴいこと、ピアノはスゴいもの、楽譜はなんだかとても高尚なもの、などというすべての「音楽権威主義」のようなものは、すべてピアノという楽器の持っている「寄りつきにくさ」に原因がある。「音楽権威主義」のゴンゲのようなピアノは、しかもその構造にギターのような理にかなったやさしさなどミジンもなく、訓練(または権威)に柔順なもののみを受け入れる。もちろん、いまでも僕のピアニストへの尊敬は大きいし、これがジャズピアニストとなったらあこがれも尋常ではない。まるで神様のような存在に見えてしまう。
しかし、なんだかピアノはヘンである。不均一なピアノの白鍵と黒鍵の並び方はヘンである。少なくとも、学校などの音楽教育の場で、あの理にかなっていない楽器や楽譜が堂々と居座っているのはヘンである。
そんなグチをこぼしていたら、ある日、バンド仲間のイケダさんが面白いハナシを持ってやってきた。そのことは同時に、僕に絶大にして膨大な損害を被らせる原因になるとはこの時まさか予想もしていなかった。 |