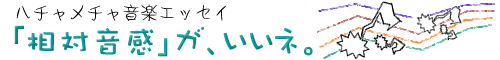●その後のハーモニカ少年
小学校6年のときに、器楽クラブというのに入った。
入ったというのが正しいかどうか、あまり記憶がハッキリしない。ハッキリしない理由のひとつが、ハーモニカほどにはそこでやったチェロに身が入らなかったからだ。そしてもうひとつの理由が、あれはカリダサレたのではないか、というものだ。
1962、3年頃のいなかの小学校にはめずらしく、その小学校の器楽クラブはいわゆる弦楽アンサンブルで、バイオリンなど他の楽器と比べて大ぶりな2台(台というのかナァ)のチェロと1台のコントラバスの担当だけが男の子で、あとは全部女の子だったからだ。何かのコンクールに出るために、なり手のなかった低音楽器に、なかよしだったスズキ君やミヤウラ君などとカリダサレたのではないか、と思う。
ともあれ、そこでは有名なオッペンバッハの曲「天国と地獄」を練習した。パリのムーランルージュなど、フレンチカンカンという少々イロっぽいダンスではお決まりのように必ず流れる、あの曲である。
身が入らなかったワリには、どういうワケかいまでもチェロのパートをおぼえている。ピチカート(弦を指ではじく奏法)で始まり、途中から弓を持って弾く。
ここで、大きな問題があった。僕はまるで譜面が読めなかったのだ。譜面が読めないだけではなかった。調弦、いわゆるチューニングというのも、練習前に音楽教師が「どうせキミたちにやらせるとロクなことにならないから、さっさとお貸しなさい」とチェロを奪い取り、勝手にやっていたように記憶している。
なぜ、そう思うかというと、記号的なものの記憶にかけて子供時代は誰でも卓越していたはずなのに、やっていたチェロの四弦の音が何だったか、まるでおぼえてもいないのだ。もしその当時、自分で調弦していたのなら、おぼえていないはずはない。
同じチェロのミヤウラ君は、楽譜を見ながらさっさと練習する。コントラバスのスズキ君も、自信たっぷりに弾いている。僕はというと、横目でちらちらとミヤウラ君の指使いを盗み見しながら、山なりに連なる音符をなんとなく比較し、それでも自信なげにボソボソと弾いていた。
あの栄光のキャンプファイヤー御用達ハーモニカ少年の胸の内に、大きな挫折感が広がていった。
中学校では、はじめに運動部に入った。ところが、その時代にもしっかりとあった体育会系のイジメ体質がいやで、バレーボール、そしてバスケットボール部をすぐにやめた。絵を描くことが好きだったから、美術部に入った。ところがこれが、極めつきの退屈。で、とうとう再び音楽関係へ。
入ったブラスバンド部では、すでにほとんどの楽器が定員締めきりで、空いているのはアルトホルンだけ。ホルンといっても、あのフレンチホルンのような逆さベルのようなカタチの楽器ではない。ラッパの先が空を向いているチューバをコンパクトにしたようなものだ。1年上に先輩がいて、先輩は真新しい楽器を、新入りはラッパのあちこちにへこみのできた古くくすんだ楽器を持つ。
ブラスバンド部に入ってすぐに気づいたことは、ここもまた大いに体育会系のノリだということだった。体力作りにマラソンはするワ、部室に入るときには御用聞きのようなあいさつを義務づけられるワ、完全なタテ社会だった。
さて、しんちゅうがさびたような独特のニオイのする金管楽器を生まれて初めて手にしたハーモニカ少年は、大いに気に入ってアルトホルンを習い始めた。楽器に息を吹き入れる場所を「マウスピース」といって、それが取りはずし自在というのも初めて知った。アルトホルンより一回り大きいのをバリトンといい(チューバは僕の中学校にはなかった)、さらに巨大な金管楽器の親分がスーザホーンということも知った。
もっと驚いたのは、トロンボーンを例外に、金管楽器はほとんどすべての指使いが共通、ということだ。そして、低いドも、高いドも、真ん中のソも、指を開放して出せることが不思議だった。
音階は、それほど時間もかからずに吹けるようになった。ハッタリでない証拠に、いまでも指使いはおぼえている。
金管楽器をやったことのない人のために、音階の指使いを紹介しておこう。指は、右手の人差し指、中指、薬指を使う。なにしろ、シリンダーについたピストンを動かすボタンが三つしかないのだから。
ド<×××>、レ<○×○>、ミ<○○×>、ファ<○××>、ソ<×××>、ラ<○○×>、シ<×○×>、ド<×××> ※上から順に人差し指、中指、薬指で、×は開放、○は押さえる。
これだけ知っていたら、あなたが今日、万が一道でトランペットを拾った場合、すぐに音階練習に入ることができる。ただし問題は、マウスピースに吹きこむ息でラッパを共鳴させられるかだ。
アルトホルンは、しかしどこかパッとしない楽器だった。同じ金管仲間のトランペットやコルネットのようにキンキラした高音は出ないし、かといってバリトンやスーザホーンのように腹ワタにビリリと響くほど低音のド迫力もない。
いよいよ曲をやるという段になって、不満はさらに深まっていく。さあ、ブラスバンドの華、マーチ!
「ンパ、ンパ、ンパ、ンパ、ンパカパッパッパー」
キャンプファイヤー御用達ハーモニカ少年の歌心がウズいた。つづいて、日本の歌のブラスバンドアレンジ!
「ンパ、ンパ、ンパ、ンパ(長〜い休み)、ンパ、ンパパー」
このぐらい単純だと、楽譜はなんとなく分かってくる。今度は秋の文化祭の出し物、ラテンだ!
「ンパーパ、ンパーパ、ンパーパ、ンパーパ・・・・・ 」
未体験の読者のために解説すると、アルトホルンのパートは、ブラスバンドの伴奏パートとでもいったらいいかも知れない。もっと重低音のスーザホーンは、ロックバンドなどのベースラインのような音を担当するが、それほどの低音楽器ではない。ロックバンドのリードボーカルやリードギターの役割は、トランペットやクラリネットといった華やかなパートが担当するから、アルトホルンは文字通りエンの下の力持ち、中低音でリズムを刻む役割に終始するワケだ。
ハーモニカ少年は、あっという間に飽きた。
「バカヤロー、こんなこともおぼえられネーのかよ!」
部室の片隅から、センパイが1年坊主をなじっている声が聞こえる。
「だれかいねーのか、こんなヤツじゃなくて」
アルトサックスのセンパイが、おぼえの悪い1年生にイラついて、サジを投げたカッコウだった。
「僕、やります」と、退屈なアルトホルンからここぞとばかりにクラ替えしたのがハーモニカ少年だった。
1年生の夏、僕の町の高校の体育館に早稲田大学ハイソサエティーオーケストラがやって来た。僕が目にし、耳にした、最初のビッグバンドだった。ジャズやラテンの名曲をやったのだろうが、中でもアルトサックスがひときわ目立つ「闘牛士のマンボ」を聞いて、冷凍チキンになったように寒気がし、鳥肌が立った。そこでは、ハーモニカ少年のキャンプファイヤーの夜のように、アルトサックスプレイヤーは一人立ち、ソロを聞かせる。
僕のアルトサックス熱は、ちょっとひどいものがあった。登校1時間前には学校に行き、下校時間が過ぎても帰らず、楽器の持ち帰りが許される土曜日を、いつも心待ちにしたほどだ。
好事魔多し。中学1年の冬にケガがもとで大病をし、2年間の休学を余儀なくされてしまった。肺炎を併発したこともあって、吹奏楽器にドクターストップがかかった。
高校に入って、かつてのハーモニカ少年はすっかり歌を忘れたカナリヤ状態だったが、音楽の授業が終わると、今度は歌でスカウトされた。混声合唱の音楽部に男声パートが足りないというのだ。
合唱がとり上げるような音楽に興味がなかったわけではない。ロシアの赤軍合唱団やアメリカのミッチミラー合唱団、レイ・コニフなど、その頃になると結構聞いていた。ドイツリートやイタリアのオペラも好きな方だった。
しかし最大の入部動機は、女の園の中に少人数の男子生徒が堂々と入ることができることに間違いはない、と今だから白状しておこう。
合唱コンクールなどでは、僕の高校は大した成績をあげることはなかった。面白いのは、この合唱部が年に1度の文化祭でオペラを上演する伝統を持っていたことだ。担当教師のオリジナル作品という場合もあったが、僕が3年で中心だった時には、イギリスの作曲家サリバンが作った「ミカド」を、生徒たち自身の珍妙な翻訳で上演した。ハリウッド映画の中でも劇中のオペラシーンとして何度も使われているから、知っている人もいるはずである。日本では藤原歌劇団が上演する出し物なのだそうだ。高校生によるオペラ上演というのはユニークなはずで、当時の地方新聞にもとり上げられたほどだ。
もっとも、いまミュージカルをやる高校生は少なくないだろう。
いずれにしても、ハーモニカ少年は、歌うお兄ちゃんに変身した。
●マママママママママー
そろそろ読者が、僕の自慢にもならない自慢話に飽きてきたのではないかと心配になる。なぜなら、音楽シロートの僕の音楽歴は、幸か不幸かまだ終わらないのだ。
しかし、そんな不安を無視しつつ、つぎにススム。
さて、どんなクラシックの名演奏家でも、その成長過程では、これもまたクラシック音楽の超一流の先生から手ほどきを受ける。ピアノであろうが、バイオリンや声楽であろうが、先生からの指導の声が飛ぶ。キーワードは「歌」である。
「もっと歌って、もっと歌って!」、と。
いまではクラシック音楽のさほどのファンではなくなった僕だが、それでもその「感ジ」だけはなんとなく分かる気がする。
いつだったか、テレビの深夜番組を見ていて、そのことを強く再認識させられたことがある。
日本のナンバーワンともいえる超売れっ子のスタジオミュージシャン兼ジャズ&ロックミュージシャンなんだったらクラシックもやりまひょかという才能の持ち主で、ポンタなどという拍子抜けしそうな芸名(なのかどうかは知らない)を持つドラムス奏者が、スタジオに集まったミュージシャン志望の若者の質問を受けていた。「ポンタさん、日頃のドラムの練習はどうすればいいんスか?やっぱ、あんまシィ、大きい音トカ、出せないじゃないっスカ・・・・」
若者以上に見事にヨタモノを体現しているポンタさんが答える。「やっぱよう、練習でいくら叩いたって意味ねえんだよ。要は歌だよ、歌。よくレコード聞きながらリズムとってれば練習になるっていうけど、あんなのウソっぱち。オレは本番じゃなきゃ、タイコは叩かないっての。歌が分かってなきゃ、ドラムスなんてやれっこないワケ」
ポンタさんの言う「常識的な練習」不要論は、なかなかインパクトがあって興味深かった。そして、ことドラムスという楽器についていえば、きっとほんとうのことなのだろうナ、という気にさせられた。
実際、ハーモニカ少年から歌うお兄ちゃんなどモロモロを経た僕が、30歳を過ぎてバンドオジサンになったとき、痛切に感じたのもそのことだった。「叩くことは歌うこと」という非常にシンプルな事実が分かっているドラムスを、わがバンドはついに探しだすことができなかった。
なにしろドラムスという楽器は、スティックを10センチ上から落としただけでも、ドンガラガッチャンと十分に響きわたる音量を持っている。シロートがもっともカンタンな楽器と誤解しやすく、その反対にもっとも演奏効果の上がらない楽器でもある。
ためしに、とりあえず2本のスティックを持ってドラムセットの前に座ってみればいい。間違いなく、スティックを握った手に力が入る。で、一発叩いてみる。そして間違いなく、「スゲエ(いやスゴイ)」と、その大音量にビックリする。つづいて、3拍か4拍のリズムを叩いてみる。あまりの不均一な自分のリズムに、またまたビックリする。そして、上手なドラムスを聞いてみると、それはリズムを刻んでいるというより、歌の中の呼吸ともいうべきものを凝縮して、むしろいくぶん歌に先行して歌っている感じがある。
高校時代、混成合唱を中心とした音楽部に所属した僕は、3年生になってブチョーという肩書きをいただいた。いまのところ、我が人生最後のマットーな肩書きである。このブチョーの大切な役割のひとつが、毎日のクラブ活動の最初に行なわれる発声練習の音頭とりだ。金切り声、シャガレ声、鼻声、小声、ひそひそ声、ダミ声、調子っぱずれの声、アマギゴエなど部員たちのさまざまな声を統一させて、音階練習をする。
ついでに言っておくが、合唱の発声練習はハタで見ているとかなり気持ちの悪いもの、という常識(?)は僕にもある。ま、弁護させてもらうと、F1などのカーレースなどで本番スタート前に軽く1周コースをまわり、エンジンやタイヤをあたためておく、アレと同じことだ。なにしろ、カラダが楽器なのだ。
さて、ブチョーとなった僕に、ここでもまた新たな問題が発生した。発声練習をリードしていくために、歴代ブチョーは自らピアノを弾いてキー(指定の音)を指示することになっている。
ドレミファソファミレド。
半音上がって、ドレミファソファミレド。
またまた半音上がって(つまり最初はレの音から始まることになる)、ドレミファソファミレド。
後になって知ったことだが、これがいわゆる「固定ド」と「移動ド」の概念で、そんなことを知らなかった僕には、「レ」から始まる「ドレミファソファミレド」をピアノで弾くなんてことは、まさに至難のワザだった。もちろん、「ドの#またはレの♭(つまり同じ鍵盤のことだが)」から始めるのは、もう狂気のサタだ。ピアノのシロートにとって、白鍵から離れて黒鍵を使うのは、ある種の恐怖である。
ちょっと面倒くさいハナシだが、念のためにここでドレミファのおさらいをしておこう。
ド○レ○ミファ○ソ○ラ○シド。
もちろん、○印は半音が間にあることを意味する。つまり、○のところには黒鍵が用意されているワケだ。
先ほどふれた「レ」から始まる「ドレミファソファミレド」とは、この○印の入る間隔を基本のドレミと同じように入れることだ(そんなこたぁ分かっとる、という読者にはちょっとガマンしていただくしかない)。
つまり、「レ・ミ・ファの#またはソの♭・ソ・ラ・ソ・ファの#またはソの♭・ミ・レ」とピアノの鍵盤を押さえると、あの「ドレミファソファミレド」のメロディーが聞こえてくるワケだ。ギターのコードを知っている人にはおなじみの「D」のコードというヤツである。
合唱の練習では、そうやって徐々に音程を上げていく。そのとき、「ドレミファソファミレド」は発声上の共鳴を考えて「マママママママママー」となる。言葉のカツゼツをよくするために「カカカカカカカカカー」となることもあるし、気分次第では「ジジジジジジジジジー」となることもある。
ブチョーとしては、しかたがないからピアノを練習した。さらに、発声練習のバリエーションでもある「ドレミファソファミレドミソミド」というヤツも練習した。こっちはもっとヤッカイだった。後半の部分で音が飛ぶのである。したがって、鍵盤もトビトビになる。ひゃ〜。
ところで、問題はもっと根深いものがあった。
あのピアノの鍵盤を思い出してほしい。さきほどの○印と同じことなのだが、基本の「ド」から始めて右隣に順に上がっていくと、鍵盤は「白・黒・白・黒・白・白・黒・白・黒・白・白」となって、最後の白鍵で一オクターブ上の「ド」になる。
白鍵だけで考えると、たとえば「ド」と「ミ」と「ソ」の音は、等間隔にある。ところが、黒鍵がからむとハナシはややこしい。
分かりやすい例でいうと、白鍵の「ド」と「ミ」の距離を「2」としよう。「レ」で「1」、「ミ」で「2」となる。ところが、その「ミ」から始まる(つまり「移動ド」のことだが)場合には、その距離が変わってしまう。「ミ」から始まる「ドミソ」では、「ド」と「ミ」の距離を数字に置き換えると「2.5」なのだ。
こういう事実は、ピアノのシロートにはいかにもキツい。僕らがやっていた西洋音楽の流れをくむ合唱の基本楽器でもあるピアノは、実はこんなにも不親切な楽器だったのだ。
習うより慣れろ。で、どうにかこうにかブチョーのメンツを保ったものの、ピアノに対する「ナンダ、コノヤロ不自由な楽器メ」のイメージだけが強く残った。
〜 次号につづく 〜
|