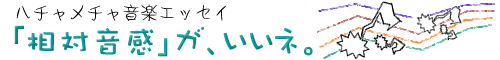●差別用語は、とても音楽的である
突然のハナシだが、たとえば知らない外国語というものが、すごく音楽的に聞こえるのは、僕だけのことではないはずだ。
実は5年前の春、念願かなって英語に関する本を出版することができた。僕は音楽狂オジサンであるとともに、スポーツ大好き中年でもある。
例のメイジャーリーグ入りしたヒデオ・ノモの一連のバッシング報道と、掌を返したようなその後の礼賛報道が気持ち悪くて、ヒデオ・ノモの登板試合が放送される場合には、日本流の報道ではない現地の声が聞きたくて、無理ヤリにも副音声の英語実況で聞くことにした。これが、そこそこ英会話力には自信があった僕でも、当初はまるで音楽のように聞こえる。「スイング・アンド・ミス」という、ヒデオ・ノモが相手バッターを空振りさせたときによく聞こえた実況の言葉は、僕にはどうしても「スイング・イン・ザ・ミス」に聞こえてしまう。それでも、日本に野球というスポーツが根づいてから長い歴史があることだし、その中で知らず知らずのうちにたくさんのカタカナ英語をおぼえてしまったことで、英語による野球実況があまり音楽的でなく、言語的に聞こえたおかげでできた仕事だった。
しかし、そもそも僕が大学で仏文学科を選択したのは、意味もわからなかったイブ・モンタンの「枯れ葉」に魅了されたのがキッカケだったし、若いころにほんのひと月ほどラジオのスペイン語講座を聞いた理由も、スペイン語によるラテン音楽の魅力があったからこそだ。もちろん、その他まるで意味不明な言語は、僕には意味のある記号としては聞こえてはこない。「ジャンボ」以外のスワヒリ語や「アンニョンハシムニカ」とあと少しの韓国語、「グーテンモルゲン」と「ダンケシェーン」以外のドイツ語、「ニーハオ」とか「シェーシェー」以外の中国語など、ほとんどすべての外国語は音楽的にしか聞こえてこない。言葉というものが、いかに音楽的(あるいは音律的)なものであり、そのことが普遍的な事実であるかという証明だ。意味を持つ音としての記号、それが音声的な言葉である。
言語そのものと音楽との関係は、こうして切っても切り離せないものになるわけで、イタリアオペラの邦訳がまるでイタリアオペラっぽく聞こえなくなったり、アメリカのブルーズに日本語をのせると演歌のように聞こえてしまうのもそのためだ。これはむしろ言語学的にも無理のないハナシで、いわば日本人の外国語習得にとって大きな構造的な問題でもある。
専門外のハナシなので(じゃ、何の専門か?)あまり確かなことは言えないが、日本語の1字1音節で生まれる音楽性と、英語のような場合とは、ずいぶんな違いが現れて当然だと思う。たとえば、野球用語の「ストライク」は、日本人にはあくまで5音節の単語だが、英語の「strike」となるとほんの1音節でしかない。これを歌詞の中に入れた曲を作る場合、日本では「ス・ト・ラ・イ・ク」と音符は5つ用意されるのが普通だし、英語の場合には1つである。そんなこともあって、なぜか日本語の歌詞はハーモニカ少年だった頃からまだるっこしくて、メロディーはしっかりおぼえているのに歌詞をちゃんとおぼえていない曲が多い。逆の意味で、外国語の歌詞には、メロディーと言葉の強勢(アクセント)が一致している場合がほとんどで、音楽的にピタッとはまる感じがする。で、どういうわけか、「イッヒ・リーベ・ディッヒ」などというオーゲサなベートーベンの曲とか、「クィカイマニマニマニマニダスキー・・・・」などと歌うインドネシアだかどこかの民謡なども、意味も分からずにおぼえてしまい、何十年たっても忘れない。
ジャズピアニストの山下洋輔さんは、言葉の面白さと音楽とをゴチャマゼにして、とびきり才気を感じさせるエッセーを縦横無尽に書きまくっているが、僕が腹を抱えて笑いころげ、同時にナルホドとうなったハナシがある。東京郊外の中央線沿線に、「ムサシコガネイ」という駅がある。で、この駅の名前のあちこちにアクセントを置き換えて発音してみると、これがなかなか面白いのだ。
こういうことを他人以上に面白がる傾向は、僕自身の出生地に関係がある。なにしろ、東京からも大阪からもほぼ等距離の場所だから、「坂」や「雨」などのアクセントが町ひとつ行くともう違ってくる。これは方言による違いである。
最近になって、若者たちのあいだで、意図的に言葉の本来のアクセントを変えてしまうのがハヤっているようだ。ディスコの後ガマとして、ここ数年来大いにハバをきかせている「クラブ」。これを山下洋輔さん流に別の言葉でアクセントの同じものを探してみる。英語の正しい発音によるアクセントの置き方は、日本語の「おまる」「おでん」と同じ。「おまる」のアクセントの波形が英語のclubには近い。しかしこれが日本語化し、オジサンたちの使うゴルフクラブやオジサンたちが通う銀座のクラブとなると、そのアクセントは「金庫」とか「ホスト」などと同じである。こういうイントネーションで発音する「クラブ」を、若者たちはダサイと感じるらしい。僕も、そう思う。で、彼らがもっぱら使っているのは「クラゲ」とか「鼻毛」などと同じイントネーションである。僕は、もっとダサイと思う。
なぜ僕が、「金庫」の「クラブ」以上に「クラゲ」の「クラブ」をダサイと感じるかを説明しなくてはならない。
まず、「金庫」がダサイのは、「クラブ」の英語の意味もスペルも知っているのに、実際の英語のclubで苦労させられたからだ。音楽的に表現すれば、歌詞は同じなのにわざわざメロディーを変えて歌わされていたようなもの、だからだ。最初に日本語化したヤツの音感の悪さを恨むばかりで、そんな例は山盛りにある。
そして、「クラゲ」がダサイのは、そういう悪例がゴマンとあるのに、しかもこれだけ国際化の進んだ時代なのに、「金庫」や「ホスト」よりもっとキミョーな方向に言葉を追いやっているからだ。
「あそこのクラゲ(いやクラブ)でやってる音楽、チョーいいんだよなー」
こういう「クラゲ」イントネーションのヤツに限って、音楽についちゃ知ってるゾ、てな顔をしているからもっと始末に悪い。省略や造語による三文字言葉のほとんどが、「クラゲ」「鼻毛」のイントネーションばかりで、ほとんどバリエーションというものがない一本調子。彼らは、自分たちの仲間だけに通じる、いわば言葉のスラング化を通じて、自分たちの仲間以外の世代を差別しているわけで、こういうやり方は、別に新しくもなんともない。ただもう少し、音楽的であってほしいと思うのは、まさに余計なお世話かも知れない。
さて、誤解を恐れずにいえば、日本語の中にさまざまある伝統的な差別用語のほとんどが、音楽的である。盲目、難聴、言語障害、跛行、精神異常、醜女、肥満・・・・。これらの大衆的差別用語のほとんどが、効果的に(つまり、どぎつく)被差別者に伝わるために、まるでくり返しを想定したかのように、あるいはあたかも意図的に破裂音をふくんでいたりする。
メクラ、ツンボ、ドモリ、ビッコ、キチガイ、ブス、デブなどだ。
美しい音楽というのは存在するが、音楽的であるということが必ずしも美しいということと結びつかない場合だってあるのだ。
●「英語教育」「音楽教育」ふたご説について
ところで、僕の英語力の基礎をつくったのは、多分音楽である。英語力とエラそうに言ってみても、まあ大したことはない。高校時代に英検2級というのをとって以来、単語の数が飛躍したとか、読解力が2倍になったとかいう自覚は、まるでない。それでもちょっとだけ、他人よりアドバンテージがあるとすれば、英語の持っている音に対して少し敏感かナ、というところだ。アメリカのメイジャーリーグ・ベイスボールの実況も、最初のうちは他の外国語と同様に意味のわからない音楽的な音にしか聞こえなかったが、「なんだコレって野球用語で知っているカタカナ英語で十分理解できるじゃないか」と聞こえるようになったのは、耳から入る英語だったからだ。すると、いま注目のNBAもNFLも、さしたる苦労はいらないということになった。もちろん、百パーセントわかるなどと大ソレたことは言わないし、わかろうと努力した経験もない。
音楽は、僕の英語力にどのように貢献しただろう。
例えば「Moon river wider than a mile・・・ 」は、「ムーンヌリヴゥーワイドゥーザナマイ」となって僕の脳ミソにインプットされることとなったし(カタカナとしてではなく、あくまで音的に)、「She
sees the sea」のそれぞれの音の違いは、中学校で英語をやりはじめたときからわかっていた気がする。
本書で、僕は冒頭から「音楽とは、結局『唄』だ」と書いてきたつもりだ。そしてそれは、必ずしも「歌詞のあるもの」と限らないことも書いてきた。さらに、「言葉は、きわめて音楽的である」とも考えている。
さて、TOEFULという、英語を母国語としない国の人のための英語力検定試験というのがあるのだそうだ。5年ほど前のことだったと思うが、その試験結果の国別平均点というのが発表された。世界に冠たる教育大国ニッポンの、そこでの成績が最悪であると知らされて、読者は驚くだろうか。
あまりハッキリとした記憶ではないが、参加した世界約120カ国の後ろから数えて何番目かだったと記憶する。日本より下位にはアジアだかアフリカだか、どこか名前さえも聞いたことのない発展途上国があるだけだと、あるニュース番組のキャスターが言っていた。アジアの隣国、韓国や中国ははるか上位にいるのに、である。 誰がお墨付きを与えたのか知らないが、日本語はムズカシいものという常識が、われわれ日本人自身にある。「ホンマかいな!」と思う。日本語は他の言語に比べ、言語体系が違う、だからこそ英語などの他の言語の修得は日本人に不利なのだと、勝手にヘ理屈をつけている。
それでも日本語と韓国語はとても“音楽的”によく似ていて、海外旅行に出掛けた時、背後から聞こえてくるのは韓国語とばかり思っていたら日本語だったなんて僕自身の経験もあるし、その逆も体験した。僕の友人のオーストラリア人も、この2つの言語は音的にすごく似ていて区別がつかない、などと言っていたのを思い出す。きちんとベンキョーしたわけではないからエラそうなことは言えないが、そんなに似ている言語のはずなのに、日本人と韓国人の英語力に大差がついているのはどういうわけなのだろう。
だいぶ以前、大前研一氏が、「日本人の外国語習得能力は、英語だけじゃなく、フランス語もドイツ語も、世界サイテー!」と言い放つのを聞いたことがあるが、決して選挙に落ちた直後の腹イセとは思えなかった。実際、僕ら日本人は、中学・高校果ては大学まで行って英語を勉強しても、ほんのささいな日常会話にも不便する。
いったい、「I am a boy. 」というような、日本で英語の基礎中の基礎と考えられているような文章が、実際の英会話で役に立つであろうか。「私は、男の子です」と、他人に自己紹介する主人公はいると考えたのだろうか。この会話にいったいどんな返事が返ってくると考えたのだろうか。
「へえ、そうですか」「そうは思えませんね」
あるいは、「This is a pen.」という文章。「そんなことは分かっています。アナタは私をバカにしているのですか?」という返事以外には考えられないではないか。 かくして、日本の英語教育は、これを受けたもののボー大な時間の浪費という結果だけをもたらして、大学出という立派なインテリとしてのキャリアを持つ人であっても、海外旅行の折りには「サルでも分かる英会話」というような安直なマニュアルを持って出掛けているのが現実なのだ。
ある意味で、理由は明白だ。言葉の持つ最大の要素「音楽性」について、それを無視しつづけてきたからだ。僕がここで言う「音楽性」とは、もちろん「聴覚」を意識したからだが、もうひとつ大切なのは「呼応性」とでもいうべきものだ。こちらの方がもっと重要なのだ、と僕は思っている。
僕は野球ファンなので、メイジャーリーグ中継でピッチャーが投げた球がストライクゾーンに入れば「strike」ということを知っている。すると、中継でも「strike!
」という英語の音声が聞こえてくる。「going going going・・・it's gone!」という実況は、バッターの打球が「行った、行った、行った・・・・入りました!」と、ホームランが生まれた場面で聞いたもので、これなどきわめて音楽的であり、状況に対する呼応性のカタマリのような表現だ。
そしてもちろん、いい音楽には呼応性がある。音楽における呼応性とは、即興性のことだ。演奏者の立場なら、直前までの音の動きにどのように呼応するかであり、いい音楽を聞いて心を動かされるのは、聞く人の感性がその音楽に呼応しているからだ。
ハナシがだいぶあらぬ方向に行ってしまったが、言いたいことはこういうことだ。世界最低水準の日本の英語教育と音楽教育というのがどことなく似ている、と僕は感じているのだ。
実際の「使える英語」では無用の長物でしかない、腹いっぱいの文法の勉強。一方、実際の「楽しめる音楽」では無用の長物でしかない、頭の痛くなる楽譜や楽典の勉強。最終にして最大の目的が異文化とのコミュニケーションであるはずなのに、まるで呼応性のない英語教材とその指導ぶり。最終にして最大の目的が「他者と喜びを共有できる音楽」のはずなのに、どこかの権威者ばかりが良いとする音楽のおしきせ。
ハーモニカ少年の時代からずっと感じていたことだが、たとえば楽譜が読めるようになることは音楽にとってとても便利なことだが、だからといって音楽ができるようになることとは別問題である。ハーモニカ少年の時代にはちっとも知らなかったが、英語力が世界最低の国民なら、音楽力も世界最低なのではなかろうか・・・・。
「教育される感じ」が、なんだか似ているんだよね。 |