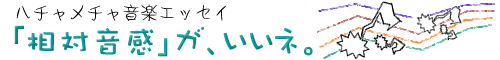●愛することと、歌うこと
いわゆる学校音楽の伝統と、最近の音楽教師の人物像について、僕は貴重な追経験をさせてもらった。5年ちょっと前、僕のセガレが都内の区立中学に入学し、クラブ活動に吹奏楽部を選んだのだ。かつてのハーモニカ少年の息子といっても、セガレはハーモニカにはあまり関心を寄せなかった。それでも音楽は好きなようで、小学生のときにはどうやらピアノと歌に自信を持っていたらしい。
もっとも、僕のたっての希望でやらせていたピアノに関しては、小学校5年の最後になって堂々と「ピアノ放棄宣言」をしてやめてしまった。僕の落胆は大きかった。それについては、このあとのコラムでふれることにしたい。
ところで、セガレの希望する楽器は、アルトサックスだった。もう一度、ふれておかなければならないが、かつてハーモニカ少年だった僕は、その後歌うお兄ちゃんとなり、やがて30歳を越えるあたりでピアノを、さらに35歳ぐらいになったころサックスオジサンに変身していたのだ。中学校時代のほんの数カ月のあいだ夢中になったアルトサックスが忘れられなくて、ついに30歳を越えてから、念願の自前の楽器を購入したのだった。決して安くはないシロモノである。
事実、東京で知りあい、いまでは無二の親友となったオーストラリア人のサックスプレイヤー、イアン・ウォレスには「お前の楽器は、クルマでいえばBMWだ」といわれるほど分不相応のもの。しかしそれ以上に、愛しあって切り離された恋人にふたたびめぐりあった気分で、買った当日は抱いて眠りたいほどの興奮を覚えたものだ。楽器好きの少年少女なら、そんな気持ちをきっと分かってもらえると思う。
前置きが長くなった。セガレが中学の吹奏楽部に入り、しかもサックスをやりたいと希望していることを知ったときの、僕のうれしさといったらなかった。まるでマンガの1コマのように「ムフフ、ムフフ」というカタカナが頭の中に鮮明に現れたりもして、セガレに向き合う自分の顔がゆるみっぱなしになってしまう。これではイカン、オヤジとしての威厳が・・・・などと考えても、ほっぺたがフニャフニャ状態なのであった。幸か不幸か、サックス吹きでプロになるような才能は持ちあわせていない僕だが、自分の息子が家業を継いでくれることを知ったときの職人の気持ちが分かったような思いだった。ともかく、僕がいちばん愛してやまない楽器がアルトサックスなのだ。ほっぺたフニャフニャ状態と化したのも分かっていただきたい。
それにしても、僕はアルトサックスという楽器を愛し、大親友は海の向こうのサックスプレイヤーであり、なおかつシロートが持つにはちょっとゼータクなほどの「BMW」があり、おまけにセガレがサックスをやりたい、ときた。これを喜ばないオヤジがいるだろうか。
しかし、セガレは第一希望のサックスを吹かせてはもらえない。学校から帰ってきて、少しばかり落ち込んだ様子のセガレに聞いてみた。
「希望は希望として出させたけど、その子にいちばん合った楽器かどうかを決めるのは、プロのコーチなんだってサ」
事情を聞いてみると、クラブ顧問の音楽教師は吹奏楽の専門ではなく、クラブが部費を集めて、どこかのオーケストラに所属するオーボエだったか何かの専門家をコーチに招いているのだそうだ。そのコーチが、「キミはパーカッション」というご託宣を与えたというのだ。
音楽教師が吹奏楽の専門家ではない、というのは分かる。そこで吹奏楽の専門家を招いてコーチをしてもらう、というのもなんとなく理解できないことではない。しかし、たかだか区立の中学校の一クラブ活動で「そこまでするか?」というのが、正直な僕の感想ではあった。
教育の細分化や専門化というのは、なにも悪いことではないけれど、これでは吹奏楽を専門に勉強した音楽教師がいなければ、中学校に吹奏楽部は存在できない、というハナシになってしまう。セガレのハナシでは、この中学の吹奏楽部は区や都の吹奏楽コンクールで毎年入賞する優秀な成績をおさめているのだそうだ。僕の胸に、なにやら悪い予感がかすめる。
それよりなにより、せっかくセガレがアルトサックスを吹きたいという「タナからボタモチ」的な僕にとっての朗報は、いったいどうなるんだ。
考えてみてほしい。あの伝統的な「大ダイコは男の子」という音楽的偏見が、まるで現代にも残っているようではないか。それよりなにより、いったいなぜ、最初に希望楽器など聞く必要があったのだろうか。しかも、希望はできるだけかなえるというハナシだったのだ。一緒に入部した別の子のケースを、セガレにたずねてみた。ある女の子の場合、父親が昔からフルートをやっていて、いつか娘と一緒に演奏できたら、という夢があったのだそうだ。「おお、その気持ち分かるよなあ」と、僕などは無邪気にそんな父親にエールを送ってしまう。セガレの他、唯一の男子入部を果たした子の場合も、希望楽器はフルートだったそうだ。たった3例を聞いただけでも、吹奏楽部での楽器配当はいかにも面倒な感じがすることも事実である。そして、我がセガレと同様、この二人も、フルートとは似ても似つかぬ別の楽器を、とご託宣をいただき、それに従うこととなったらしい。ハッキリしないが、どちらかがトロンボーンだったと記憶する。
一方、せっかく選んだクラブで希望楽器ができないセガレは、ちょっと落ち込んだ。僕の親としてのアドバイスは、こうだった。
「教師が決めたことは、なにも最終的な結論ではない。どうしても自分自身がアルトサックスをやりたいのなら、自分自身で意思表示してみろ」
どうやら、セガレはそのことを音楽教師に伝えたようだ。
「夏にコンクールがあるから、今だけはパーカッションをやってほしいけど、それ以後、サックスをやりたければ、希望をかなえてくれるってサ。でも、先輩に聞いたけど、そんな例は今までなかったって」
セガレの観察がおそらく正しいことは予測できた。まして、数カ月とはいえ、子供のことだ。その間の楽器の習熟度には大きな差がつくはずだ。なぜ、希望楽器について生徒たちに競争をさせないのか。なぜ、プロといわれる人のツルの一声がすべてなのか。なぜ、当初希望の楽器をアンケートしたのか。ここは素直に、クラブ顧問の音楽教師の教育観なり音楽観を聞いてみたい、と思った。
中学校にクラブ顧問の音楽教師を訪ねると、返ってきた答えはこうだった。
「お父サマ、うちの学校は毎年コンクールで入賞を続けている伝統のあるクラブです(ザマス)。吹奏楽には楽器のバランスというものがあって、生徒1人1人が好きな楽器を自分勝手に選んでいたら、入賞なんぞとてもおぼつかないものになってしまいますヨ(ザマス)」
カッコ内は、音楽教師の放つ空気である。
「でも、希望楽器の動機とか、希望の度合いとかはご配慮いただけないのですか。新1年生でサックスになった生徒さんは、どうしてもサックスというわけではなかったようですが」
今度は妻の質問だった。
「お母サマ、例えば野球のことを考えてください。野球では、みんながみんなピッチャーをやりたがりますよね。どうなりますか、チームは」
おお、スゴイ飛躍的発想!と、僕は思った。実は、セガレは小学校の高学年3年間、少年野球チームに入っていた。もちろん、ピッチャー志望の子が多いことは想像できるが、少年野球をはじめる子供すべてがヒデオ・ノモやヒデキ・イラブにあこがれるのではないし、イチローや松井選手やマイク・ピアッツァの場合もある。セガレのあこがれは、バットをビュンビュン振り回すライオンズの佐々木外野手だったしし、僕の頃なら、「サード長嶋」である。そんな思いが頭をかすめながらも、目の前の若い女性教師の権威主義的な決めつけに、夫婦で目を見合わせていた。
「ともかく、そうシンケイ質におなりにならず、まずはお子さんにはガマンすることも大切だというふうに申し上げたいですね。吹奏楽では、そうした全体の調和のための個人個人のガマンも大切な要素ですから」
「なにを!ガマンが大切な音楽的要素だと?バカいってんじゃねえや、このザーマス教師!」
と、僕も言いたいところだが、彼女が実際にザマスを連発していたワケではないし、学校というところが明らかに子供を人質に出している場なので、グッとこらえた。
僕がセガレの吹奏楽部入りとアルトサックス希望を知って喜んだのは、音楽と恋仲になるに違いないセガレを祝福してのことだった。この恋は一生もので、人によっては自分がハマった楽器をしばしば「性悪女」のように言ったりもして、それだけセガレのこれからの人生を大きく左右する出会いになると確信したからだった。ところが、ザマス教師とプロのコーチは、息子の初恋に横ヤリを入れ、いきなり「今はダメでも、つきあってみればいいコと分かるわヨ」と見合いを強制する。僕がセガレを祝福したのは、アルトサックスという楽器(あるいは女のコ)とつきあって(デートして)みることで、コンクールの入賞など、どうでもいいことだ。まず、愛すること。そして、愛することが、歌になり、音楽につながるのだ。帰宅後、セガレに吹奏楽部を退部することをススメたのは、言うまでもない。
ウソのような余談だが、フルートを一緒に演奏することを夢見ていたという、セガレと同時入部の娘さんの父君が、その年の夏、何かの病気で亡くなられた。娘さんの心に、父親との音楽的な思い出がたくさんあることを祈るばかりだ。
●音楽するなら、遊びなされや
せっかくのサックスオヤジの夢を打ち砕かれた恨みは、まだまだこんなことではおさまらない。もっとも、いろいろと事情を考えてみれば、セガレの退部についてはかえって良かったとさえ思っているが・・・・。
しかし、である。もう一度ムシ返すが、中学校の吹奏楽部の指導に、吹奏楽の専門家は必要なのだろうか。僕自身がほんの数カ月在籍した中学校のブラスバンド部には、音楽教師以外の指導者はいなかった。楽器演奏のイロハを教えてくれるのは、もっぱら先輩の役割で、そんなところに学年を越えた交流があったのだ。技術レベルはともかく、こんなにも音楽を愛し、こんなにもサキソフォーンを愛する1人の人間をつくったことだけは確かである。そんな程度以上のことが、生まれて初めて手にする管楽器を使ってする音楽のクラブ活動に必要なのだろうか。
もちろん、プロのコーチは、あくまでコンクール入賞をめざすもので、僕もそのことをとやかく言うつもりはない。ただ、2点だけ、僕の納得いかないことがある。
1つは、音楽教師が吹奏楽については分からない、と答えた点だ。音楽ではないか。指使いや音の出し方程度は、高学年の生徒に教えさせればいいではないか。何が分からないと言うのだろう。音楽教師は音大で、「音楽の基本とは歌うこと」と教わらなかったのだろうか。彼女の専門は歌唱なのだろうか、あるいはピアノなのだろうか。それでも答えはひとつ。「歌うように吹け」、それで十分ではないか。そしてなにより、彼女の専門は中学校教師ではないのか。生徒が希望する楽器をあきらめるというガマンが最初にあって、それから楽しめるようになるのが、吹奏楽の本質なのだろうか。どこからそんな奇妙な教育理論が生まれたのだろうか。
「希望楽器をそのまま好き勝手に生徒にやらせてしまうと、どこかの学校のように非常にバランスの悪い構成になってしまって、いい成績が上げられない」
と彼女が僕に話した「バランスの悪い吹奏楽部」は、コンクールの成績はともかく、音楽を楽しんでいなかっただろうか。サックス狂オヤジの希望や、病床で娘とフルートを一緒に吹くことを楽しみにしていた父親の夢をかなえるなど、親と子と学校を音楽でつなぐことは、何か教育理念に反するものがあるのだろうか。
もう1つは、楽器の特性についてである。プロの演奏家には、その子供にあった楽器を選ぶ目がある、というハナシ。僕には、そんなデタラメな理屈がまかり通ることが不思議でならない。
断じていうが、楽器の相性というものは当人の希望の度合いであり、唇のカタチでも、掌の大きさでもない。コメディアンのタモリ氏が数種類の楽器をこなすことは有名だが、学生時代にいちばん熱心に練習し、いちばん愛着を持っているらしいトランペットについて、テレビでこんなハナシをしたことをおぼえている。
「オレの唇は薄いんでネ、トランペットにゃ向かないんだよネ」
これをしたり顔でいうものだから、視聴者のほとんどが「ナルホド」とうなずいてしまう。多少の真実をふくんでいるとしても、彼の発言の奥底には「音楽的才能の欠如」やら「努力不足」つまり「愛情不足」のいいわけがチラホラ見える。単純なことだが、音楽に関する才能とは、音楽をどの程度愛しているかであり、楽器との相性は、楽器をどの程度愛しているかで決まるものでしかない。文学的才能も、絵画的才能も、同じことだ。右手が不自由でありながら世界的に高名なピアニストはいるし、第一、あのベートーベンが晩年失聴したことはあまりにも有名だ。
それにしても、日本の音楽教師や音楽教育に「音楽」の最大要素である「楽」の字のカケラもないのはなぜなのだろう。西洋音楽に限らず、もともとあらゆる音楽が持っていた「即興性(インプロヴィゼーション)」という「臨機応変さ」、言葉を換えれば「出たとこ勝負」とか「やってみなはれ」につながる精神の豊かさが、なぜこの国の音楽教育の現場から失われているのだろう。
もちろん、答えとしては大半の音楽教師にそうした才能がないからであり、音楽だけでなくあらゆる分野でマニュアル人間がふえているのだから、当然といえば当然のハナシなのだ。マニュアルには、即興の中身までは指示されていない。
で、ちょっとつまらない仮説を考えてみた。「音楽=オンガク」という言葉が持っている語感に大きな原因があるのではないか、と。とくに「ガク」の語感が、イケナイ。「ガク」は「学」に通じ、ほとんどの音楽教師は「音学」と考え違いしているのではないか、ということだ。少年期の、これから音楽と本格的につきあっていこうという世代に向けた音楽教育では、どう考えてみても「学び」の中から豊かな音楽を見つけることなどできはしない。
「仕事をするなら、遊びなされや。」
昔、ヒットした某洋酒メーカーのキャッチフレーズである。
「音楽するなら、遊びなはれや。」
音楽教師に、いったいどれだけこの言葉がわかる人材がいるだろうか。
もう10数年も前のことだが、東京・青山の子どもの城で「ジャズ・フォー・キッズ」というコンサートがあり、まだヨチヨチ歩きのセガレを連れて見に行ったことがある。世界的なベーシストのポール・ジャクソンとその奥さんが中心となり、音楽の成り立ちというようなものをストーリー立てて演奏する。キーボードやトロンボーン、サックスなどには、日本の一流ジャズメンが参加し、当時2、3才だった我がセガレなどは喜びまくってステージ上で踊るわ、キーボードは鳴らすわの大ハシャギ。ジャズというワクなど関係なく、子供のための音楽教育の一つの理想形を見る思いがした。
耳をそばだてさせる。音で合図する。踊らせる。騒がせる。楽器にさわらせる。歌わせる。そして、なにより楽しませる。
実は、小中学校での音楽教育は、こういう一連の楽しみ方を通じて、音楽的興味や感動を体験させることがいちばんだと思う。そして、世の中の大半の教師も、そのことにうすうす気がついているはずである。
ところが、彼らの受けてきた音楽教育や音楽教師マニュアルには、そのノウハウがないし、彼らは、教材としての楽譜にしがみついているだけなのだ。これには、僕は音楽家や社会全体の責任というのもあるのだと思う。さまざまなジャンルを超えて音楽の面白さを伝えようという試みは、テレビの「題名のない音楽会」あたりがやっていたともいえるのだが、かつての番組司会が権威そのもののマユズミさんでは、はなっからクラシック臭がプンプンとにおってしまう。
ジャズびいきだからいうわけではないが、クラシック1本ヤリの学校音楽関係者のみなさん、日本のジャズメンたちの音楽的優秀さをちょっと教育の場で生かしてみてはいかがですか。目からウロコですよ。ドビッシーだろうが、ショパンだろうが、彼らはなんでもやっちゃいますゼ、きっと。
|