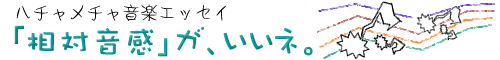●ビートルズがもたらしたもの
日本のフォークソングブームこそが、この国から「歌文化」をなくしてしまったのだと指摘する人がいる。これはあくまで私見だが(もちろん本書すべてがそうなのだが)、フォークギターに熱中した連中とエレキギター層のあいだに、この時代になってハッキリと音楽的深度のようなものの差が現れたように見える。すなわち、チャリティーの大御所イズミヤさんのような例外を除けば、フォークギターを手にして登場したかつてのミュージシャンたちは、お笑いタレントにくら替えしたり、医者になったり、走る農業従事者になったり、エラい評論家のセンセーになったりして、「遊ぶだけ遊んだし、稼げるだけ稼いだから、もういいよ」とばかりに音楽圏を去ってしまった。
デモも終わったし、伝えたいメッセージもなくなっちゃったし、ということだろう。僕などは、これを音楽的な探究心のなさ、または音楽へのボートク、はたまた音楽的才能の欠如、とどのつまりは彼らは音楽そのものに深い関心があったワケではなかったのネ、という結論にたどりつかざるを得ない。
ところで、このフォークソングブームは、その世代の若者たちにギターブームをも巻き起こすキッカケとなっていった。もちろん、それ以前にも「テケテケテケテケ」でおなじみのベンチャーズに代表されるエレキギターブームというのがあったワケだが、エレキギターでは演奏能力というのを結構問われたのに対し、フォークギターはもっとお気軽伴奏楽器として登場したように思う。
以前、「青春デンデケデケデケ」という映画を見る機会があって、その原作者がほぼ僕と同世代で、エレキギターに熱中した高校時代へのノスタルジーともいうべき内容であることを知った。幸か不幸か、僕自身はエレキギターを手にしたことはないし、当時のベンチャーズをはじめ日本のグループサウンドにも熱中したことのないヘンなヤツであった。しかしエレキギターは、紆余曲折はあったにしても、その後も延々とミュージシャン志望の若者たちを中心に根づくとともに、インストゥルメント(楽器)だけで聞かせるバンドというのも次々に登場してきた。今日の音楽のベース(ギターのことではない)になっている楽器、それがエレキギターだといっていい。そして、そのことを決定的なものにしたのが、ビートルズなのだろうと思う。
後に、僕は東京のある大学の文学部に入った。友人たちとキャンパス内で文学を論じたことはなかったが、音楽談議にはまさに花を咲かせたもので、ビートルズ登場後の若者文化に、いかに音楽が重要な位置を占めるようになったかの典型的な例だろう。ただし、僕の大学入学時には確かビートルズはすでに解散していて、僕らが語り合ったのは「自分たちの音楽体験」ということについてだった。その後、僕がサックスを吹くバンドおじさんとなって多くの同世代の人たちと音楽談議をしても、ビートルズの影響の大きさには毎度驚かされるばかりだった。一万五百三十七人の人と話し、一万四百五十九人が「自分の世代に最も強い影響を与えた音楽」としてビートルズの名前を上げた。
しかし、ハーモニカ少年だった頃から僕はヘンなヤツだったし、闘病生活で2年間の社会からの隔離生活を送ったり、その後に歌うお兄ちゃんになったりしていたおかげで、僕にとってはビートルズはさしたる存在ではなかった。だから、僕らの世代をはじめ、その十年ほどさかのぼる世代までの全体を、あたかも当然のことのように「ビートルズ世代」と呼ぶことには抵抗を感じていた。
それでも一方で、その時代のオトナたちが一斉にマユをひそめた長髪や(実際のビートルズはマシュマロカットで大した長さではなかったが)、どうヒイキ目に見ても上手とは言えない演奏力(真正ビートルズファンに殺されそうだ!)での音楽スタイルは、やはりその後に決定的な影響を与えたのだと思う。ビートルズファンでない僕でさえ、彼らによって次々に生み出された音楽の新しさと質の高さについては、ただただ尊敬の念を抱く。今でも、彼らの演奏にではなく、彼らが残した数々の名曲に感動してしまうし、その気持ちは、歳月を経てだんだんと大きくなっていく。
しかし残念ながら、我ら「ビートルズ世代」が受けた最大の影響は、肝心カナメの音楽作りそのものではなく、彼らのファッションや演奏形態だった。3、4人集まればバンドができるゾ、ボリュームを目いっぱいに上げればロックになるゾ、そしてきわめつけが、「とりあえず、バンドやろうゼ」というノリをもたらしたのだった。
そしてギターは若者音楽の主役となり、それまでの「禁じられた遊び」に代表される正統的(?)演奏スタイルを学ばなくても、さっさとできる「コード奏法」の知識が、あっという間に広まっていった。こうして、ギターは若者の音楽に欠かすことのできない決定的なアイテムとなり、街で聞こえる音楽だけでなく、自分たちで楽しむ場合にも「音楽=ギター&ボーカル」のパターンが確定したのだと思う。
かくして、僕らの十代、二十代の頃の若者、とくに男のコの場合には、音楽などとほとんど無縁に思われていた柔道部の猛者も、分厚いレンズで丸メガネの化学部のガリ勉タイプも、たいてい1、2曲のギターレパートリーを持っていたはずである。
さて、いまの十代、二十代の若者たちはどうなんだろうか?どっちにしても、このギター文化は、テレビやレコードなどのメディアの発達や普及とともに、若者たちと音楽とのかかわりを一変させたことは事実である。内緒だけれど、ただ今17歳のセガレがパンクロック兄ちゃんなので、そこらへんの情報も結構入ってくる。がはは。
歌うお兄ちゃんとなっていた高校時代最後の年、謝恩会だか何かの催しがあって、僕は音楽部2年後輩のマツシタマコト君と二人のギター&デュオで何曲かのフォークソングを歌った。ピーター・ポール&マリーやブラザーズフォアなどの曲とマツシタ君のオリジナル曲を体育館のステージのマイクの前でやったのだが、女生徒たちの歓声とあたたかい拍手に比べ、男どものやや冷たい視線が印象に残っている。どことなく、「フン、やりやがったナ」というフンイキなのである。
その催しのあった数日前、学校でマツシタ君と練習していたときのことだった。野球部だったか、サッカー部だったか、まるで軟弱な音楽など眼中にないゾというタイプの男子生徒がやって来て、ヒョイと僕のギターを取り上げると、「パフ・ザ・マジック・ドラゴン・・・・」をたどたどしくアルペジオで弾くではないか。無言でやって来て、無言で去って行った彼のメッセージは、こんなものだったと思う。
「ギターができるのは、オメエらだけじゃないんだゾイ」
意外なヤツが突然現れて、ガラに似合わない「パフ」をかわいらしいアルペジオで弾いて去って行く。役に立たない月光仮面のようで、僕とマツシタ君は目を見合わせてから抱腹絶倒ということになった。が、つまりそれほど当時の若者たちにとってギターで1曲ぐらい弾けないとカッコがつかない気分というものがマンエンしていたのだろう。硬派の歌わないお兄ちゃんが、自宅でこっそりとギターを練習していた風景を想像すると、なんだかほほえましい。
ついでながら、このとき一緒にフォークソングを歌ったマツシタマコト君は、その後ポピュラー音楽の学校に入り、数年後プロになった。彼の初アルバムは、僕の共演者のその後という名誉ある思い出とともに、いまでも我が家の棚の中にある。
「おーい、どうしているんだい、マツシタ君!」などと吠えまくっていたら、2001年お台場のフジテレビ出演の折り、僕の控え室にひょっこり訪ねてきてくれた。当日彼は別のスタジオでの音楽収録。僕の方はコピーライターとしての仕事だった。松下誠くん。あの人気アイドルグループ「スマップ」なんかのコーラスアレンジやったり、手広く活躍してると聞いて、なんだかウレシー。
●ギターが国民楽器にならないワケ
国民栄誉賞やら国民的アイドル、国民的行事など、なにごとも国民という言葉が好きなこの国にあって、今日「国民的楽器」にいちばんふさわしいのはギターだろう。実際、演奏できる人の数(ウマいヘタは問題としない)、保有台数、街に流れる音楽での使用頻度などなど、考えれば考えるほどギターの王座はゆるぎそうにない。
それなのに、である。それなのに、学校の音楽教育の中にギターが登場するというハナシをほとんど聞いたことがないのは、どういうワケなのだろうか。少なくとも30年近くのあいだ、世の中にあふれる音楽の中心を担ってきたのがギターであるにもかかわらず、なのだ。おそらく、ギターをやったことのある人ならほとんどすべての人が、こう思ったことがあるに違いない。
「音楽って、こんなにカンタンだったのか!」
タネ明かしはカンタンだ。ギター練習では、学校教育ではなんともムズカシそうにしか教えてくれない「和音」を、初歩の段階からさっさとやるハメになる。ハメになるというよりむしろ、和音をさっさと演奏できるようにするためにギター練習はされる。なにしろ大半のギター練習の動機は、さっさと歌うためである。メロディーは当人の歌なのだ。ギターは伴奏になればいい。で、六本の弦をポロロロロンと右手で弾くと、さっさと和音は出てくれる。問題なのは、その六本の弦を押さえる左手の指の位置である。これも、ギター教育を最初に編み出した人物が偉いというべきか、ギターとはそもそもそういうものなのか、一度にジャジャーンと六本の弦を鳴らす場合の左手の指の押さえ方、つまりコードというものがあって、これは図解されていたり、親切なものでは「コード一覧表」がついた教則本なんてものまである。もちろん、さだまさしが大好きなアルペジオ奏法などというのは、当初はとんでもないゼータクテクニックである。ここは質素に、ジャカジャカジャカジャカとやる。
最初は「C」というコードをおぼえる。カンタンなメジャー(長調)の曲は、コレで始まる。つづいて「F」と「Gセブンス」をおぼえると、ほぼ一曲分のコードをおぼえたことになる。なぜ、こんな面倒なカタチのコードをおぼえなくちゃならないんだ、などとは考えない。なにしろ、目の前にあるのはいまハヤリの歌いたい曲の楽譜なのだ。
コードからコードにさっさと移ることができるようになると、さあ、もう歌だ。ジャンジャカジャカジャカジャーン。できた。
つづいて、演歌などにありがちなマイナー(短調)の曲をやってみようか。「Aマイナー」と「Dマイナー」と「Eセブンス」をおぼえる。なぜ、こんな面倒なカタチのコードをおぼえなくちゃならないんだ、などとは考えない。なにしろ、目の前にあるのはレコードなりCDで聞いたあのヒット曲の楽譜なのだ。
こうして、歌いたい曲の伴奏がさっさとできるようになってしまう。考えてみたら、これがギターのものすごさなのだった。で、先ほどの「音楽って、こんなにカンタンだったのか!」という感慨と、「それにしても、学校じゃこんなこと教えてくれなかった!」という憤慨を感じたりするのである。
これに類することは、僕がギターコードを知るようになり、ギターで歌うようになった歌うお兄ちゃん時代のエピソードとしてすでに書いたが、「ギターはエライ!」とつくづく感じるのは、「F」に代表される「バレーコード」と呼ばれるものの使い勝手の良さを知ってからのことだ。たいていの人にとって、この「F」コードの習得がいちばんヤッカイで時間がかかったに違いない。
で、ある日、今度は「G」で始まる曲に遭遇する。楽譜の上の図解を見る。「C」の曲でおぼえた「Gセブンス」とどことなく似ているが、「Gセブンス」のコードで出した和音のニゴリのような音、決してこのコードでは終われまへんデという感じの音が混じっていないことが判明し、まるで「C」と同じように「ドミソ」の和音に聞こえてくることが判明する。さらに、このコードは「右のコードで代用することができる」として、もう一つの「G」のコードが図解されていたりする。よく見ると、おぼえるのにえらく苦労させられた「F」のコードにウリ二つではないか。もっとよく見ると、「F」で作ったバレーコードの指のカタチをフレーム二つ分だけスライドさせただけではないか!
こういう発見は、当事者にとってはもう大変な大発見なのだ。思わず「ヒエーッ!スゲエーッ!」と叫びながら、誰か友達に知らせなくっちゃいけない、という使命感さえ感じてしまうのだった。この驚きは、ある意味で、楽器のしくみを発見したことの驚きでもある。
さて、ギター初心者の驚きはこんなことでは終わらない。「G」で始まる曲でつぎに出てくるのが、なんとこともあろうにあの最初の「C」なのであった。もう一つ新しく登場した「Dセブンス」には驚かないが、なにしろギターをやり初めて最初におぼえた「C」が、ここで再登場してきたのである。「F」と「Gセブンス」との美しいセットで三位一体となっていたハズの、あの「C」である。
どうやらこうやらコードをおぼえ、さっさと歌の伴奏にとりかかる。すると、「G」のコードが「C」の曲で弾いた「C」のコードのように聞こえたのと同様に、「C」のコードは「C」の曲で弾いた「F」のコードのように聞こえてくるではないか。また、「Dセブンス」は、「C」の曲で弾いた「Gセブンス」のように聞こえてくるではないか。こちらの驚きは、純粋に音楽のしくみを発見したことの驚きであった。
つまり、「相対音感」の発見である。
もちろん、「音楽学的」ないい方をすれば、「C」「F」「Gセブンス」の和音とは、Ą、Ľ、Ś.の和声のことで、「アラ、そんなことは学校の授業でも習ったでしょ」と言われれば、ミもフタもない。しかし、黒板の五線譜上にオタマジャクシを並べられて解説されただけのおベンキョー知識と、自分から進んでした体験学習の中から得たものとでは、やはりウンデーの差があるのだ。まして、僕の記憶では、「G」「C」「Dセブンス」の和音の流れが、「C」「F」「Gセブンス」の感じとウリ二つだというような説明は、学校の授業で習った記憶がない。
これも、「音楽学的」な表現を借りれば、「絶対音感」と「相対音感」に関連したことで、僕らが受けた学校音楽というのは、「絶対音感至上主義」の帝国であったと、つくづく思ったりするのだ。
さて、ギター初心者はさほどの苦労もなく、やがてギター中級者となる。その頃には、「F」と「G」のバレーコードで発見した共通性はさらに広がり、「Fマイナー」と「Gマイナー」、「Bフラット」と「C」の共通パターンのバレーコードのかずかずを発見することとなる。さらに、スリルとサスペンスに富んだ「ディミニッシュ」コードの発見に鳥肌を立て、まるでSFの世界に引きづりこまれるかのような「オーギュメント」を発見し、快感に酔いしれたりもする。
あらゆる面で、ギターは分かりやすく、とっつきやすい楽器である。人によっては、理にかなった楽器だとも言う。カンタンな曲を弾けるようになるのに、ギターならほんの1週間もあればOKだ。僕がこれまで書いてきたように、あくまでも「音を楽しむという意味での音楽的なもの」の発見に、ギターというのはまさにシンプル&クリアーに答えを出してくれる楽器なのだと思う。
「国民的楽器」のこのギターだが、それでも学校の音楽教育の場でひんぱんに活用されているというハナシは聞かない。ピアノ主役主義、譜面大事主義、音学主義など、大金をつぎ込んだ自分たちの音大キャリアで得た音楽教育者たちの「既得権」が、ギターなどという「分かりやすすぎる楽器」を教育の場から閉め出している、としか僕には思えない。
世の中に、ピアノを弾ける人はほんのひとにぎりにすぎないが、ギターを弾く人はゴマンといる。そして、ギターを弾く「音楽を楽しむ人」は、学校の音楽教育とは無縁の場所でギターを習得する。ほんのひとにぎりのピアノを弾く人たちによってのみ、学校の音楽教育が牛耳られている現状は、やはりなんだかヘンだ、とは思いませんか。
|