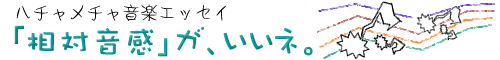二日酔いの朝、目が覚めてすぐに、これが「ド」の音に違いネエとおぼしき声を上げてみる。「アー」と発声することができず「オエー」とウナリ声を上げ、おもむろにピアノの前にたどりつき、ポロンと「ド」の音を出してみる。そんなことを三日ばかりつづけてみた。安心した。僕には「絶対音感」がないことが分かった。
しかしもちろん、ピアノの「ド」の音を聞いた後になら、それと同じ「ド」の音を「オエー」と出せる。つまり、「相対音感」には不自由していないワケだ。
数年前にベストセラーとなった『絶対音感』(最相葉月著/小学館)を読んでみて驚いた。タイトルから考えて当然、音楽に関する書と思ったら、オンガクはオンガクでも「音学」の方で、僕なんぞがお気軽に楽しんでいる「音楽」の方の書ではなかった。あの本は、純粋なサイエンスの書であって、大脳生理学の本でもあり、いわゆる「音楽」について極めてニュートラルな立場を貫いた科学リポートの力作で、そういう意味で十分に説得力のある良書だとは思う。
しかし、大ベストセラーとなった事情を考える時、僕にはおぼろげなギワクが浮かんでくる。書名を知って本屋に走った読者の内の多くが、実はあれが「音楽書」であると信じて疑わず、マットーな音楽ファンを自認する人びとが音楽的教養を高めるための強迫観念にとりつかれて買い求めたのではないか、というギワクだ。まだ音楽的教養などというものに一部の特権意識みたいなものを持っている人たちだっているんじゃないだろうか、というギワクだ。また、『絶対音感』の著者である最相葉月さんが、その表題にした「絶対音感」というコトバを、作品を書き始める一九九六年までは知らなかった、というのにも驚いた。
僕なんぞの世代では、「絶対音感」は学校の音楽授業のキーワードの一つでもあって、ある意味で音楽教師のバックボーン「音楽アカデミズム」のコケオドシに、必ず使われていたと記憶するからだ。数人の友人に尋ねてみたが、僕のまわりに音楽好きが多いせいもあるのだろう。みんな知っていた。はて、最相さんの世代と僕ら世代の間で、受けた音楽教育が違っているのだろうか。とてもそうは思えない。
繰り返すが、僕には「絶対音感」はない。それどころか音楽のプロでもないし、専門教育を受けたこともない。ただ、ハーモニカ少年だった頃から始まり、チェロ、アルトホルン、サキソフォーン、フルート、ギター、そして高校時代の声楽、さらにはその後のピアノまで、なんだか音の雑貨商みたいにいろいろと音楽体験してきたことに、自分自身で驚いている。もちろん、たいていの場合、他人も驚く。驚かれた後で、そのどれもがロクデナシの腕前であることを発見され、今度はケーベツされる。
さて、この連載タイトルを「『相対音感』が、いいね。」とした理由を最初に明かしておきたい。
まず第一の理由。『絶対音感』を音楽の本と勘違いして買い求め、ムズカシさのあまり途中で投げ出してしまった読者のために、今度はちょっとクダラないけど楽しい音楽エッセイを読んでもらいたい、ということ。
第二の理由。本書は、音楽は好きだけど学校で習った音楽はまったく好きじゃなかったという、日本全国9千8百76万人の人びとに対して、「なぜ学校音楽は面白くなくて、一般的な音楽にはこんなにも関心があるのか」という答えを、音楽チュードク者のドタバタ体験記を通じて理解してもらうためだ。
例えばカラオケ好きなあなたなら、あなたがカラオケであんなにも上手に歌える秘けつはあなたの「相対音感の良さ」にあることを知ってもらいたいからだ。
そして第三の理由。「絶対音感」をテーマにすることはそのまま西欧のクラシック音楽の理論や体系、そこから派生する音楽アカデミズムへの服従をイメージしがちで、おっとどっこい、実は僕ら一般の音楽ファンに役立つのは「絶対音感」ではなく「相対音感」のはずじゃないか、ということだ。おととい来やがれ、音楽アカデミズムのやろめ! ということだ。
もう十年も前のこと、僕は友人たちと連れ立って東京厚生年金会館ホールにキース・ジャレットを聞きに行った。世界的に有名なジャズピアニストであり、優れたジャズミュージシャンがたいていできるようにオーケストラとの共演も少なくない。
当日、僕の横には素人バンド仲間のピアニスト、紅一点ミユキ嬢が、その向こうにはミユキ嬢の夫君にして我がバンド二代目のベーシストが陣取り、まるでキース教の熱心な信者だけが参会するミサのようにコンサートが始まった。コンサートが始まってすぐに、僕の隣のミユキ嬢が何やら書き物をしていることに気がついた。カサコソカサコソとウルサいのだ。見ると、ミユキ嬢はキースが演奏する曲のテーマ部分を即座に音符にしてメモをとっている。演奏されている曲の調にこだわらなければ僕にだってできないワケじゃないが、なにしろミユキ嬢は「絶対音感」を持っていて、瞬時にコードまで聞き分ける。クラシックは長年ベンキョーしてきたけど、ジャズはもっと知りたいし、メモった曲を自宅で練習したい、というのがミユキ嬢のメモ動機のようだった。
その時の僕の感想。「絶対音感は、非常にメーワクだ」
さらに、「絶対音感」を持つ人は、コンサートという公共の場での人間の「相対関係」に無神経なのかしらんなどとも感じ、コンサート後、恐る恐る文句を言った。なにしろミユキ嬢はプロのピアノ先生で、日頃僕などのようなヘタクソとバンドづきあいしてもらっていたのだから。
それにしても、ヘタの横好きで始めたジャズバンドで、僕の最大の関心事は「相対音感」だった。フリージャズなどの例外を除けば、ジャズの最大の魅力はアドリブにつきる。基本的な和声の流れにのって、元のメロディーからどう逸脱できるか。素人の僕にしてみれば、それはまさに「相対音感」にかかわる問題なのだ。
考えてみればハーモニカ少年だった時代からギターで歌うお兄サン、さらには無手勝流ピアノオジサンになった今日まで、僕の唯一のトリエは「相対音感」なのだろうと思う。
ところで、1996年、最相さんが「絶対音感」という言葉を初めて知った頃から、すでに僕のこの原稿は書き進められていた。その当時のテーマは「絶対音感至上主義なんて、クソの役にも立ちぁしない!」だった。そこでは、楽器の王様ピアノをダメ楽器と糾弾し、五線譜をロクデナシ譜面とやっつけることで、日本の西欧クラシック音楽偏重主義と、その下で行なわれている音楽教育をコテンパンに(?)やっつける予定だった。あの不自由にして態度のデカいピアノという楽器と、そこから生まれたに違いない五線譜の不合理性は、いったい何なんだッ!
もともと僕はコピーライターで、広告が本業だ。音楽のシロートだけど、音楽シロートが音楽に関する原稿を書いちゃイケナイという法律は、ない。だいいち、野球シロートの僕は今、野球大好き青少年&オヤジたちの専門誌に、これもまた英語シロートなのに、野球英語に関する連載コラムが持てちゃってるのだ。ああ、アリガタヤ。 さて、96年から書き始めたこの原稿を一気に書き上げてしまった原因を、最初にタネ明かししておきたい。ひょんなキッカケで、ある企業と出会った。ジャリタレ養成でしこたま儲けながら、音楽教室なんぞも開きつつ、芸能&音楽教育を多角的にやっているスンゴイ名前の会社を知る機会を得た。
さらに、その会社が独自に開発したという奇妙な楽譜と、ピアノであってピアノじゃない、ヘンテコリンな楽器をPRしたい、ついてはちょいと相談にのってくれないか、というものだった。ホイホイと引き受け、ほんじゃどういう媒体で広告宣伝をしましょうか、というハナシになった。
「この種のモノはパンフレットやら何やらじゃ、なかなか世の中に知らしめられないんですよねぇ〜。トホホ」
相手の部長というのが開口一番、コピーライターとしての僕の気勢をそいだ。
「なんか、一般の書籍のようなカタチで出せば、それも第三者が書いたカタチで出せば、そこにある種の信憑性が生まれると思うんですけんどねぇ〜。ケケケ」「ホイホイ、ここはイッパツ、このワタクシメにおまかせあれ。ヤラセだろーが、ウソ八百だろーが、なにしろこのところ本を書きたくってウズウズしてるとこズラ」
かくして、本来はそのワケの分からん楽譜理論と奇妙な楽器を宣伝する目的で、あくまで結論に「素晴らしく革新的な楽譜理論と楽器に出会ったゾ〜〜ッッッ!」と紹介するために、この原稿を出版を意図して再整理し始めたのだった。
出版時期は一転二転三転し、いつの間にか友人たちからは「相対音感が、なかなか出ないネ」とからかわれる立場となった。腹が立つから、間に入ったフリーの編集者Yさんにも「相対音感がなかなか出ないネでお馴染みのYさん」と言うのが、僕の常套句になった。99年3月、ついに発行の手順となった。連載コラムを書いているベイスボール・マガジン社の「月刊メジャー・リーグ」読書欄にも、近日発行だから読者プレゼントしまっせ! と堂々と告知した。
ハナシはそれきり立ち消えとなった。ワケが分からん仕打ちの前に、実は僕の原稿を「買い取り」の形式にしたいという申し出があった。「やなこったい!」という僕の対応がマズかったのかも知れないが、別に後悔はない。
〜 次号につづく 〜 |