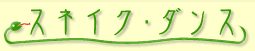
7.
週末の午後、ダツはナガラミ荘を出ると実家まで歩き、母親の自転車を借りた。Z町に 出掛けようというのだ。
事情があった。ダツのズボンの右ポケットの中で、ここ数日の間、飛竜が日ごとに弱っ てきていたのだ。突然の臨終という事態がやって来る可能性が、ダツにも飲み込めた。飛
竜を美しいと褒め、可愛がった数少ない人間としてサヨリにもこの事実を知らせておくべ きだ、とダツは考えた。
線路向こうの町に入り、Q町までやって来ると、歩道のあちこちにカニエ夫人のシャボ ン玉が残骸と混じって散乱していた。カニエ家での事件の後、それを報道する新聞はなか
ったし、結局、単なる事故として処理されたのに違いなかった。その結果、カニエ夫人は 今日外出しているわけなのだから。 きっと、カニエ夫人が日曜の散歩に出掛けたのだろう。散歩しながら誰かと話せば、い
くらでもバブルは発生するのだし、歩いた道順にその残骸が残るのも当然だ。 ダツはカニエ夫人の散歩を確信し、自転車を歩道に乗り上げ、硬化したバブルをタイヤ
で砕くように進んで行った。
青いZ町に入り、三軒目のサワラ家のインターフォンのボタンを押した。このあいだ少 しだけ話したサヨリの母親の声が応対した。
「P市役所市民生活課調査係のダツですが、今日は調査係としてではなく、個人的にサヨ リさんに会いに来ました。実は・・・・」
ダツがインターフォンに向かって訪問の目的を告げている途中に、サワラ家の青い玄関 ドアが開き、まるでモヘヤの毛糸のピンク色に染まった頬の健康そうなサヨリの嬉しそう
な笑顔が現れた。
「ダツさん、会いに来てくれたのですね」
心なしかサヨリの頬はふっくらとし、薄かったはずの胸もふくよかにその隆起を誇張し ている。
「銀行に勤め始めたそうですね。もう、休日にしかお目に掛れないようなので、今日、や って来ました。これをお返ししなくてはならなかったのです」
ダツはズボンの左ポケットから青いブラジャーをつまみ出すと、サヨリに差し出した。 サヨリのモヘヤのピンク色の頬が、さらに赤みを増し、ダツの手から慌てて奪い取ると、
着ているブルーのセーターの腹の中に隠してしまった。エメラルド症候群の時のサヨリが しなかったうろたえぶりだった。
「上がってください」というサヨリの申し出の通り、ダツはサワラ家に上がり、今回は居 間ではなくサヨリの部屋に連れて行かれた。小さな青い部屋には、サヨリが子供の頃から
使っていただろう勉強机とシングルベッドがあり、机の上には簿記の本や電卓、ゴンズイ 銀行の接客マニュアルなどがきれいに整頓して並べられていた。
「居間には父も母もおりますし、こちらの方がダツさんも気が楽でしょう?今、紅茶を入 れてきますわ」
サヨリは楽しげな表情で部屋を出て行き、案内されて入ってから自分にふさわしい座席 の位置を探していたダツは、立ったままポツンと取り残されてしまった。勉強机の前の、
小さな少女だけが座るのにふさわしい椅子と、あとはクッションの良さそうなベッドだけ だ。ダツはベッドの端に腰を下ろすと、ズボンの上からそっと右ポケットに触ってみた。
ここ数日で急激に弱ってしまった飛竜が、以前よりもやや小さくなってそこにいた。
やがて盆の上に二つのティーカップを持って帰って来たサヨリがベッドに腰掛けている ダツに嬉しそうな微笑を送りながら、隣に腰を下ろした。
「会いたかったのです」
サヨリが、ダツを真正面に見据えて言った。
「ダツさんのことを考えると、夜も眠れませんでした。エメラルド症候群を本気になって 直そうと考えたのは、ダツさんにお会いした瞬間からだったかも知れません。そしてワタ
シは直ったのです。ワタシはもう、人を好きになることができるようになったのです」
「サヨリさん、今日ぼくが会いに来たのは、この飛竜のことなんです。コイツが急に弱っ てしまって・・・・」 サヨリに一瞬落胆の表情が走り、もう一度気をとり直してダツを見つめる。
ダツがポケットに手を入れて飛竜を取り出そうとすると、一瞬サヨリの表情がこわばっ たようにも見えた。
「ほら、これ」
ダツが飛竜をベッドの上に出すと、サヨリは十センチほど後ずさりした。青いベッドカ バーの、サヨリが退いた分だけやや広くなった空虚な場所に丸くとぐろを巻いて横たわる
飛竜は、かつてのアクセサリーのような美しい輝きも失せ、萎え干からびた光沢のない膚 とくすんだ眼をして二人を見上げている。
「飛竜は時々ぼくに話していたのです。コイツはぼくのアコガレだったり、記憶だったり ・・・・。そうそう、最初にコイツが言ったのは、コイツはぼくのカサブタだ、と。いや、ぼくの停滞する魂だったかな。最近ではコイツはぼくの愛憎だとか懐古趣味だとか、ぼくにも訳の分からないことばかり言うのです。もちろん、断言しますが、ぼくはコイツの言
うそれらすべての言葉を、これまで一切気にも留めてこなかったのですが、最近になって コイツは以前にもましてお喋りになり、コイツはぼくのペニスであり、ぼくの恋だとまで
言ったのです。その日から、コイツは弱り始め、まるでサヨリさんのところに連れて行け と言わんばかりだったのです。 コイツが初めてサヨリさんに会った日、つまりぼくも同じことなのですが、サヨリさん
はコイツを見て、『まあ、なんて美しい蛇』と言いましたね。覚えていますか? それがコ イツを喜ばせ、サヨリさんに纏わり付いたじゃありませんか。サヨリさんの言葉はコイツ
を増長させ、ぼくがそれまで見たことのないほど、コイツは有頂天になったのです。コイ ツはサヨリさんのからだをまさぐり、サヨリさんのからだの隅々に侵入し、ついにはサヨ
リさんが素っ裸にならなくっちゃいけないほど、サヨリさんの服の中にまで入り込みまし たね。ぼくには、その時のコイツの気持ちが分かったのです。ぼく以前に、コイツがサヨ
リさんに恋をしてしまったのです。コイツは、あなたの美しさに誘惑されて、あなたのエ メラルド症候群を確かめたいと思ったのです。ひょっとすると、コイツは自分の死に場所
を探していたのかも知れません。もう、長いですからね、ぼくとの共生も。コイツは、サ ヨリさんのあのエメラルド症候群によるおしっこの塊の中に、自分の最期の場所を求めたのかも知れません。
なぜなら、あの時のサヨリさんは、エメラルド症候群の只中にいて、それだからこそ美 しかった。吸い寄せられるほどの魅力を、サヨリさんはお持ちだった。そして、サヨリさ
んの作り出すあのエメラルドの塊は、もっと美しかった。 ぼくは今日、飛竜の死に場所について、サヨリさんとお話をするためにやって来たので す。それは、あなただけがエメラルド症候群の持ち主であり、あなただけがあのエメラル
ドの塊を作り出すことのできる女性だからなのです。 ぼくは確信しています。飛竜の最期の望みは、あのエメラルドのおしっこに浸され ながら、やがて美しい塊となったあの中に、自分の死骸を閉じ込めて欲しいという気持ち
であることを。それは、なんて美しい死でしょう。そして、なんと飛竜の死に場所にふさ わしい姿でしょう」
ダツは自分でも信じられないほど一気に、澱みなくサヨリに話し掛けた。少しの真実も、少しの 現実感もないまま、まるでそう話すことが最初から決められていたように。
ベッドの上の飛竜は、そうしてダツが話している間にも、どんどん生気をなくしていく かのようだった。
「もう、ワタシには、あのエメラルドの塊になるおしっこはできないのです。それは、ワ タシの罪なのでしょうか?」
サヨリが、切ない吐息と共に言った。
「いいえ、サヨリさん、どうか気にしないでください。でも、たった一つだけお願いがあ るのです。サヨリさんのおしっこは、もう二度とあのエメラルドの塊になりはしないので
すか、その可能性はないのですか。なにしろ、ぼくはエメラルド症候群だった当時のサヨ リさんのおしっこが固まる事実さえ、実際には見たこともなく、確かめることさえできな
かったのですから」
「分かりません。今、飲んでいる薬を止めたら、ワタシは再びエメラルド症候群に舞い戻 ってしまうのかも知れません」
「それなら、たった一度だけ、もう一回だけ、エメラルド症候群のサヨリさんのおしっこ を見せてくださいませんか。ぼくは、それが空気に触れる瞬間に凝固してしまう様子をこの目で確
かめたいし、もしそれが可能なら、飛竜を美しいエメラルドの棺の中に閉じ込めてやりた いのです。ほんの一度だけ、ブロック一個分だけでいいのです」
「分かりました。三日後のこの時間に、もう一度来てください。その日はワタシは銀行を 休みますし、父も母もいないはずですから。ただし、本当にワタシのおしっこが以前のよ
うに塊になってくれるかどうかは分かりません。それから、ワタシにエメラルドのおしっ こをもう一度させようという理由が、飛竜の棺作りだけだとしても、ダツさん自身のワタ
シに対するお気持ちを、その時には教えてください。ワタシはこんなにも愛しているので すから」
サワラ家を出たダツの気分は、死に行く飛竜の存在を右ポケットに感じながらも、幸福 感に満ち溢れていた。ついにエメラルド症候群の正体を目の当たりにできるばかりか、飛
竜の納まる美しい棺桶さえも手に入るかも知れないのだ。三日経ってなお、仮に飛竜が生 きていたとしても、その時は生きて飛竜を葬ることになるだろう。しかし、そのことは飛
竜の不幸とはならないはずだし、美しい死を選択することは、飛竜自身の喜びでもあるは ずだ。ダツは、そう確信している。
Q町まで戻ってくると、歩道に正装した人だかりができていて、その中心にカニエ夫人 の黄緑色の髪が揺れていた。カニエ夫人は「ハレルーヤ、ハレルーヤ」と、何かクリスマ
スの歌を大声で歌い、黄金色の口紅に縁どられた唇からパラパラと例のシャボンを出して いる。彼女の腰の位置ほどしか背丈のない奇怪な男たちが黒のタキシードやモーニング姿
でそれに群がり、手掴みにしようと殺到している。ところが、カニエ夫人が決して一か所 に止まらず、まるでバレエダンサーのようにくるくると回転しながら、踊るように歩道を
移動していくので、男たちはその動きについていくことさえできない。薄紫色のヴェール 状の肩掛けが、カニエ夫人の優雅な回転と共に舞い上がり、虹色のシャボンに風を送る装
置のようにも見えた。
「カニエ夫人の幸福なクリスマス・・・・」
ダツは、懐かしいリポートNO1の備考欄に、そのフレーズを書き足しておこうと思った。
このサイトに掲載される著作物(文書、資料など)に係る著作権は特別の断り書きが無い限り、ミキオ・Eが保有します。
mikio-e can be reached at QWQ05617@nifty.ne.jp
Copyright(C)2001 mikio-e All Rights Reserve.