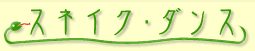
To
Rie, for her birthday.
1.
P市役所市民生活課調査係というのが、ダツの新しい職業だ。
それは、決してこれまでのダツの生き方にふさわしくない肩書きで、つい最近、少しばかり卑怯な手段によって手に入れたものだ。
P市はダツの故郷で、それまで数年間の大学生時代とほんのつかの間のサラリーマン生活、さらに無職だった半年ばかりを都会で過ごしたダツにとって、言ってみればUターンということになる。
都会はダツに迷路のように混沌とした空間で生きることの興奮を教えてくれたが、歩いても歩いても不揃いでいかがわしい商業施設とデコボコの舗装道路、役に立たない信号機などに歩行を遮られるばかりで、目的地にさえ無事にたどり着いたことがない。ダツは迷いを繰り返し、その迷いの中で、果たして自分が目的地を持っていたのかさえ見失ってしまった。しかし、目的地とはいったい何なんだろう。
確かに、ダツは歩いていた。毎日毎日、都会を歩くために生きていた。大学で経済学を勉強すると言ってもダツにとってその目的は、小さく古びた木造のアパートから大学という場所へ移動するために歩くことだけに集約されていた。他の学生たちなら地下鉄や電車やバスを利用して移動するはずの距離も、歩くことだけが目的のダツにとって何ら苦痛を伴うものではなかった。
「オレは、自力で移動する魂だ」
ダツが心の中で繰り返す、それが独り言だった。
ダツは、移動することを目的とする魂だった。
移動を繰り返していなければ、人間は死ぬ。
生命維持の唯一の方法として、カツオが海中を疾走し続けるのと同じように、ダツは歩行し続ける。
それは、ひょっとするとダツの強迫観念のようなものかも知れない。
ある夜、ダツは、小さな蛇を手に入れた。
いつも通りに、大学からアパートに帰る道すがら、歩く行為に没頭していたダツが地図上の自分の位置を見失い、どこか繁華街の路地裏に迷い込んだ時のことだった。
居酒屋のハデな電飾看板の蔭に何かうっすらと光るものがあった。光りは、どこかの光源を反射して起こるものと言うより、それ自体が発光するもののようだった。
ダツはその発光体に近づき、拾い上げようと右手を伸ばした。ヒスイ色に青みがかった地膚と、ラグビーのジャージのような横縞の太い黒の模様が、一見ビーズの頸飾りか何かのアクセサリーに思われた。ダツには、それ以外のイメージはなかった。その瞬間、発光体はダツの右腕に飛びついてきた。ダツは驚き、小さく叫び声さえ上げたが、腕に張り付いた小蛇の腹の感触は心地よく、すぐに陶然とさえした。マチ針のような深紅の眼と、黄金色に伸びる舌を持った、ほんの二十センチほどの小蛇だった。
「飛竜」と名乗るその小蛇は、腹でダツの腕の皮膚を愛撫しながら言った。
「オレは、キミの心に潜む澱みだ」
心外だった。
誰からも、ただの一人からさえも、ダツは心の停滞を指摘されたことはなかった。澱みとは流れのないことであり、何物かに拘泥する魂の停滞に他ならない、と思えた。
ヒスイ色に光るその小蛇を一瞬のうちに捻り殺してやろうと思わないでもなかったが、次の瞬間に、再び小蛇が言った。
「オレは、移動するキミの魂だ」
それからダツと飛竜の関係は一心同体のようになった。
その夜、飛竜はダツのアパートで、こうも告げた。
「オレは、キミのカサブタだ」
昔から、ダツはカサブタに触るのが好きだ。できてしまった傷はその初めに痛みを伴うものだとしても、やがて生まれる異質の膚の触感はコロコロと気持ちよく、ダツはそれを決して剥がそうとなどしたことがなかった。
その夜以来、ダツのズボンの右側のポケットには、ちょうどペニスと寄り添うように飛竜が棲息し、すでにもう四年が経っている。
夜、ダツが寝床に入るためにパジャマに着替えても、飛竜は昼間の生温かいダツの体温や体臭の残ったポケットの中から這い出して来ようとはしない。
あの夜すぐに、飛竜はダツのズボンのポケットに安住のスペースを見つけ、ダツも自分のはいているズボンの右ポケットを飛竜のために空けているのだった。
飛竜との心地よい関係のためにダツが唯一気を使っているのは、ジーンズでなく、比較的底の深いポケットのあるゆったりとしたズボンをはくようになったことぐらいだ。
ダツは大学在学中に小説書きをめざそうとしたが、作家となるための作品にイメージがあるのではなく、作家となった自分のイメージしか持ち合わせがなかったのと、生来の怠惰な性格のために短編小説ひとつ書き上げることなくそれに挫折し、大学も中退してしまった。やがて、小さな広告プロダクションに入って二年ほどコピーライターをやった挙げ句、代理店のディレクターと喧嘩したのがきっかけで退社してしまった。
飛竜は言った。
「オレは、キミの解決できない時間だ」
ふらふらと何をするでもなく生活するダツを見かねた田舎の母親が、父筋のP市助役の伯父に泣きこんで手に入れたのが、市民生活課調査係という職だった。
いわば情実採用の典型なのだが、ごり押しをしたその分、ゆくゆくの出世は諦めるよう伯父には因果を含められていた。もちろん、大学は中退で学歴とはならないし、P市にとっても異例の中途採用職員で、通常のポストが用意されるはずもなかった。
そもそも、「で、お前。何がやりたい?いや、何ができる?」と尋ねたのは助役の方からだった。
伯父さんだったら何とかしてくれるからと母親に諭され、故郷のP市に帰ったある日曜日の午後、二人連れ立って訪れた採用者の家で、P市助役つまり伯父から尋ねられたのだった。
もちろん、その時もダツのスーツの右ポケットには飛竜が潜んでいた。
伯父は、この話が降って湧いた最初から、終始不機嫌だった。なぜなら、これは明らかに母子による脅迫行為とも言うべきもので、伯父の方には門前払いが許されない事情があったからだった。その切り札はダツの母親が握っていて、五年ほど前に亡くなった伯父の弟でありダツの父親が、伯父を助役に登用してくれた市長の選挙資金作りに絶大な貢献をしたのであり、父親抜きでは現在の市長も、また助役の地位もあり得なかったという恩を売っていたのだった。
法に触れる部分も含め、互いに弱みを持っているのに、どちらが失うものが少ないかという比較で、ダツと母親が圧倒的優位を占めたのである。
「何がやりたいって、伯父さん、何でもやらせてもらえるのですか」
「いや、だから、東京での仕事は何だったんだ?」
「コピーライター、です」
分かっているのかいないのか、伯父は何度も意味なく頷きながら「どういう仕事だったんだ?」と尋ねる。
ダツが無気力に、大雑把な仕事の中身を説明すると、さらに頷きの回数を増やし、「ほう、そりゃすごい」「大したもんだ」と繰り返した。
「結局、世の中の動きを知ってなきゃできん仕事だな、それは。どうやって、そういうことを勉強するんだ、コピーライターってものは」
「雑誌を読んだり、はやりのテレビを見たり、あとは街になるべく出掛けるようにするとか。流行の観察というとカッコはいいんですが・・・・」
ダツの最後の言葉が、伯父のヒントになった。
P市を隈なく歩け、歩いて何でもいいから見つけろ。市民の暮らしの変化や、P市ならではの個性のようなものを見つけたらリポートしろ。机は、多少スペースに余裕のある市民生活課に置く。調査係というのがいいだろう。リポートはある程度の分量が集まったところで直接自分に持って来い。以上が、その日の内に決められた。
伯父の指示を聞きながら、ダツは案外面白いかも知れない、と考えていた。
P市役所市民生活課調査係と聞いて、ダツは最初、どこかの家の軒先にいっぱいに翻る洗濯物をイメージした。それから、ナンバープレートを外され、雨曝しで錆だらけになった不法投棄のクルマのイメージが浮かんだ。例えば、そんなクルマを見つけたとして、公僕としては何をすべきなのだろうかと考えたが、伯父、いや助役の指示はあくまでリポートのみということだから、面倒な責任は負わなくていいはずだ。
一週間と一日後の月曜日から市役所に出た。
新築してまだ数年という真新しい二階建て庁舎は、ダツの目に貝をイメージしてデザインされたもののように映った。盆地にあるP市の中心部の小高い丘の中腹にべたっと張り付くホタテ貝のようだ。ダツの家からは丘を反対側の北の斜面から越えて、なだらかな坂を下りかけたところにそのホタテ貝はある。
正面入口を入ると、市民向けの窓口カウンターがずらりと並び、その横を通り抜けたいちばん奥まったところに、職員用のドアがある。ダツは、ドアの前の守衛に市民生活課の場所を尋ねた。指示された場所にいってみると、間仕切りのない四つの机の塊の中央天井から「市民生活課」のボードが垂れ下がっている。
すでに定員いっぱい、顔のない四人の職員がそこには座っていて、新聞を読んだり、お茶を飲んだりしている。ダツが、そのうちの一人に名前を告げると、黙って指し示された方角に、同じ事務用ではあるが肩袖の引き出し部分の付いていない、その分小ぶりな机がコピー機の脇にピタリとサイズを合わせて寄生していた。
机の前に座って時間が過ぎるのを待ったが、だいぶ前に確認した壁の時計の針は故障しているように、ものの五分と経っていない位置にしか移動していない。
立ち上がって階段室に出た。見取り図で確かめ、二階に上がって助役室に向かった。
「来ました」
ダツが伯父に言った。
「うん。これが市職員のバッジ。この採用書類に必要事項を記入して、生活課の誰かに渡すといい。先輩のフナ○○君あたりが手続きをやってくれる。名刺もすでにできているだろう。それから分かっているだろうが、お前の父親のことや俺との関係、甥であることは他人に話さないようにな。コネで、というのがバレるのはやっぱり拙い」
人の名前を覚えるのがどうも苦手だ。伯父に言われた職場の先輩の名前も聞き逃してしまった。確か、フナ○○君とか言ったはずだ。フナモト君、フナヤマ君、フナムラ君、どれも違う感じがした。フナムシ君かも知れない。
助役室から帰り、今日から同僚となった一人に書きあげた書類を渡してしまうと、いよいよヒマになった。四人の顔のない同僚は、ダツにはまるで無関心で、それはちょうど市役所を訪れた市民が窓口でまったく無視されているかのような扱いを受けるのと同じだった。むしろダツは、そのお蔭で市役所勤務が始まったのだ、という実感を得た。
誰がフナ○○君なのか、名札を目当てに捜したが、前に回って覗き込むというのも失礼で、この四人の中にフナムシ君がいるのだな、とボンヤリ考えた。
机の引き出しを開けると、青く透明なプラスティックケースがひとつポツンと置かれていた。名刺だった。P市役所市民生活課調査係に任命された男の名前があった。何枚かを抜き出して、背広のポケットに入れた。
「出掛けてきます」
四人の同僚のうちの一人、誰か分からないフナムシ君に向かって言うと、ダツは席を立って市庁舎の外に出た。九時三十五分だった。
天気のいい、風の穏やかな秋の日だった。ダツは、目ざとくP市市役所のペイントが施された黒い自転車を見つけると、管理人にバッジを見せながら了承をもらい、サドルに跨がって漕ぎ出した。ポケットの中で、飛竜が少しだけ位置を変えるように動くのが分かった。小さく、飛竜が囁いた。
「オレは、キミの非効率な内燃機関だ」
ペダルをひと漕ぎすると、ホタテ貝の前のなだらかな道はそのまま自動運搬装置になってくれた。ボサッと前に垂らしているダツの前髪が、風を受けてオールバックになるのが分かった。市役所職員らしい風貌であるな、とダツは思った。このまま真っ直ぐ南に向かうと、鉄道のP駅にぶち当たる。四〇〇メートルもあるだろうか。勢いのついたダツの自転車は、ブレーキを掛けなければ駅までも到達しそうだ。
クーイン、クーイン。
油切れしている自転車の車軸が、情けない音を立てた。ポケットから飛竜がマチ針の頭のような深紅の二つの目を出していた。
「オレは、キミの動かなくなった唇だ」
クーイン、クーイン。
ダツは、最初のひと漕ぎ以来、まだペダルを漕いでいない。自転車は深く小さく澱んだ川に懸かった橋を勢いよく通り抜け、町の商店街に入った。予想外に、自転車は急に勢いを弱め、駅までの行程の半分も行かない間に停止しそうな状態になる。ダツは上体を前後に揺すり、自動運搬装置による到達距離を世界記録まで伸ばそうとした。それは、世界記録への挑戦なのだった。
期待に反してすぐに停止してしまった自転車を横づけにしたのは、文房具屋兼タバコ屋兼日用雑貨品屋の店の前だった。
「市役所の者ですけど」
A4横罫のリポート用紙を手にしてレジで支払いをしようとした時、ダツは理由もなくそう言った。
「はあ」
文房具屋兼タバコ屋兼日用雑貨品屋の中年女性は、コイのようにパクパクと口を開いて返事をした。
「領収書が必要ですかね」
「いえ、結構です」
ダツは言った。それならなぜ、市役所の者だと言ったのだろうと、文房具屋兼タバコ屋兼日用雑貨品屋の中年女性もダツも、その時思った。
文房具屋兼タバコ屋兼日用雑貨品屋を出ると、ダツは気がついた。買い物カゴのない市役所の自転車で、片手のふさがった状態であの帆立貝までのスロープを戻るのは大変だ。ダツは自転車を手で曳き、歩いて一ブロックほどさらに南に行った。
コーヒー豆メーカーの看板を見つけ、喫茶店らしき店に入った。「マーメイド」というありふれた名前の店には、まだ誰も客らしい人影はなかった。コーヒーを注文したついでに、店のボールペンを借りた。紙袋の中からリポート用紙を取り出すと、表紙を開けて、ダツは最初の一行を書き始めた。
《P市役所市民生活課調査係からのリポート》
一行目をやや大きめな文字でタイトルらしく書き終えると、ダツははたと考えた。今後この仕事を続けていくためには、リポートの基本的なスタイルあるいはフォーマットのようなものが必要だ。
まず、日付には調査時間までも必要だろう。調査場所、調査物、調査物の所有者、調査の動機、調査結果によって判明したこと、備考欄というのもこういうリポートには必要になるかも知れない。
そこまで考えて、やや冷めてしまったコーヒーを口に運ぶと、ダツの気持ちも同じように冷めてしまった。
市民の暮らしの変化が分かるものの発見、という職務内容に関して、ダツはおぼろげに放置物や投棄物、廃棄物の発見というテーマをこの一週間でイメージしていた。しかし、それらを発見できるイメージというのがまったくわいてこないのだった。
もし、P市で飛竜を見つけたのだったら、それが市民生活課調査係としての最初の功績になったのかも知れない。
調査場所・・・・残念ながらP市ではないもと住んでいた都会の路地裏。
調査物・・・・体長15cmの蛇。
調査物の所有者・・・・不明。
調査の動機・・・・一見女性のアクセサリーのように見え、高額な物の拾得と考えた。
調査結果によって判明したこと・・・・当初アクセサリーと思われた拾得物は生きた蛇であった。
備考欄・・・・拾得後、ただちに投棄できず、飛竜と判明して以後飼育中。
ウェートレスが空になったダツのコップに水を追加しようとテーブルに来た時、ポケットから少しだけ頭を出していた飛竜を見つけて飛びのいた。同時に、テーブルの上のコップが倒れ、少しだけ残っていた水がダツの膝にかかった。
「あ、いいんですよ」とダツは言ったが、ウェートレスは怯えて後ずさりしながら「何がいいんですよ、ですか」と声をあらげた。
「マーメイド」を出たダツは再び自転車に跨がり、P駅の線路向こうまで足を伸ばしてみることにした。都会に出るまでの十八年間をP市で過ごしたダツだったが、どういうわけか線路向こうまで出掛けた経験がなく、そこからは見知らぬ土地だった。それでも、そこからずっと先までP市は続くのだし、P市役所市民生活課調査係として、ダツは行くべきだと思った。
小綺麗な庭のある一戸建ての町並みが続いている。白壁の光沢はまるでプラスティックのような質感で、それぞれの家が一戸という単位ではなく、一個と言う方がふさわしいような工業製品の規格品の佇いを見せている。道路は車道と歩道に分かれ、レンガ色の歩道のところどころに小さく植えたばかりと分かる潅木が立っている。ダツは、黒く塗り替えられたばかりのアスファルトの車道を選び、まだ少しばかり鼻をつく臭いが残っている道路にゆっくりと自転車を走らせる。自転車のタイヤとアスファルト道路は互いに粘り着く感じで、ペダルが重い。
静かな住宅街を走っている間中、ダツの横を通り抜ける車はないし、住宅から人の出入りする気配さえもない。コンビニエンスストアや商店なども見掛けないし、どこにも生活感らしきものがない。ちょうど家の主人や子供たちが出掛けた後の虚ろな時間なのかも知
れなかった。
ダツはペダルを漕ぎながら、「セイカツチョーサ、セイカツチョーサ」と頭の中で繰り返していた。
やがて、一軒の住宅の前の歩道に山積みに出されたゴミ袋を見つけた。五十センチ四方もあるポリ袋がゆうに二十個ほどもある。P市ではまだこれからがゴミの回収時間で、どの家の前にも一つか二つのゴミ袋は出されているのだが、これほどうずたかくゴミの山があるのは初めてだ。
ダツは自転車を降り、ゴミの山の前に進んだ。注意深くポリ袋を見ると、ブルーの半透明の袋の中身が、ほとんどビー玉のような球体ばかりだということに気づいた。それぞれのポリ袋にはP市のゴミ回収時の決まりとしてラベルが貼ってあり、ダツは屈み込んで読んでみた。
P市ゴミ回収シール。
廃出者住所氏名・・・・Q町3丁目45の2番、カニエ。
廃出事由・・・・一般ゴミ。
特例事由・・・・急性バブル硬化症による。
奇妙なゴミ回収シールの記述を見て、ダツはそれをリポートに書き留めておこうと決めた。ポリ袋の一つをつまみ上げると、それは思った以上に軽かった。小さなビー玉大の球体からピンポン球ほどのもの、中には野球のボール大のものまで混ざっていて、袋の外から指先で弾いてみると、コツコツとプラスティックのように乾いた硬質な音がする。
「あのう、何をなさっているのですか」
ダツの背後にいつの間にか一人の女が立っていて、女は片手を口に当てながら、たった今話した言葉が何物かに変質してしまうのを防ぐように、その掌を開閉させている。
「あ、市役所市民生活課の調査係の者です」
胸のバッジを見せながら、ダツが答えた。女は「ハア」と言いながら再び片手を口元に持って行き、直後に吐息を分解するように掌を握り締める。
「カニエさんの奥さんですか」
ダツは市民生活課調査係としての任務に入った。
女は三十歳ぐらいで、色白の艶やかな膚と黄緑色の髪が印象的で、振り返って見た瞬間から、ダツはその美しさに目を奪われていた。オレンジ色に透けるブラウスの下には、カニエ夫人は何も着けていないのが分かった。シルクのような銀色のスカートは、午前中の緩やかな光を背に受け、夫人のすらりと伸びた足の輪郭さえ浮き彫りにする。
「この、シールに書いてある急性バブル硬化症と、お出しになったゴミとは、いったいどんな関係があるのでしょうか。ちょっとばかり気になったものですから」
「あら、それは市役所の方には連絡済みですのに」
「すみません、新米なものですから」というダツの答えの最中に、夫人はコホンと咳をした。ぷるる、と夫人の大きな乳房が揺れるのが見え、同時に、口に当てていた掌の隙間からふんわりと虹色のシャボン玉がこぼれ出してダツの目の前を浮遊している。
「これ、ですわ」
夫人は口元に押し当てられた手はそのまま、もう片方の手を伸ばすと、シャボン玉を捕まえ、掌を握ってつぶした。プチンという小さな音が聞こえ、かけらになったシャボン玉の残骸が夫人の掌から砂のようにこぼれ落ちる。
「どういうことでしょう」
ダツはわけが分からず、もう一度尋ね直した。
「ア・タ・シ・ガ・コ・ウ・シ・テ・シャ・ベ・ル・ト・・・・」
夫人は口元にあった手をどけ、美しい唇の動きをダツに見せながら話し始める。言葉が数語発せられると、そのたびに透明なシャボン玉が夫人の舌の上から湧き出てくる。
「あっ」とダツは声を上げ、三つ四つ浮遊するシャボン玉のうちの一つを片手でゆるゆると捕まえた。
ダツが捕まえたシャボン玉の触角は、最初ぬるりと柔らかい感じなのに、掌の中で急激に ぬめりを失って固まるようで、さっき夫人がしたのと同様に握り締めてみると、あっけな
く粉々に砕けた。捕まえずに空中浮遊していた残りのシャボン玉は、ゆっくりと地上へと 舞い降り、地面に着くと同時にカラコロと音を立てている。
「これだったのですね」
「そう、急性バブル硬化症・・・・」
夫人の口から再び三つのシャボン玉が現れた。
「このポリ袋は、いったい何日分なのでしょうか」
目の前の二十もあるゴミ袋を指して、ダツは尋ねた。夫人は掌を口に押し当て、黙って指を二本立て、一日に十袋分のシャボン玉が生まれることを暗示した。
「お困りでしょうね」
ダツが言うと、夫人はしばらく考え込む素振りをした。
「別に。でも・・・・」
二つのシャボン玉が現れ、ゆっくりと地面に落下するのを、ダツは見届けた。
「キッスができないわ」
このサイトに掲載される著作物(文書、資料など)に係る著作権は特別の断り書きが無い限り、ミキオ・Eが保有します。
mikio-e can be reached at QWQ05617@nifty.ne.jp
Copyright(C)2001 mikio-e All Rights Reserve.