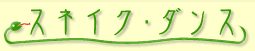
6.
翌日、また翌日と、ダツはP市をくまなく調査し続けるが、これと言って、何も新しい 発見ができない。 ペットとして飼われ毎日の散歩を欠かさない椅子の存在、あるいは電気を食べている老
人の存在、箱詰めにされたチーズの上に薄力粉を敷きつめて生活する中年夫婦の問題も、 飛行機雲に糸を引っかけてタコ上げしている九歳の少年の行ないも、何ら目新しいものには映らなかった。
ダツのリポートNOは相変わらず48で停滞しているし、新しい毛布を調達しに実家に寄っ た時、まるで死んだ魚の眼のようだと母親に様子を心配されたダツ自身の心も停滞し続け
ていた。
P市役所市民生活課調査係という職分を気に入っているダツにとって、移動という行為 を、何かの目的抜きには考えにくくなっていた。何という自分自身の変化だろうと、ダツ
自身が思う。かつて移動することそのものが目的だったダツの行為の動機は、明らかに変 質していたのだ。一週間ほど前、イニシャルKの女が言ったコード105の廃棄物の手掛
かりさえ掴めなかった数日間、ダツは放心し、学生時代以来久しぶりに移動する行為その ものを目的にして移動したことがあった。しかし、それにダツはあっと言う間に飽きてし
まい、目的もないままペダルを漕ぐのはなんだかひどく退屈だと思うようになった。 それに気づくと、ダツが日課にしていたあの世界記録への挑戦さえも、ホタテ貝からの
スロープを下りきった地点でようやく気がつくといった現象も起こった。世界記録への挑 戦は、それ自体が目的ではなかったのだろうか。 喫茶店「マーメイド」で一日の大半の時間をつぶし、市役所に戻って、すぐに家に帰る
という生活が日常になった。
飛竜が随分とお喋りになり、毎夜ダツの寝床で「オレはキミのモヤモヤとした懐古趣 味だ」とか、「オレはキミの素姓だ」、「オレはキミのリンパ腺だ」、「オレはキミの後悔を是認するエゴだ」などと言っても、ダツの心には何も響かなかった。
町中にサンタクロースが現れる十二月も押し詰まってきた頃、改めてダツはまだ一度も 助役にリポートを提出していないことと、クリスマスが近づき、もう三カ月近くも市民生
活課調査係の仕事を続けているのだということに感慨を持った。 リポートNOは相変わらず48までで、NO49に該当する調査対象物は決定されていない。な
ぜなら、あの日以来ずっと、ダツは市役所からすぐにナガラミ荘に戻り、イニシャルKの ドアを開けるのだが、売店の女はずっと不在で、さらにその足で出向くP駅でも、未だに
駅員と接触さえできないのだった。
本当に久し振りに、ダツはホタテ貝のスロープの出発点から世界記録に挑戦するための最初の、大きなペダルの最初にしてたった一回だけのひと漕ぎを力一杯踏み込んでみた。
すぐに耳が千切れるほどの冷たさを感じ、こういう透明な冷気の中でなら、世界記録の 更新も夢ではないな、と直感した。ホタテ貝から下りてすぐの小さな橋を越えるまでに、
すでにダツは三人のサンタクロースたちを追い抜いている。その内の二人は徒歩の、もう 一人は乳母車を押していたサンタクロースで、蛇行することでより加速を付けようという
ダツの目論見のために、それぞれの真横を掠めるような格好になって、三人とも首をすく めるのが分かった。内心、ダツは悪いなと思いながらも、世界記録の更新のためのスネイ
ク・ダンスは、それ自体正当な行為なのだからやむを得ないのだと思った。
文房具屋兼タバコ屋兼日用雑貨品屋を越えてもなお、その日のダツの自転車にはまだ余 力がある。今日までの世界記録の目印になっている葬儀屋の横書きの看板「祭典」の「典」
の字まで、多分到達できそうだ。 ダツはからだをリラックスさせ、できるだけ惰性に逆らわないよう、自転車の付属品の 一部になったようにベタリと張り付くような体勢をとった。葬儀屋の店先が視界に入り、
頭を上げると、スローモションのように「祭典」の文字の向こうに「マダラ」という文字 が見えて来る。ダツの自転車は、ほとんど静止しかかりながらも、ついに葬儀屋の看板の
「マダラ」さえも越え、すべての力を使い果たして葬儀屋と隣の洋品店の境目で息絶えた。 同時に、葬儀屋の名前が「マダラ祭典」だったということを、その時初めて知った。世界
記録の更新だった。
無意味な行為が決して意味のない成果だけをもたらすのではないことを、ダツは体感し ていた。恋に意味がないのと同様に、世界記録への挑戦だって、少なくとも意味を追って
する行為ではないのだ。ダツには何か大きな達成感がわき上がり、きっと何かの幸運の前 兆なのに違いないという気持ちになった。
そのまま再びペダルを漕ぎ出し、線路向こうの 町に向かった。 カニエ夫人の家の前には、今日も二十個ほどのポリ袋が出されていた。すでに新しい車
道のアスファルトには粘り着くような感じがなくなっていて、埃や空気に馴染んでしまっ たようだ。以前よりもスピードを上げて、ダツはカニエ夫人の町を走り抜けた。
青いZ町の家並みの三軒目にやって来ると、ダツは躊躇なくインターフォンのボタンを 押した。
「P市役所市民生活課調査係です」
「はい」
応対したのは、明らかにサヨリではない別の中年女性の声だった。青い玄関ドアが開か れ、水色のブラウスに紺のカーディガンを羽織った女が現れた。
「サワラさんですね」
「はい、さようでございますが、どういったご用件でしょうか」
サワラサヨリの母親は、丁寧に、しかし怪訝そうに答えた。
「以前、エメラルド症候群によるブロックについて調査させていただいた調査係のダツと 申しますが・・・・」 「まあ、あなたがダツさんね。娘から聞いております。とても親身になって心配していた
だいたと」
「いえ、私はあくまで調査係ですから」
サワラ夫人は、サヨリからダツのことを聞いていたようだ。
「で、今日は?」
「サヨリさんはご在宅ではないでしょうか」
「はい、娘は銀行に勤め始めましたのよ、今月から」
ダツの心に、再びサヨリに対するもっと深い軽蔑の気持ちが浮かび上がった。
「もう、大丈夫なのでしょうか。その、普通の生活ができるのかどうかという意味で、で すが」
「ええ、もうすっかり。ご覧のようにブロックも全部片付けてしまいましたのよ」
こういう場合、何と言えば良かったのだろう。「ご全快おめでとうございます」などと いう言葉は、結局ダツの口から出ては来なかった。サヨリの勤める銀行の名前を母親から
聞き出すと、ダツはまるで失意のどん底を味わったようにふらふらとサワラ家を後にした。 どうしてサヨリは、「ゴンズイ銀行」などというつまらなさそうな場所で勤めを始めて
しまったのだろう。どうして、あの青い家の中で美しい暮しを続けていかなかったのだろ う。彼女は、気に入っていたはずだった。彼女のおしっこから生まれる、あの美しいエメ
ラルドのブロックを。 カニエ夫人だって、「キッスができないわ」という不便を除けば、さして急性バブル硬 化症を嫌ってなんかいないはずだった。あの虹色のシャボンよりももっと、サヨリのエメ
ラルド色のおしっこの塊は美しかったのに、どうしてエメラルド症候群を治療しようなど と考えてしまったのだろう。少なくとも、サヨリの凛とした青い美しさを増すことはあっ
ても、損ねることなど一つもない、あの切ない病を抹殺してしまったのだろうか。
ダツは完全に混乱していた。そして、心の中にあるサヨリへの軽蔑が刻一刻と肥大化 していくことに気がついた。 それは、ある一人の少女の面影を残す若い女がエメラルド症候群という病に侵されてい
た事実と、エメラルド症候群という奇病から立ち直った一人の女が今月から銀行勤めを始 めた事実の重さの比較であった。前者は、エメラルド色のおしっこの塊を生み出す存在とし
て、後者は、何ものも生み出さなくなった普通の銀行の女として存在しているのだった。 軽蔑は、神秘性から通俗性への、あるいは特別性から普遍性への、サヨリ自身の変身が
もたらしたものだった。なによりも、もし二度とサヨリがあの美しいエメラルド色のおし っこの塊を生み出せなくなったのなら、サヨリの選択したエメラルド症候群の治療とは、
美しいサヨリ自身のかつての存在や、エメラルド色に輝くおしっこの塊を抹殺する行為に 過ぎないことになる。 どうして、馬鹿な、つまらない、そんな考えを実行してしまったのだろう。
ダツはサヨ リを失った気さえして、込み上げてくる涙を振り払うように、ペダルに掛ける力を強めて いった。 途中、カニエ夫人の家の近くに救急車やらパトカーなどの車両が数台止まっていること
も無視して、一気に駆け抜けた。
翌朝の地方新聞の事件欄に、Q町3丁目45の2番カニエマスノスケさん方の居間で、マ スノスケさんの弟コマイさん(三十二歳)が呼吸不全のため急死した、という記事を見つ
けた。そして、当時在宅していたカニエ家の主婦(三十歳)に事情を聞いたところ、日頃 の健康に何ら問題のなかったコマイさんの死亡はあまりに突然で、現在P市警察署で死因
について詳しく調査をしている模様、という内容だった。
ナガラミ荘の部屋でその記事を見つけたダツは、市役所に出てからも、いつものように 調査のためにすぐに出掛けることをせず、また別の新聞のカニエ家の事件に関する記事を
読んだ。
ダツには当然、事件の真相が分かっていた。カニエ夫人が夫の弟とキッスをした結果が 引き起こした、それは事故のはずだった。死因が特定できないということは、きっと夫の
弟の喉か何かで例のシャボンが凝固し、それが原因で男は死亡。その後、あのシャボン は脆くも砕けたのだろう。 カニエ夫人は、キッスがしたかったのだ。そして、彼女はキッスをしたのだ。その結果
として、一人の男が死んだのだ。 あるいは、カニエ夫人がキッスすることによって夫の弟を意図的に死に至らしめたとし ても、そのことにダツは関心がなかった。
なんだか当然すぎる、当たり前すぎる結末という気がした。ただ、もし自分がカニエ夫 人とキッスをしたら、本当に呼吸不全で死んでしまうだろうか、そのことを考えた。
一日中、ダツは調査と称して外出するいつもの手口を使わなかった。顔のない四人の同 僚たちは、だからと言って、ダツを気にする風でもなかったので、懐かしいアルバムを括
るように、ダツはリポートNOの1から順に読み返して時間を過ごした。
市役所をひけてナガラミ荘に帰ると、調査係として市内を駆けずり回っていたこれまで の日々と同じ疲労を感じて、ダツは寝床に横たわった。 飛竜がすぐに、ポケットから頭を出した。
「オレは言いたくはなかった。だが、キミの予期していた通り、オレはキミのペニスだ。 そして、キミのペニスとは、キミの奇跡の恋だ」
ダツは、言ってみてもしょせん何の意味もないことは分かっていたが、真顔で飛竜に告 げた。
「馬鹿を言え。カニエ夫人はともかく、サヨリさんに関しては、オレは軽蔑さえしている んだ。オレの性器とも、オレの恋とも、今起こっている事柄は何の関係もありはしないじ
ゃないか」
飛竜は、何も答えなかった。
このサイトに掲載される著作物(文書、資料など)に係る著作権は特別の断り書きが無い限り、ミキオ・Eが保有します。
mikio-e can be reached at QWQ05617@nifty.ne.jp
Copyright(C)2001 mikio-e All Rights Reserve.