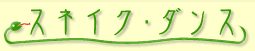
4.
翌朝、ダツは何かの物音で目覚めた。しかし、まだ時間は早い。一階の自動車修理場の騒音は、もちろん、こんな早朝からは聞こえてくるはずもない。
ダツはのろのろと起き上がり、枕元の時計で時刻を確かめる。 五時三十八分。仄明るい 窓の外の気配を感じながら、玄関に近づいて行くと、はっきりと物音が聞きとれた。
シャラシャラシャラと、何かを引きずるような、小さく耳障りな音。 玄関のドアを開けると、ちょうど隣のドアの閉まる音が聞こえた。ナガラミ荘の四階に
ダツ以外の住人はいないはずだった。ダツは隣の玄関の前まで進み、恐る恐るドアを開け た。
ドアを開けると目の前のキッチンで、中年の女がやつれきった表情の後ろ姿で直立して いる。いや、やつれきった後ろ姿の表情とはいったい何なんだ。シャラシャラと光るシル
クの光沢の黒い喪服のようなワンピースのはだけた肩が鋭利に尖っている。女はまるでセ ーターを脱ぐように、黒いワンピースの裾をつかんで持ち上げ、頭を抜こうとしていた。
ダツは小さく「あっ」と声を上げたが、ダツの出現に気がついたはずの女の表情は少し も変わらない。
「物音が聞こえたものですから」
ダツが女に詫びるように言い訳した。
「お隣にはどなたも住んでいないものとばかり思っていました」
再びダツは言った。 薄っぺらな胸の前に靴べらのような乳房の隆起を垂れ下げて、女はダツに近づいた。 「大変よね。コード105の廃棄物を捨てに行くのに、アタシは電車と地下鉄とバスを乗
り継いで出掛けなくちゃならなかったのよ」
「コード105の廃棄物?」
女の顔がダツに吐息がかかるほど近づいた。
「アタシがここの住人であることは、あなたがお隣の住人であることと同じぐらいはっき りしないことだわね。アタシがここの住人であることは、あなたがお隣の住人であることと
同じぐらいにはっきりしているけれど」
女の言葉はまるで訳が分からない。ダツは働かない自分の脳を恨めしく思いながら、そ れでも目の前の女の表情にどこか懐かしさを感じ始める。
「どこかでお会いしましたか?」
ダツは女に尋ねた。
「さあ、どうかしら。アタシはここでずっと暮していたし、あなたがアタシに会ったこと があると言うんなら、この部屋か、あるいはP駅でのことでしょう」
「P駅?それではあなたはP駅の売店で働いておられるのですね?」
ダツは確信を持ってそう言いながら、P駅で売店を見た経験などないことにも気がつく。
「いったい、オレの寝ぼけた頭はどうしちまったんだろう」
小さく声に出して、ダツは言った。
「しかし、P駅に売店などありましたっけ? 何を売るんです? この町の住民は誰もよその 町に通勤していないし、通学もしていない。そんな駅では新聞さえ売れないじゃないです
か。だいいちぼくはP駅で売店の姿を見た憶えもない」
「おしゃべりなヒトなのね、あなたは。さっきから質問、質問、また質問。まるで市役所 の市民生活課調査係に調査を受けているようだわ」
「どうしてP市の市民生活課に最近できたばかりの調査係という部署があることをご存知 なのでしょう。偶然にもぼくは、その市民生活課調査係なのです」
「あら、そう。まるで知らなかったわ。それにしても、駅の売店で、アタシが毎日毎日売 っているものを何だとお思いなの?」
今度は女から質問が返ってきた。
「そうですね。どこか遠方の誰も行ったことのない土地の観光ガイドブック、あるいは座席補助のための快適な簡易ヒジ掛け、人混みを嫌う人のための携帯式呼吸器、それとも口腔内で膨張するチューインガムなら、ひょっとすると売れるのかも知れません」
女がフンと鼻で笑った。
「アタシが売っているのは、アリバイ。アリバイよ。駅の売店で売れるのは、アリバイで しかないわ。駅にやって来る人のすべては、電車に乗るためじゃなくって、アリバイを手
に入れるためだけにやって来るものよ。いいこと。アリバイを求めない人は、駅にすらや って来ないわ。まして電車に乗る必要もないの」
「アリバイとは、いったい何のことですか」
「アリバイは、アリバイ。あなたがナガラミ荘に住んでいるのか、あるいは住んでいない のか、たった今、あなたにアリバイが必要なように、どんな人にもアリバイが必要なの」
「それじゃぼくは、こんなにもはっきりとここにいるのに、ナガラミ荘の住人ではないの かも知れない、とおっしゃるのですね」
「アタシのことは、どう? あなたは、ナガラミ荘の四階にはあなた以外に住人はいないは ずだとおっしゃったわ。でも、アタシはここにいる。多分、ここにいる」
ダツの頭はますます混乱するばかりだ。
「それにしても、ぼくはP市役所市民生活課調査係なのです。あなたに関する調査をさせていただきたいのですが・・・・。それでなくともぼくは、昨日も全裸の女性の調査を終えた
ばかりで、今もって混乱の中に漂っているのです」
「全裸の女の調査がお好みなら、アタシも裸になりますわ。で、あなたのお名前は?」
「ダツです」
「ダツはダツロのダツですの? それともダツワ、あるいはダツミョウ、シンダツのダツな の? エダツモのダツ? キダツチのダツなの? 」
どれもダツの語彙にはない言葉だった。
「いいえ。ダツはダツ。ぼくの名前はそれ以外に説明のしようもありません」
「説明のできないことを求めるのも、アリバイなのよ。つまり、あなたは、名前によるア リバイさえも証明できない、ただそこにいるだけの存在と言う訳なのね」
女が勝ち誇ったように言う。 不意にダツは、目の前の女にパンチを食らわせ、衣服を剥ぎ取ってしまいたい衝動に駆 られた。 縮れて不揃いに伸びた赤毛の髪の真ん中に小さくやつれた顔、皺のよった首筋、弛んだ
下腹と筋肉のそげ落ちたかのような下肢が、目の前の黒いワンピースを着た女のすべての 情報のように思われた。もし、もう少しばかりつけ加えるとしたら、小さくて上を向いた
貧弱な鼻と、大きく見開いた目、顎が人間の意志の力を表現するのなら、鼻持ちならない 高慢や傲慢を、きっと女の顎は示しているのだった。 「アタシは駅の売店の女。あなたは市役所の市民生活課調査係。隣人って、どうしてこう
も似た環境になってしまうのでしょう。さあ、アタシをお抱きなさい。アタシを抱けば、 きっとあなたにもアリバイができるに違いないわ」
どうして不意に現れた隣人を、会ったその日に、それもこんな早朝に抱かなくてはなら ないのだ。これはきっと、まだ覚醒していない自分の心の混乱が巻き起こした幻覚
なのだ、とダツは思った。 すると、それまでの緊張や不可思議が溶解し、急に眠気を催したダツは、その場にへな へなとヘタリ込んでしまった。
窓の外にはっきりと陽差しがある。
いったい何時間ほど、ダツはこうして眠り込んでし まったのだろうか。再び目が覚めたのは、キッチンの流し台の脇、玄関ドアを入ってすぐ の床の上で、てっきりそこは自分の部屋だと思った。いるはずもない隣人、P駅の売店の女の存在など、ダツの記憶からは消え去っていた。しかし、居間の方を見やると、自分の
部屋には掛かっていない銀色のカーテンや見慣れない籐のテーブルと椅子、それに女が居住しているに違いない化粧品の臭いを確かめると、そこが自分の部屋でないこと、駅の売
店の女の存在が確かだったことに再び気がついた。 どうやら売店の女は、ドアの開け放たれた部屋とは別のもう一方の部屋にいる様子だっ た。カリン、カリンと、フォークか何かの金属と食器の当たる音がする。女が食事中なの
が分かる。
「あのう、何をなさっているのですか?」
ダツは上体を起こしながら、ドア越しの女に聞こえる声を出した。
「あなたのアリファイと、アタヒのアリファイを、今こうして擦り合わせているところだ わ」
売店の女は、口に何かを含みながら、もごもごと返事をする。
「今、いったい何時なんでしょう?」
ダツはきっと長い時間固い床に張り付いてビニールタイル状の跡が残ってしまっている に違いない右頬を撫でながら、まだ開かないドアの向こうの気配を窺う。
「二時五十分よ」と、向こうの部屋の声が聞こえた。 ダツは驚き、慌てて腰を上げた。
「いけない、市役所に行かなくちゃ」
そう叫ぶと、振り向いて玄関ドアのノブをガチャガチャと回す。鍵がかかっている様子 もないのに、しかしそのドアは一向に開いてくれない。 背後でドアの開く音がし、振り返るとあの女が立っている。黄色いバスローブに包まれたその姿は、数時間前に見た時よりもはるかに若く見えたが、縮れた赤毛とその真ん中に
ある高慢そうな顔は、やっぱり同一人物のものだった。
「市民のアリバイ探しのための、仕事というアリバイ作りのために出掛けて行く男が一人 いる、という訳なのね」
スパゲッティを食べていたのか、女の唇には赤いケチャップのようなものがへばりついていて、それがルージュを引いた唇のように艶やかに見える。
「ああ、何とでも言ってくれたらいい。ぼくには市民生活課調査係という仕事があって、 それは、あなたの言うアリバイ作りなのかも知れないのだから」
売店の女は表情一つ変えずに近づき、言った。
「じゃ、アタシのアリバイはどうなるの? アタシだってP市の市民のうちの一人でしょ。 今、アタシのアリバイがあなたに語り始めるわ。見て。ほら調査係さん」
女がクルクルと頭を水平に回転させ始める。あの小さい顔が一秒に一回ほどの間隔で正 面に現れる。見ているダツの目が回るほどのスピードだ。遠心力で縮れた赤毛が舞い上が
り、ダツの鼻面を打ちつけそうになった。
「ほう。ぼくはあまり関心しませんがね」
ダツが女に冷たく言い放つと、女は今度は片足を上げ、膝から下をブルブルとプロペラ のように回し始めた。
「ぼくはもう行きます」
ダツが回転する売店の女を無視して玄関を出ようとすると、背後から女の絞り出すよう な声が聞こえてきた。
「アタシを調査してちょうだい。あなたは調査係なんでしょ。P市の公僕なんでしょ。ア タシの躯は、アタシのアリバイだけれど、調査係というあなたの仕事のアリバイでもある
はずなんだから。調査してちょうだい」
ダツが自分の部屋に戻ると、飛竜が待ちくたびれたように言った。
「オレは、キミの隣人が課したアリバイだ」
ダツはそのまま再び寝込んでしまった。
無断欠勤の翌日、ダツは二日ぶりで市役所に出た。
市民生活課の職員たちは、昨日無断欠勤したダツに特別の注意を払う訳でもなく、いつ も通りに新聞を読んだり、お茶を飲んだりしている。 ダツはもうそれが市役所に出た際の習慣になっているように、すぐに椅子から立ち上が
り、市庁舎の外に出て自転車に跨がった。そして、もう一度思い直すように庁舎に引き返 すと、清掃局の一画に進み、市民にも開放されている「廃棄物処理細則」という分厚い冊
子の一ページ目から順に目を通していった。 ページをめくっていくと、「急性バブル硬化症」も「エメラルド症候群」も、すでに記 載されていて、それぞれに廃棄物としての処理形態がRとかXという記号で表示されてい
ることに気づいた。 ところが、ダツの欲しい項目の情報はリストの中に掲載されてはいなかった。 とりあえず、その日のダツの予定は明確に決まっていて、それはJ町3丁目45番地40
2号、つまりナガラミ荘の隣人宅に向かうことだった。 ダツが再び売店の女が躯のあちこちを回転させる曲芸について調べたいと思った訳では なかった。
その頃にはすでに、ダツの周りではあまりにも多くの病理的産物があり過ぎて、売店の女が見せた奇妙な回転技ぐらいのものにいちいち反応していては、自分のリポートすべき
対象が拡大し過ぎてしまうことは明白だった。売店の女の曲芸なんぞは、とるに足らない 日常の出来事であり、そんなことで貴重な調査リポートを汚すつもりは、ダツにはなかっ
た。たとえ、あの曲芸が売店の女の言うアリバイだとしても、そんなことにどれほどの意 味があろうとも思えなかった。 ダツが正式にナガラミ荘の隣人宅にP市役所市民生活課調査係として出向こうと決心し
たのは、まったく別の問題だ。あの売店の女が最初に発したひと言、コード105の廃棄 物に関する調査、それこそが調査係にふさわしい対象に違いなかった。なぜなら、P市の
「廃棄物処理細則」の中に、売店の女が言うようなコード名での廃棄物の存在はなかった のだ。
女は、確かに言った。「電車と地下鉄とバスを乗り継いで廃棄しに行かなくてはならな い」と。しかし、P市には電車やバスは走っているものの、地下鉄などどこにも走っては
いない。いったい、コード105の廃棄物とは何なのか。すでにP市役所市民生活課調 査係という職分に使命感さえ抱いているダツとしては、それは究明されなくてはならない
調査対象となったのだ。 つい一時間ほど前に出たばかりのナガラミ荘に再び戻ってくると、ダツは隣人の玄関前 に立ち、ドアをノックした。表札を見るのは初めてで、考えてみるとダツは隣人の名前
を知らなかった。 表札には「K」というイニシャルだけがあった。 ノックの後、三十秒ほど待ったが、応答はなかった。 ドアのノブを回してみると、カギはかかっておらず、玄関は開いたが、売店の女は留守
だった。
ダツはその足でP駅に向かった。女が働いているという売店に行けば、隣人に会えるは ずだ。ホタテ貝のへばりつく丘を越え、いつも通りに世界記録への挑戦をしてみたが、ど
こか気が焦っていて、坂の途中でペダルを漕いでしまった。そして、あっという間にP駅 の前に到着した。
P駅は、コンクリートの円柱を縦に半分に切り落として伏せたような長いドーム状の建 物で、ちょうどカマボコのような形なのだが、元は灰色だったに違いないその表面にスス
や埃が吸着し、どす黒く変色している。以前からダツは、それを「ナマコ」と呼んでいた。 そこから東西に走る四本のレールは、ナマコの腸のようにも感じられたからだ。
ナマコ全体から見れば、ほんの小さくくりぬいたような穴がP駅のエントランスになっ ている。 自転車をエントランスの脇に置きながら、これまで何度も利用しているP駅の内部について、ダツは記憶を呼び覚ます。エントランスを入ってすぐ左側に券売機が四、五台ほど並
んでいる壁面があり、その隣が駅事務所の窓口が二つ。正面に二か所の改札口がある。そ して右手には、名前だけの待合室のようなコーナーがあって、数人が座れるベンチが二台
向き合っているはずだ。 しかし、そのベンチから奥まった空間に何があったか、ダツはまるで思い出せない。歩 を進めながら、ダツの心に不安が芽生える。
エントランスを入ると、ダツは真っ先にベンチの奥に視線を這わせた。すると、そこに は明らかに過去に何物かがあって、その後に除去されたかのような無用としか思えない空
間が五メートル四方ほどに広がっている。何かを喪失した空間というものは、きっと誰の 目にも明らかなほど、残影を臭わせているものだ、とダツは考えた。そこに売店の女がア
リバイとする売店があったのではないか。ダツは思った。自分の記憶にはないが、売店の女が勤める売店はきっとそこにあったのであり、何かの理由、例えば販売成績の悪さなど
で閉鎖されたのではないだろうか。
ダツはその奇妙な空間に足を運び、すぐに踵を返すと、駅事務所の窓口に向かった。窓 口に人影はなく、ダツはカウンターの中に首を突っ込んで内部を窺った。
「誰かいませんか。市役所市民生活課調査係のものですが」
まるで応答がない。改札口に回ってプラットフォームを左右に見渡してみたが、一人の 人影もなかった。無人駅だったことは、これまでのダツの記憶にもないし、そんなニュー
スを聞いた覚えもない。改札口の上に掲示されている時刻表を見ると、あと十分ほどで上 り電車がやって来ることになっている。仕方なく、ダツはベンチの片隅に腰を下ろして、
次の電車の到着を待つことにした。
ほんの数分という時間が、まるで数時間にも感じられるほど、物音一つしない駅構内の 静寂は、ダツのズボンの右ポケットに棲息する飛竜の微かな身動きの音さえ響きわたらせ
るようだった。実際、ダツは飛竜に言った。
「静かにしろ」
すると飛竜は、ポケットから頭を出さずに言った。
「安心しろ。オレはキミの理由のない恐怖に対する弁解だ」
ダツの左手首に巻かれた腕時計と、改札口の時刻表の上に掛かった壁時計の共通した時 刻表示によって十分後が表示され、上り電車がP駅のプラットフォームに滑り込んだが、
乗降客の姿はどこにもなく、電車は予定通りにP駅を去って行った。もう一度、ダツは窓 口で呼び掛けてみたが、応答はなく、その日のP駅での調査を断念した。
二つの時計は、午前十時四十二分を指していた。
このサイトに掲載される著作物(文書、資料など)に係る著作権は特別の断り書きが無い限り、ミキオ・Eが保有します。
mikio-e can be reached at QWQ05617@nifty.ne.jp
Copyright(C)2001 mikio-e All Rights Reserve.