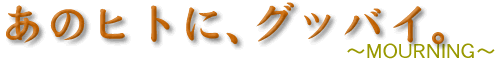|
●静かなること……
この人物は、僕の義父つまりワイフの父親である。数多くの著作があるが、僕はそのほとんどを読破していない。理由は明白だ。後半生のほとんどを、江崎誠致は囲碁三昧で明かした人物で、当然囲碁にまつわる著作が多い。僕は結局、囲碁の世界に一歩も足を踏み入れないままだから、書かれていることのほとんどを理解できないという致命的な原因があった。
それでも、1957年上半期の直木賞受賞作「ルソンの谷間」は、ワイフと知り合った学生時代に即座に読み、大学の現代日本文学のリポートとして提出した。僕自身は4歳ほどで父親を病気でなくし、反動からかその世代のオトナの男に対する畏怖と敵愾心が人一倍で、必要以上に生意気な口を利き続けたのだと思う。僕の実父もまた大戦中にフィリピンへの輸送船に乗り込み、あっという間に撃沈されて俘虜生活を送った人物だったので、すでに記憶の片隅に追いやられたとはいえ実父像をダブらせないワケにはいかなかった。
初対面は、ほんとうに緊張した。学生時代の同棲で始めたワイフとの共同生活の折に「娘さんと一緒に住むことになりました」と告白しに、当時東中野の自宅を訪れた時、仕事途中の義父が玄関先だったか書斎の脇まで出てきてくれた。「あ、そうか」
一見一人娘に無関心なのかと思わせるほど素っ気ない一言を頂戴しただけで、僕らは郊外のアパートで生活し始めた。すぐにワイフから「オヤジさんが一度食事でもしようって言ってるヨ」と告げられると、いよいよ僕の緊張は高まった。
なにしろ相手はそれまで直接会ったことのない職業作家で、さらに三十年近く前の当時にしてみても珍しい和服姿の御仁だから、そんな姿を見慣れない僕には強烈な威圧感を伴って見えても仕方ない。
新宿のステーキ屋に連れて行かれ、生まれて初めて食す分厚いステーキをコックが「いかようにいたしましょうか?」などと言うものだから、「レアがいいです」などと生意気な注文をし、これじゃいかにも血がしたたりすぎだろうと後悔する余裕さえなく、目の前の着流しの人物の存在感に圧倒された。
冷静沈着。物に動ぜず、淡々と酒を飲み、淡々とステーキを頬張る。長身痩躯で透き通るように色白のいかにも文学者の風情なのに、骨格はしっかりしていて、当時はかなりの健啖家でもあった。
さしたる会話もないまま、歌舞伎町のバー「ナルシス」に連れて行かれた。僕は根っからのおしゃべりだから、その間まったく黙っていたワケではない。何事か無駄なハナシを持ち出すたびに、例の「そうか」という義父の返事があったのを今も憶えている。「ナルシス」のママさんに「娘の連れ合いだ」と紹介され、酒を飲み、茫然自失となって初の対面は終わった。
その後、事あるごとに「ミキオを連れてこい」とワイフ経由で伝わってくる。そのたびに「ナルシス」やら他の酒場の当時の僕にとってかなり高い敷居をまたぐこととなった。
故・井上光晴さんは義父よりも年少のはずで、物静かな義父と対照的にガラッパチでバンカラ、豪放磊落。どんな酒席も氏にかかれば即井上流と化すほどのインパクトのある人物だった。「ナルシス」での初対面、義父から紹介された僕に、氏は開口一番こう言った。
「おう、お前ぇ。何かやれ。何かできるだろう」
幸い他に客はいなかった。義父に勧められて、僕は歌った。
当時まだ、「ナルシス」にはギターが置いてあって、酔客が時々ポロンポロンとやっていたのだが、井上さんの気迫に負けまいと、僕はアカペラで「オーソレミオ」を歌い上げた。高校時代にオペラの真似事をやっていたので、声のデカさだけはちょっとしたコケ脅しに使えたのだ。歌い終わると井上さんの、「いいぞ。やるじゃないか」に続いて、「さあ、飲め」が連発された。
その間、義父の表情は終始静かでにこやかで、奇妙なハナシだが、その時初めて僕は義父に認められたような気がした。確か僕が20歳代終わりの頃だったと思う。当時「ナルシス」には埴谷雄高さん、田村隆一さんなど錚々たる文壇の巨星が訪れていたようで、僕にはむしろ敷居が高すぎて、義父だけの夜に出没するのが常だった。今にして思えば本当に残念なことをした。
●達観と虚無思想
文壇本因坊に就いたこともあり、囲碁への造詣の深さは衆目の一致するところだった。その著書のタイトル通り「呉清源」さんへの敬愛は深く、それがやがて本人の意図しない度重なる中国行きにつながったのだと思う。
中国行きのハナシが最初にあった時、義父はかなり逡巡をしたはずだった。日中戦争をハッキリと侵略戦争ととらえ、あれほど国家国民を陵辱した地に日本人として出掛けることを潔しとしなかったのも、いかにも義父らしい。井上光晴さんなど親友の説得だったか、それともすでに来日して交流のあった中国の関係者たちの勧めだったのか、義父は珍しく翻意し、そこから中国棋界や文化人との親交を深めていった。中でも中国映画界で活躍する脚本家の1人に寄せる信頼は絶大で、中国訪問後に聞く土産話の中に「コウシュウさん」「カツコウドウさん」の名前が出る度に、僕自身もお会いしたい人物の印象を深くするばかりだった。さらに、すでに亡くなられた碁友であり書家の柳田泰雲さんが望んだ日中交流にも客人として参加するするなど、90年代に入ってからの義父は中国の人々との交流を心底楽しんでいた。中国の女流棋士・孔祥明さんは、中でも義父を「日本の父」と慕い、家族のみで行った密葬にも彼女を呼ばないワケにはいかなかった。際限がなくなるからと、一切外部に通知しないと言っていた家族の意向に異を唱え、呼ぶべきだと主張したのは僕だった。本来お知らせすべき関係者に非礼があったとしたら、ひとえにこの僕の責任である。2000年初夏に呼吸不全で入院検査し、末期大腸ガンを宣告された義父の元に通ってくれたのも孔祥明さんで、彼女はわざわざ自分のフィアンセを義父に面会させるほど信頼を寄せてくれていた。「シナ哲というのは西洋の哲学以上に深みがあって、会ってみたらなかなかの人物だった」と、中国の大学教授のことを嬉しげに語る義父の様子は珍しかったほどだ。「シナ哲」とは、中国哲学のことで、かつて言われていた文化領域さえも、この僕は知らなかった。
不徳の娘婿としてつきあったほぼ30年。酒が入り、興に入った時だけ、僕はときどき義父の戦前戦後のハナシを引き出すことに成功した。「ルソンの谷間」に描かれた旧軍隊の醜さ、戦後の一時期まで地下に潜って活動した共産主義運動、さらにはいかなる組織にも属さないと決断し共産党脱退に至るまでの経緯。
痛烈な虚無思想とホンモノのアナーキズムを義父に見ながら、その実、限りなく他者を許容するその懐の深さに、僕はいつだって打ちのめされてきたのだった。

|