
バックナンバー 2003年の「ちょっと言わせて」を読む
バックナンバー 2002年の「ちょっと言わせて」を読む
「ちょっと言わせて」目次へ戻る
|
電車の中で化粧をする女性について、いろいろと書かれたものを 目にするようになって久しい。たいていは「みっともない」「公私の空間の区別がない」などという非難調で、化粧をしている女性もガングロの女子校生とか、ハデな化粧の若い子が多かったような気がする。 ところが最近は、ごく普通の女性が電車のなかで化粧をしている。私は西武新宿線と地下鉄の丸の内線を使って銀座まで通勤しているのだが、駅のベンチでも、私鉄や地下鉄の中でも、一日に一人くらいは、ごく普通の会社員の女性が熱心に化粧をしているのを見かける。もともと人を眺めるのが好きな私は、そういう女性がいるとついつい観察してしまう。そこで気づいたことは、ごく普通に見えるナチュラルメイクでも、塗るものの数がやたらに多いことだ。下地クリームを2種くらい、ファンデーション、粉ファンデ、チークも2、3種類塗るし、「揺れる車内で器用に塗るなあ」と感心するマスカラだって、どういう組み合わせかよく分からないが3種類くらいを重ね塗りしている。ノーブラ、ノーメイクをかっこいいとした時期に青春時代を送り、化粧にあまり関心を持たずに生きてきた身としては、化粧品の進歩と種類の多さ、使い方の違いに驚く。そして、あれだけの化粧品を使ってナチュラルメイクができ上がっていく様子をつぶさに見るのは、なかなかおもしろい。ただ、こんなヒミツを男にみせちゃっていいのか?とは思うけれど。そして、「電車で化粧」が増えているの理由が、単純に時間の節約であることにも気づく。だって、これだけの手順を踏むと、メイクが完成するまでに、ゆうに30分はかかるのだ。 (2001年12月1日) |
|
「今に生きよ」とは、私が長年やっているヨガの教えだ。かんたんに言えば、過去にやったことを後悔せず、起こってもいない未来のことを心配せずに、今日一日をいっしょうけんめい生きよ、ということだと思う。こういうことを言っているのは別にヨガだけではなくて、「過去に起こってしまったことは変えられないのだから考えてもしかたがない、未来の心配事の99%は起こらないことなのだから思い煩うな」というようなことを、いろいろな癒し系の本が言っている。 もともと私は目の前の「快」を追い求める人間なので、自分がやった事に対して後悔する事はあっても思い悩む事はないし、先の事もほとんど心配しない。真摯さには欠けるかもしれないが、目の前の一日一日を楽しく生きていると思っている。だから、この教えを聞いた時も、そんなことはとっくに実践していると思っていた。 しかし、最近ちょっと様子が違ってきた。五月にガンで亡くなった父の事を考え始めると心が騒ぐ。もう少し、こうしてあげればよかったとか、本当はこう思っていたのかもしれないと考えてしまうのだ。もう一つ、心にさざ波を立てるのが息子の事だ。三月に高校を卒業したらあとは自分で人生を切り拓いていくべきだと思うし、親が心配してもしなくても勝手にやっていくとわかってはいるのだが、それでもついつい先のことを心配してしまう。 父を亡くして娘の役割は終わった。息子が卒業すれば保護者としての母の役割も終わる。そんな変化に、心が揺れているのだと思う。そんなとき、夫だけが十年一日のごとく同じペースで目の前にいるのが、けっこう貴重だったりする。 (2001年11月30日) |
|
一年ほど前だろうか、家から五分くらいのところに二十四時間営業のスーパーができた。人件費や光熱費を考えると採算が取れずにすぐにつぶれるのではないかと思っていたが、それなりに繁盛しているようだ。朝早く行くとベビーカーに赤ちゃんの乗せたお母さんたちがいる。ゆっくり買い物ができて、便利なのだそうだ。夜は会社帰りの若者を見かける。行きつけの美容院のおにいちゃんも「仕事が終わってから野菜が買えていいですよ」と言っていた。けっして客の数は多くないが、コンビニにはない生鮮品を求める需要は、思いのほかあるようだ。 私自身、最初は二十四時間営業なんて必要ないと思っていたが、最近は「便利」を実感している。病気の父のところに通っていた頃は、朝行きがけに、頼まれていたものや菓子類(諸国銘菓などの品揃えが豊富)をこのスーパーで買って会社まで持って行き、そのまま帰りに父のマンションに寄っていた。朝、会社に行く前に不足しているものを買いに行けるのもありがたい。夜、家に帰り着いて、食事をして、一息ついて、そこから明日の予定を考え、足りない食材があっても買いに行ける。実際に行くことはたまにしかないが、「いつでも、行けばある」ということは、心の余裕を生む。 しかし、働いている人のことを思うと、ここまで便利を享受していいのだろうかとも考える。不況で労働者の立場は弱くなり、深夜勤務などが増えているとしたら、便利よりも皆が人間的な暮しをできるように考えなくては、と思うからだ。 (2001年11月29日) |
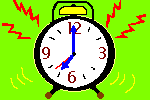 |
私の一日は、子供を起こすことから始まる。高3の息子を毎朝起こしてやるというのも甘い親だと思うが、ほっておいて寝過ごしたら飛び起きて学校へ行くかと思うとそうでもないので、ともかく遅刻しないで学校に行かせるために、朝起こすのが習慣になってしまった。私も高校時代まで祖母に起こしてもらっていたので、しょうがないかと思っている。 「さっさと起きろ」と何度か声をかけながら、子供の弁当を作り、自分の朝食の支度をし、コーヒーを入れて新聞を読む(この時間には、夫は寝ていて起きてこない)。ようやくごそごそと起きてきた子供が「お腹がすいた」と言えば朝食を作ってやるし、「いらない」と言えばそのままほっておく。やっと支度を終えた子供が「行ってきます」と声をかけたところで、玄関まで見送りにいく。 そのときに息子がよく言うのだ。 そんな話を友人にしたら、「若い頃って、自分の自由になることはとても少なくて、行かなきゃ行けない時間とかやることが全部決まっているから疲れるのかもしれないね」と言う。「私も学生時代は疲れてたもん。疲れなくなったのは、自分で自分の時間をコントロールできるようになってからよ。すべて自分で選んでやっていると思うと、疲れないわよ」 確かにそうかもしれない。そして、自分で自分の人生をコントロールできる「疲れない人間」になるために、若者は皆、疲れながらも学校に通っているのかもしれない。そう思うと、「疲れた」という息子の言葉も、大目にみてやるかという気になった。 あと五か月で高校も卒業。その後はもう、朝起こすのはやめるよと先日宣言した。卒業後は自分の生活を自分でコントロールして、疲れたと言わずに生きていってほしいと思う。 (2001年10月31日) |
|
私が五年連用日記をつけ始めたのは、今から十四年前のことだ。 それまでも日記はずっとつけていたけれど、出産を機に会社を辞め、生まれて十カ月の息子の子育てに追われていた当時の私には、一日一ページの日記を書く時間がなかった。子供を生んだ後はコピーライターとして家で仕事を続けるつもりだったのだが、子供の世話に時間と体力を奪われ、子供が眠るころには自分もクタクタという毎日。一方、夫は、私の分も働かなくてはと、ますます仕事に力を入れていた。 「一日中子供の相手なんて、息が詰まる。それに、こんなに体が疲れるんじゃ、いつまでたっても仕事ができない」そう思うと、泣きたくなった。子供に縛られているという閉塞感と、このまま仕事ができないのではないかという焦りが、心の中で黒雲となって渦巻いていた。 そんな時、本屋で五年連用日記に出会った。 一九八五年一月一日。私は五年連用日記をつけ始めた。毎日六行。日記をつけながら一日を思い返すだけで、子供をゆったりと眺められるようになった。三、四年目になると、毎年同じ時期に風邪を引いていたり、「去年はこんなこともできなかったんだ」と息子の成長に驚いたり、前の日記を読むのもおもしろくなってきた。なによりも一番よかったのは、その時々の自分の気持ちを、「書く自分」が客観的に見ることができたことだ。いらいらしたり心がささくれだつような時も、そんな気持ちを書くだけで心が静まった。考えてみれば他愛のないことが原因だったり、単に心配のし過ぎだったり…。書くことで、そういう自分の精神状態が見えてくる。 この日記をつけ始めたことで、私は自分が一番つらかった時期から抜け出せた。以来ずっと、私は五年連用日記をつけている。子供は大きくなったけれど、日々の暮らしの中で心が揺れるできごとは多い。そんな時、五年後の自分を読者として想定しながら日記を書くことで、心安らかにいられる自分がいる。 (1999年5月) |
|
1999年に、京都の京田辺市が主催する「一休とんち大賞こばな しの部」に応募したところ、大賞をいただきました。京田辺市で行 なわれた授賞式に参加し、一休禅師の菩提寺である一休寺を訪ね、 京都の友人たちとも会って話すという楽しい時間を過ごしました。 以下がその「こばなし」です。 |
|
|
「明日は日曜?」 水曜の午後、喫茶店に入ったぼくは、藤原紀香に似た髪の長い女の子と茶髪にピアスの男の子のいるテーブルの近くに座った。きれいな女の子だ。四十過ぎの男が若い男女の会話に聞き耳を立てるなんて行儀が悪いと思いつつも、ついつい二人の会話を聞いてしまう。 「ねえ、どうして黙ってるの」「ちょっと、おまえの声が聞きたくてさ」 「好きって言ってよ」 「今、おまえのことを考えていたんだよ」 「うそばっかり」 女は深刻な顔。だんだん表情が険しくなる。ところが男のほうはヘラヘラ笑っている。おいおい、ピシッとしろよ。でないと女に嫌われるぞ。 「 今度、一緒に映画を見に行こうよ」 そうだ、そうだ、その調子。女なんて、ちょっと甘い言葉をささやけば機嫌が直るものなんだ、がんばれ。ぼくはもう完全に男の味方になっていた。 「わかっているわ。じゃ、明日は会えるのね」 「いいよ、じゃ今度の日曜にね」 ぼくがあれっ?と思うのとほとんど同時に、二人は頬から右手を離 した。二人の手の中には銀色の光る携帯電話があった。 (1999年7月) |
 |
「ねえねえ、ぬばたまって知ってる?」 「はい、これがぬばたま。ヒオウギって植物の実なんだって。どうしてぬばたまっていうんだろうね」 「四十四歳で初めて、高校の古典の時間に読んだぬばたまの実体を知るなんて、なんか楽しいねえ」 国分寺街道を南下して右折し、しばらく行くとちょろちょろと水の流れる水路があり、流れに沿って石畳の『お鷹の道』が続いている。やがて右手に武蔵国分寺の本堂が見えて来た。境内に入って行くと、左奥に万葉植物園があるという案内板が立っていた。植物園は、起伏のある狭い敷地に万葉集ゆかりの植物が無造作に植えられ、それぞれに小さな名札が下がっているだけというそっけないものだった。冬枯れの草木も多く、どういう姿形なのかもよくわからない。それでも、一つ一つの草木と名札を見て「こんな植物も万葉集に詠われていたんだね」と話しながら一回りした。右手の郷土資料館の前にも、万葉集に出てくる植物の鉢植えがずらっと並んでいた。ふと入口横の鉢植えの名札を見て、私は背中に電気が走るのを感じた。枯れ草が何本か残っているだけの寂しげな鉢の名札に、『ヒオウギ(檜扇)アヤメ科種子はぬばたま』と書かれていたのだ。なんという偶然。生まれて初めてぬばたまを見た日に、この黒い玉を実らす植物にも出会ってしまうなんて。 数日後、辞書を調べている時に、突然別の項目が目に飛び込んできた。 |
|
木曜の夜十二時近く。突然電話が鳴り、ファックスが送られてきた。前日に出した原稿に赤字が入って戻って来たのだ。ファックスの1枚目には「夜分にすみません。直しの原稿は来週でけっこうです」の文字。来週でいいのに、なんでこんな時間に突然ファックスを送ってくるのだろう。来週でいいのなら、翌朝送ってくればいいではないか。今夜送らねばならない事情があるのなら、事前に電話するか、事情の説明が書いてあってもいいはずだ。 「何を考えているんだろうね」とつぶやく私に、「こんなに忙しく働いていますって言いたいんじゃないの」と夫。 たしかに、この編集プロダクションは、深夜勤務が多い。編集者たちが出社するのは昼過ぎで、終電で帰ったり、泊まり込みで仕事をする女性編集者が何人もいる。「段取りが悪くて仕事が遅いか、忙しいのが好きなだけ」と夫は言うが、「一人だけ実力があったり段取りがよくても、仕事が片づかないこともあるからね」と、私はけっこう同情的だ。しかし、「もう少し考えてファックスを送れ」という気持ちは伝えたい。一方で、仕事をもらっているフリーライターの身としては、正面から文句も言いにくい。 さてどうしたものかと思いながら、机の上にあった前日の夕刊をふと見ると、次のような文が目に止まった。「昔は女工哀史のような明確な悲劇と目に見える貧困があり、もっとずっとわかりやすかった。しかし、今や編集部で朝の三時にコンビに弁当を食べながら、ミラノブランド品マップを書く女子は、自分が不幸であるコトを明確に自覚できない」 これは、十月十六日朝日新聞夕刊の「当世三十女胸算用」にイラストレーターの渡辺和博が書いている文の一部だ。職場の花として扱われたくない女性たちは、安い給料で夜中に働かされているのに、頼りにされていることに充実感を感じてしまう。雑誌作りという聞こえのいい仕事をしていることに満足してしまう。もっと自分の不幸を自覚して、「労働条件改善、実力に見合った給料を」と要求しなくては、体を壊すか都合のいい労働力で終わってしまうのに。男も女も、自分の働く環境をよくする努力ができてこそ、一人前の職業人と言えるのではないだろうか。 翌日私は、ファックスを送って来た編集者に「緊急の場合以外は連絡は朝十時から夜八時くらいまでにお願いしますよ」とやんわり伝えた。自分が気分よく仕事をするために。そして、彼女が自分の不幸に気づくことを願って。 (1997年6月) |
|
目を覚まして時計を見ると、朝の十一時だった。「おはよう。十一時って、ホント?」居間のコンピューターでゲームをやっている夫に声をかける。「ほんとだよ」の声を背に受け、洗面所で顔を洗い息子の部屋に行く。 寝ぼけ眼で居間に戻りコーヒーを入れる。うー、頭が痛い。久しぶりの二日酔いだ。昨日で息子の学校が終わり、夏休みに入った。「明日からもう、早起きしなくてもいい」と思うと、それだけで気分がいい。深夜のテレビでは全英オープンの生放送をやっていて、これがなかなかおもしろい。冷えたビールがなくなったので、途中から冷酒に変えて、ゴルフと男の幼児性について、夫と語り合っていたのだ(からんでいたという説もある)。顔が腫れたのは、この冷酒のせいだ。 日曜の昼のテレビからは若い男女の話し声や笑い声がひっきりなしに聞こえ、「あんたたち、そんなんでお金もらっていいの?」と私はだんだん凶暴な気分になる。こんな時は風に当たるに限る。 「散歩に行ってくる」と告げて自転車に飛び乗れば、大きな池のある石神井公園はすぐそこだ。私がいつも座るのは、目の前に白い蓮の花が揺れる水際のベンチ。目を閉じて太陽の光をまぶたいっぱいに感じると、世界は柔らかなオレンジ色に変わる。耳を澄まして風の音を聞き、深呼吸を繰り返して、眉間に神経を集中させる。すると、揺れていた心がピタッと収まり、体がスーと楽になる。あとは居眠りをするもよし、近くを通る散歩人たちを観察するもよし、 こんなふうに一時間近くぼーっとしていると、体のなかに動のエネルギーが満ちてくる。「帰りに図書館に寄ろう」とか、「今夜は春巻を作ろう」とか、日常的なことが思い浮かぶようになったら引き上げ時だ。まだ頭の痛いのは直らないが、こうして一人、自分のことを考える時間を持てるのは、二日酔いの効用といえそうだ。 (初出 NiftyServe Fbookc Mes6 1998年7月) |
 |
約束のイタリアン・レストランに入っていくと、店の奥で香子が小さく手を振っている。 高校時代、甘味喫茶であんみつをつつき、チョコレート・パフェを食べながら、おしゃべりに興じた私たち。大学を卒業して、それぞれに仕事や家庭を持ってからは、香子の家に集まってビールを飲むのが楽しみだった。そして、今。四十歳を過ぎて、ちょっとおしゃれなレストランで、ピザやパスタを味わいながら赤ワインを楽しむ。大きくなった子供たち、キャリアを積んだ仕事、健康管理の必要な夫、年老いた両親など、一息ついたことも、これからが心配なことも、まだまだいろいろあるけれど、とりあえずこうして集まって笑顔でお酒が飲める幸せを、それぞれが胸のうちで感じているに違いない。グラスを重ね、口が滑らかになるほどに、心が軽くなる三人だけの時間。これからもこんな時間を、年に一、二度持てたらいいなと思う。 (初出 NiftyServe Fbookc Mes6 1999年1月25日) |
|
最近俳句を始めた。 そもそも私は、俳句よりも和歌が好きだった。泉式部、与謝野晶子…。ほとばしるような激情を三十一文字のなかに封じ込めて歌う力強さ。万葉集、源氏物語に歌われた相聞歌の言葉遊びの優雅さ。それに比べて俳句は、自然を切り取って来ただけの観察句ばかり。 しかし今回は、指折り数えて俳句の真似事をしてみる。十七文字で自然の一風景を切り取る難しさに気づく。俳句の本を読む。俳人の多さと、秀句の多さに驚く。指を折り句を作る。入門書を読む。自然描写が単なる自然描写ではなく、作者独自の発見であることに気づく。指を折り句を作る。季語辞典を読む。季語の持つ力と深さを知る。同時に自分の日本語の語彙の少なさを痛感する。指を折り句を作る。そして今の実感。「いやー、俳句ってむずかしいねー。でも、おもしろいねー」 この気持ちがずっと続くかどうかわからない。でも私は今、久しぶりに大きな楽しみを見つけて、うきうきしている。 (初出 NiftyServe Fbookc Mes6 1999年2月21日) |
|
「ふるさと」というと、人は美しい自然と人情を思い浮かべるのだろうか。私が育った東京にも、緑豊かな美しい自然や、近所の人々が助け合う人情がある。しかし、私が「自分の街」として思い浮かべるのは、人があふれ、デパートやファッションビル、映画館、飲食店、ゲームセンターなどが立ち並ぶ渋谷の繁華街だ。女子高生の風俗を伝えるニュースによく取り上げられるセンター街、人気歌手見たさに一階放送ブース前に若者が群がる「タワー・レコード」のある街…。 JR山手線と私鉄の京王井の頭線、東急東横線、地下鉄銀座線、半蔵門線が交錯する大ターミナル渋谷駅。駅前には、待ち合わせ場所として東京一有名な忠犬ハチ公の銅像があり、ハチ公前広場には携帯電話を持った若い男女があふれている。渋谷センター街には、若者に人気のドラッグ・ストアやファーストフードの店が並び、制服にルーズソックスの女子校生が闊歩する。駅の回りには、騒音と猥雑、物欲、食欲、性欲など、種々雑多な欲望がうず巻いている。 駅から歩いて十分ほどの距離には、あらゆる手作り材料がそろう「東急ハンズ」。その近く、東急デパート本店隣には、映画館と美術館、劇場などが集まる「東急文化村」があり、文化や娯楽を求める中高年の姿が多く見られる。西へ十分ほど足を伸ばすと、そこは閑静な住宅街。マンションや戸建て住宅のなかに紛れるように、松濤美術館や陶磁器を専門とする戸栗美術館がある。 十五の春、私は渋谷の二つ先の駅にある都立高校に通い始めた。初めての電車通学。学校帰りに友達と寄る渋谷のにぎわいが、とても新鮮だった。フルーツ・パーラーでのおしゃべり、ジャズ喫茶でのデイト、「東急名画座」で見る恋愛映画のときめき。渋谷で思春期を過ごした私は、渋谷で大人になった。痴漢やナンパにあって、世の中にはろくでもない男がいるということを知り、ストリート・ミュージシャンに街のエネルギーを感じ、着飾ったおばさんたちを出会って、母の世代のパワーに圧倒された。美術館に通って、「世の中にこんなに美しいものがあったのか」という感動も味わった。ある日は恰幅のいい紳士にからかわれ、ある日はホームレスのおじさんに親切にされた。渋谷で出会ったたくさんの人を通して、どこにでも信頼できる人や立派な人がいること、そしてそれは年齢や地位、富や見かけに関係ないということを学んだ。友情の強さともろさ、恋のときめき、無関心の悲しさも知った。私はこれらの体験のすべてを通して大人になった、といえるだろう。 かつては大人の街だった渋谷は、今やゲームセンターやファンシーショップが並ぶ子供っぽい街になった。インターネット・カフェができ、呼び込みや宣伝のティッシュを配るガイジンが目につくようになり、うず巻くエネルギーも雑多になった。しかしそれでも、渋谷は渋谷。よくも悪くも、人々の欲望とエネルギーのあふれる街であることに変わりはない。生まれてからずっと東京で生きてきた私にとって、種々雑多な人間のエネルギーが集まり交錯する街・渋谷は、「私のふるさと」を象徴している。どう変わろうと、私はその変貌を見届けながら、この街を愛し続けるだろう。 (初出 NiftyServe Fbookc Mes6 1999年3月) |
|
新宿歌舞伎町。横断歩道の信号が変わるのを待ちながら、二十代のOL風の女性が携帯電話のボタンを押す。信号が緑に変わると、ロングコートのすそを翻し、横断歩道を渡りながら携帯電話で話を続ける。 携帯電話でいつでもどこでも声を聞ける便利さは、人に会う楽しみを減らしているかもしれない。人と会って話をするのが苦手という若者たちは、苦手な状況や気まずさを味わうことなく、安易に電話をかけることで、多くのものを失っているのではないだろうか。携帯電話の多くは、歩きながら、車に乗りながら、人を待ちながらの、ついでのコミュニケーションだ。そんな状態で人と話して楽しいだろうか。 一月十四日の朝日新聞「天声人語」に、東洋大学主催の「学生百人一首」の入選作が載っていた。その中の一首。 |
|
電車で隣に座った三〇代の男が、頬に手を当てながらボソボソとつぶやいている。 東京には、酔っぱらっていなくても一人でぶつぶつとつぶやく男や女がいる。この男も自分で自分に言い聞かせているのだと思っていた。ところが十分ほどして、男が頬に当てていた手の中に、小さな形態電話が隠れていることがわかった。話は三十分近く続き、その間男は「大丈夫、気にするな」を延々と繰り返した。 携帯電話すべてを否定するつもりはない。工事現場での連絡、待ち合わせ場所の確認、宅配便の在宅確認など、携帯電話ならではの利用法も多いだろう。しかし、「いつでもどこでもかけられる、受けられる」が売り物の携帯電話は、相手の都合を考え、自分を律する心をマヒさせる。そのような垂れ流しのコミュニケーションで、きちんとした人間関係が作れるだろうか。そうした思いから、私は携帯電話を持つ気になれずにいる。 (1999年1月14日) |
|
「全日本の監督になった日から、いつやめることになるかわからない、と家族には言ってあります。幸いまだ体が動くので、何をやっても家族を養っていくくらいのことはできると思います」なにげなくテレビに目をやると、岡田監督がこう語っていた。サッカーワールドカップ三連敗の責任を取って「やめる」と宣言した直後の記者会見での一コマだ。 このシーンを見て、私は何年か前の吉田栄作の結婚式を思い出した。美男俳優として有名だった彼は、ニューヨークで演劇の勉強をしたいと仕事をやめていた。その充電期間中に、十歳以上年下のモデルの女の子と華やかな結婚式を挙げたのだ。結婚式直後の記者会見の様子を、私はやはりテレビで見ていたのだが、集まった芸能レポーターたちは結婚のお祝いもそこそこに、「充電期間中に結婚して、生活の方は大丈夫なんですか?」「今後の生活はどうするつもりなんですか?」と、"一時稼ぐのをやめた男"に対する非難がましい質問を重ねていった。 今まで俳優をやっていたんだから、普通の男よりも蓄えがあるだろう。奥さんがモデルなんだから、しばらく奥さんに稼いでもらったっていいじゃないか。私はそう思いながら世間のモラルの代表のような顔をした芸能レポーターたちが、こんなにも"稼がない男"を非難することに驚いていた。そしてもう一つ、私を驚かせたのは当の俳優の答だった。自分の経済状態についてとやかく言われることにいらついた彼は「女房ひとりくらい、何をやってでも養っていきますよ」と吐き捨てるように答えたのだ。 女房を養えないと、男失格なのだろうか。そんなに目の色を変えて「家族を養うくらいできる」と宣言しなくても、「蓄えがあるのでしばらく休憩」とか「代わりに妻に稼いでもらいます」と言えばいいのに。俳優の答を聞いた時も、テレビで岡田監督を見た時も、私はそう思った。 そして先日、中三の息子が、級友の修学旅行感想文が載った「学年通信」を持ってきた。その作文には、京都の清水寺で弁慶が担いだといわれるこん棒を持とうとした山田君の感想が書かれていた。「男三人でやっと持てるくらい重いこん棒だそうだが、僕が動かそうしてもビクともしなくて、男としてちょっと情けなかった」ああ、彼にとって「重い物を持てない男」は情けない存在なんだ。私は、山田君が将来、体は弱いけど立派な男に出会えるといいなと思った。 十五歳の子供にも、「男はこうあるべき」という理想像がある。大人の男たちは、もっとたくさんの「こうあるべき」を抱えているのだろう。そしてパートナーである女たちにも、たくさんの「男はこうあってほしい」があるのだろう。理想を持つのはいいことだ。ただ、その理想が、おしきせだったりステレオタイプでないことを願う。世間の「こうあるべき」から自由になって、自分らしい「男像」を追求する男たちが増えることを願っている。 (1998年7月6日) |

|
花を育てるのは子育てに似ている。手をかけて、よかれと思って愛情を注いでも、のびのびと育たないこともある。日光と水と肥料をふんだんに与えても、根腐れしてしまうこともある。失敗続きで落ち込むこともあるが、それでも、新芽が出たり茎がぐんと伸びるのを見ると、本当にうれしい。小さななつぼみでも見つけようものなら、ちゃんと花が咲くだろうかとハラハラ、ドキドキ。花が咲けば、それが花屋で見るよりはずっと貧弱な花でも、人に見せたいような誇らしい気分になる。 子育ての結果はすぐには出ないが、花を育てた結果は一年でわかる。育てる楽しさと難しさを毎年味わいながら、春になると、「もっときれいな花を咲かせたい」と思い、せっせとベランダの鉢にタネをまく。 花を育てるようになってからは、子供のことも「いつかあの子なりの花が開くだろう」と、おおらかな気持ちで見られるようになった。私が機嫌よく花を育てているのを一番喜んでいるのは、実は十四歳の息子かもしれない。 (初出「ガーデンQベランダガーデン」(主婦と生活社)1998年6月) |

|
「犬と猫とどちらが好き?」と聞かれたら、断然、猫と答える私だが、最近「犬を飼うのもいいかもしれない」と思い始めている。こんな気分になったのは、私の週末の散歩コース、石神井公園でよく出会うステキな女性のせいだ。 最初にその女性と出会った時、彼女は犬を連れた背広の紳士と立ち話をしていた。その二人の姿の、絵になることといったら…。その後も何度か、男性と立ち話をする彼女の姿を見かけた。 ある日、木のベンチにすわってぼんやりと池の水面を眺めていると、目の前をくだんの女性が通り過ぎた。髪にはだいぶ白いものが混じっているが、背筋を伸ばして歩く姿はキビキビしててカッコいい。ステキね、と思って眺めていると、向こうからやって来た男性が、すっと近寄って話しかけた。 知らない男が話しかけたというのに、彼女はにこやかに応対している。男も目を細めて足下を見ながら相好を崩す。五分ほど歓談した後、二人は静かに左右に別れていった。 彼女はいつも知らない男性と自然に話し、自然に別れていく。そんなつき合いを可能にするのが、彼女の足下にいて、彼女と同じように器量よしのビークル犬だ。赤ん坊ではこうはいかない。十年前に私が子供をベビーカーに乗せて歩いていた頃、にこやかに話しかけてきたのは、お節介焼きのおばちゃんか小さい子供を持つ母親たちだけだった。ところが犬を連れて歩くと、あんなふうに知らない男性がにこやかに話かけてくる。向こうも犬連れ。近所の人だろうし、犬の様子を見れば飼い主の人柄もわかる。年を取っても、犬がいれば男友達ができるのだ。 そこで私は、「犬を飼うのもいいかもしれない」と思い始めた。目標は十年後。犬を飼える家に住み、背筋を伸ばして歩けるような体型を維持し、笑顔の美しい女性になるのだ。そう考えただけで、人間が上等になったような気がするから不思議だ。子供は親を「親」に育てるというが、犬は人間を「上等な人間」に育ててくれるのかもしれない。 (初出「わんぷれ3号」(北北西)/1997年12月加筆訂正) |
|
新聞を広げると、満面に笑みを浮かべた大男が、着ているコートをマントのように開いていた。コートの裏には、小さなピンバッジがびっしりと並んでいる。彼のようなコレクターがアメリカにはたくさんいて、オリンピックやスポーツの世界大会などがある度に、開催地を訪ねてはピンバッジを交換するのだという。 「ぼくはごつい顔だから、最初は怖がる人もいるけれど、これを見せて、チェンジ!って言えば、みんなニッコリしてくれるよ」 新聞記事にはそんな談話が載っていた。オリンピックにはあまり熱狂しない私も、こういう話を読むと冬季オリンピック開催中のナガノに行ってみたくなる。小さな国の選手たちと商店街の交流をテレビで見たり、通訳ボランティアでナガノに滞在していた友人の話を聞くと、オリンピックというお祭りに参加する楽しさも想像できる。 スポーツ、語学、ピンバッジ。心から愛し情熱を傾けるものがあれば、見知らぬ人とも心の交流ができる。街角で「チェンジ、チェンジ」と呼びかける彼と、そのまわりに笑顔で集まる日本人たちを思い描くと、高い旅費を払ってピンバッジ交換の旅に出るコレクターの気持ちが分かるような気がした。 ピンバッジを集めてみようかな。ふと、そんな気にさせられる新聞記事だった。 (1998年3月8日) |
|
シドニーのちょっと高級なアクセサリーと小物の店。クロスステッチが趣味の私は、刺繍仲間のお土産に、陶器の指抜きを選んでいた。と、そこへ高そうなスーツを着て大きなイアリングをした五十代の日本女性が飛び込んで来た。山岡久乃をきつくしたような美人タイプの女性だ。 私の方を見もせずに立ち去った女性も、日本で会ったら礼儀正しい奥さんだろうに。外国での買い物に夢中になって、まわりへの配慮を忘れてしまったのだろうか。一回り年上の日本女性の言動を見て、そんなことを考えたが、私もすぐにその店での買い物に没頭してしまった。 日本に帰って、雑誌に載っていたグッチのバッグの値段を見て、急に腹が立ってきた。黒革のバッグが五十万円。海外で半額で買っても二十五万だ。あんな態度で、こんなに高いバッグを買おうとしていたのか。高いものを持っている人が上品、優雅というわけではないけれど、着てるものや持っているものにふさわしい立居振舞というものがあるではないか。そう考えると、あの女性店主の何事もなかったような態度も気にかかる。ブランドショップが並ぶ一角にあるあの店には、年配の女性が毎日のように飛び込んできては日本語でまくしたて、言葉が通じないとわかると黙って飛び出して行くのかもしれない。 「美しい五十代が増えれば、日本は変わると思います」という化粧品の広告があるが、世界を旅する五十代の日本女性たちが、美しい立居振舞で出会った人を魅了すれば、日本のイメージもずっとよくなるだろう。「金持ちの無作法な日本人」と軽蔑されないために私たちがやるべきことはたった一つだけだ。言葉ができないことに臆せずに、日本にいる時と同じ態度で、礼を持って相手と接しようではないか。 (1998年3月4日)* 暮れの福引に当たって、2月3日から8日まで、家族3人でメルボルンとシドニーの旅を楽しんできました。上のコラムはその旅の一コマです。 |
 |
春になると、ご近所の玄関や庭先を眺めながらの散歩が楽しい。ピンクの花ミズキが並ぶ家の前を通り、芝生の庭に置かれた大鉢にあふれんばかりに咲くパンジーを眺め、一列に並ぶマリーゴールドのプランターの前を過ぎるころには、私の心にも春の喜びが満ちて体がフワフワと軽くなった気がする。 やがて、私がひそかに敬愛するお宅の前にやってくる。門の両側には、季節ごとにデザインが変わるコンテナガーデンが置かれ、いつ行っても見事な作品を見せてくれる。「どんな人が作っているのだろう。初老の優雅な女性だろうか。呼び鈴を押して、ステキな寄せ植えのお礼を言ってみようか」と思うが、意気地がなくて果たせずにいる。 そのかわり、家に帰ると草花の世話に熱が入る。「あんなふうに道行く人に幸せを分けたい」と、気分が高揚するのだ。花は優しい心を育てるが、花に育てられた優しい心は、ことのほか強い伝染力を持つに違いない。 (初出「ガーデンQコンテナ&ハンギング園芸」(主婦と生活社)1998年2月) |
|
「あなたのホームページを読んだけど、おもしろかったわ。私、日本に興味があるの。日本のお正月について教えてちょうだい」 日本語と英語の文章を並立したホームページを作って1年半になるが、最近どういうくわけか、「ホームページを見たよ」という英文のメールが多くなった。それだけインターネットが普及したか、プロバイダーの検索機能が充実して「JapanSketchbook」というタイトルのJapanが検索にひっかかるのだろうか。英語の手紙を書くのは時間がかかるし、疲れるし、ちょっと負担だ。でも、読んだと言われるとうれしいし、数少ない読者なのだから大事にしたい。そこで、アンチョコの「英文日本絵とき事典・文化風俗編」(JTB)で、お正月の紹介文をさがすことにした。私も日本人のはしくれ、日本の文化・風俗は肌で感じているが、知識はあいまいなことが多い。今回も「除夜の鐘」の項を読んでいて発見があった。百八の鐘が人間の百八の煩悩を表すということは知っていたが、仏教の教えでは鐘が鳴り終ると世界は新しくなり、人もクリーンな状態で新しいスタートを切るのだという。皆がお正月にあんなに「おめでとう」と言うのは、世界が新しくなったからなのだ。 しかし、年が明けたら去年のことはすべてチャラという考えは好きになれない。悪いことをした人間にとって都合がいい考え方じゃないか、積み重ねがないなんて進歩がないじゃないか、と思ってしまう。そういえば私は、「なんでお正月だけ特別に、朝になるとめでたいのだろう」と考える子供だった。その気持ちは、今もあまり変わっていないわけだ。こんな気持ちをトレイシーに伝えるには、アンチョコの英文では間に合わない。そこで今年は、英語をたくさん書く努力をしようと思う。みなさん、今年もどうぞよろしく。 (1998年1月9日) |
|
一九九六年八月四日、寅さんが死んだ。一九六五年の『男はつらいよ』第一作以来、毎年お正月映画に登場して多くの日本人に愛され続けてきた男。日本人なら、この映画シリーズを見たことがない人でも、寅さんのあの顔、あの帽子、あの腹巻き姿は瞬時に思い浮かぶに違いない。水戸黄門と同じように毎回ステレオタイプなストーリーながら、いや、そのストーリーゆえに、義理人情に厚い日本人の心を引きつけ、多くの人がその死を悲しんだ。 しかし、密葬が終わり、テレビのワイドショーにその死が取り上げられるようになって、私は奇妙なことに気づいた。寅さんは日本人ならば誰でもが知っている超有名人だが、寅さん役者・渥美清について、私たちは何を知っているだろうか。ワイドショーで、渥美清そっくりの若い男がインタビューを受けるのを見て初めて、「ああ、渥美清には子供がいたんだ」と思った。私生活と仕事を分けるのが、渥美自身の美学だったというが、役者・渥美清の影は薄い。テレビに映された彼の葬式で弔辞を読んだ女優・倍賞千恵子は、遺影にむかって「おにいちゃん」と呼びかけ、映画の中の妹役を演じた。その葬式は渥美清の葬式ではなく、役柄の寅次郎の葬式のようだった。その後、柴又で開かれたお別れ会でも「寅さんを偲ぶ会」の大看板が掲げられていた。 役者・渥美清ではなく、役柄の寅次郎として葬られ、偲ばれることに、渥美清は満足しているだろうか。私に彼の思いを知る術はないが、与えられたひとつの役柄だけを演じ続ける役者の悲劇を感じさせる葬式だった。「よい夫、よい妻、よい社会人。そんな役割だけを演じ続けて、ナマの自分をなくすなよ。オレみたいになっちまうぜ」と、あちらの世界で、俳優・渥美清がつぶやいているような気がした。 (初出 Niftyserve Fbookc mes6 1996年10月) |
 |
人はみな、自分の子供の名前を考える時、詩人になるという。もうひとつ、私たちが詩人になる時があるとすれば、それは「サンタクロースって、本当にいるの?」と子供たちに聞かれた時だろう。親たちはみな、子供たちの夢を壊さないためにはどう答えればいいかと思いを巡らせるはずだ。 うちの息子は五歳の時、サンタクローズを心から信じていた。七歳になると好奇心をいっぱいにして「どうして欲しいものがわかるの。サンタさんはどこに住んでるの。うちにはどうやって入ってくるの」と、親を質問攻めにした。九歳の息子には知恵がついて「この包装紙、うちにあったのと似てる」と言って親をあわてさせた。十一歳の息子は「サンタさん、いつまでプレゼントを持ってきてくれるかな」とつぶやき、私が「サンタさんを信じている間は持ってきてくれるんじゃないの」と言うと、「やったー、ぼく信じてるからね、持って来てって言っといてね」と、念を押した。 そして一九九六年のクリスマス、十二歳才の息子にサンタクロースはやって来なかった。「中学生になって、運賃も大人の料金を払うようになったんだから、もうサンタさんは来ないと思うよ」と言ってあったのだけれど、それでもクリスマスの朝、息子はほんの少し、サンタからのプレゼントを期待していたらしい。 その後、私たちはサンタクロースについて何も話していない。何も語らないことが、彼が大人になることを受け入れたしるしのようにも思える。「サンタクロースを信じる」という暗黙の共犯関係を崩したことへの無言の抗議のようにも思える。しかしともかく、私たちはサンタが来ない特別な朝を迎え、夫と私はサンタクロースになるという楽しい時間を失った。 「嘘をついてはいけない」と教える世界中の親たちが、年に一度つく悪気のない嘘。この嘘について、今、息子がどう考えているのかはわからない。でもきっと、何かすっきりしないものがあるだろう。もし彼が、「サンタクロースなんて本当はいないのに、なぜ嘘をついたの?」と聞いてきたら、どう答えたらいいだろう。一九八七年の冬、ヴァーニジアという名の八歳の女の子が、シカゴ・サン紙の記者に手紙を書いた。「親愛なる記者様、サンタクロースは本当にいるのでしょうか?」 記者は新聞紙上に、こう返事を書いたという。「ヴァージニア、サンタクロースはいます。目には見えないけれど、愛や、友情や、優しさが私たちの心の中にあるように、サンタクロースは、私たちの心の中にいるのです」 これは、クリスマスの度にテレビやラジオで紹介され、絵本にもなっている有名な話なのだが、この話が百年近くも語り継がれてきたのは、多くの親が 「サンタークロースは本当にいるの?」という難問に苦労して答えてきたからだろう。 そう、私は息子の問いに、こう答えよう。「サンタクロースはいるよ。なぜならサンタクロースとは、親の愛だから。プレゼントがなくても親の愛を十分に感じ取れるほどキミの心が成長したから、サンタは来なくなった。でもその代わり、キミはこれからサンタになる楽しみを味わえるんだよ」と。 (初出 NiftyServe Fbookc 1996年12月) |
|
「おばあちゃんのお漬物って、どうしておいしいのかね?」 こんな会話をしながら、私はよく祖母が漬物をつけるのを手伝った。塩漬け、ぬか漬け粕漬け、梅干しと、春夏秋冬、祖母は旬の野菜を漬けて、おいしく漬かったものを家族に食べさせるのが楽しみだった。 ところが、私は祖母が漬け物を漬けた手順をほとんど覚えていない。もっとちゃんと漬け方を教わっておけばよかったと思うが、当時小学生だった私には、「シロウリのタネを取るのを手伝って」とか、「ハクサイを四つに割って」などと突然言われて、手伝わされるのはけっこう迷惑だった。だから言われたことだけやって、さっさと遊びに行ってしまったのだ。漬け終るのを最後まで見ていたことはない。覚えているのは「手のひらが違う」とか「心の込め方が違う」というような精神論めいた言葉ばかりだ。そして当時の私はそんな祖母の言葉をお説教臭いと感じただけで、全然信用していなかった。 さて、自分が毎日家族の食事を作る身になってみると、昔の祖母の言葉に真実味が感じられる。鍋に手をかざして「おいしくなれ」と念じてもおいしくなるとは思わないし、手のひらから"気"が出るとも思わないが、おいしくなれと思いながらハンバーグのタネをこねれば、練りにも力が入るし、スープの灰汁(あく)取りもていねいになる。そんな心配りから生まれる味の差を、祖母は「手のひらが違う」と表現したのだろう。そんなことが少しわかるようになった。 グルメというのが、作った人の心遣いと、そこから生まれる味の違いがわかる人だとすれば、家族のために食事を作るようになって私もグルメの階段を一段上ったことになる。主婦の食べ歩きに眉をひそめる男性も多いようだが、実は主婦こそ、グルメに一番近い存在なのかもしれない。主婦の舌が肥えれば、家庭料理もおいしくなるし、日本の食文化も安泰なのだ。そう考えれば、豪華なレストランで五千円のランチコースを食べる女性たちがテレビに写っても、許せる気がしませんか? (初出 NiftyServe Fbookc 1996年12月) |
 |
4月24日(木)晴れ 4月25日(金)晴れ 4月26日(土)晴れ 私はどうも純粋とかピュアと形容される人間が苦手だ。純粋さと隣合わせの無知を感じてしまうし、彼ら、彼女たちの「ピュアでないものは受け入れない」という姿勢が狭量に映る。せっかく優しい心を持っているのだから、私の憎まれ口に反論するくらいの懐の深さを持ってほしいものだ。 (初出 NiftyServe Fbookc 1996年12月) |
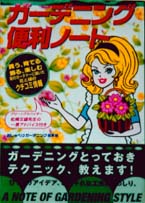
|
子供は嫌いだった。ベタベタしてうるさいし、自分勝手で手に負えない。電車のなかで自分は座らずに小さい子供を座らせる母親を見ると、なんて常識がないと憤慨した。ところが、自分の子供を持ってみると、ベタベタすることろがかわいい。欲ばりでわがままなのも、これが人間の本質かもしれないと鷹揚に受け止められる。電車の席も「立たせて疲れて泣かれるより、座らせた方がマシ」という母親の心理が見えてくる。子供を持って知ったことは多いし、前より他人に優しくなったような気がする。中2の息子が自分の考えを述べるのを聞くと、こんなおもしろいやつを作っておいてよかった、としみじみ思う。さて、私は今、『ガーデニング便利ノート』という本を書いている。これはアマチュアガーデナーの体験談を集めたくちコミ情報集なのだが、最初にこの本の話が来た時は、あまり乗り気ではなかった。植物は好きだが、今の私に花を育てているヒマはない。園芸は時間と場所、心にゆとりのある人の優雅な趣味だと思っていた。しかし、仕事だ。自分が園芸をやらなくてもいい本はできる、と思って引き受けた。そして、たくさんの人の話を聞き、たくさんの本を読む間に、うちのベランダにもどんどん鉢が増えていった。これがあの人がカンタンに殖えると言っていたニホンスミレ、これがあの人が育てやすいと勧めてくれたパキラ、と思うと愛着がわいて、つい買ってしまう。水やりの手間は一鉢でも十鉢でも同じと考えると次々に新しい鉢が欲しくなる。新しい花が咲くのを見ては興奮し、若葉の艶にうっとりする。こんなはずじゃなかったのに、とつぶやきながらも、私はけっこうガーデニングを楽しんでいる。 新しい体験、新しい仕事の楽しみは、自分も知らない自分を発見できることかもしれない。だから、これからも「新しいこと」が目の前に飛び出してきたら、とりあえずそれに飛びつこうと思っている。 『ガーデニング便利ノート』は1997年6月に双葉社より出版されました。園芸好きの人達のクチコミ情報を集めたイラスト満載の楽しい本なので、興味のある方は本屋でさがしてみて下さい。 (1997年5月) |
|
「おかあさん、きょうは弁当がいる」 まわりの友達が母親の心のこもったお弁当を食べているのに、コンビニのおにぎりなんて可哀想、と思った。でももう一つ、子供にコンビニのおにぎりを持たせるなんて、ひどい母親と思われるでしょうね、とも考えた。そして、そんなふうに考える自分に、ちょっと苦い思いを抱いた。たしかに、手作りのお弁当は一つの愛情表現だ。でも、弁当を作らないから愛がないなんて、誰にも言わせはしない。そう思っているのに、息子の思いや、まわりの見方が気にかかる。 クラブから帰った息子に、さりげなく昼食の様子を聞いた。「カワイソー」なんて言われなかったかどうか心配だったのだ。ところがなんと、「エザ、いいなー」とうらやましがられたという。中学生の男の子にとっては母親手作りの弁当より、コンビニのおにぎりのほうが、カッコイイものらしい。 もしかしたら弁当を楽しんでいるのは、食べる子供よりも、作っている母親のほうかもしれない。母親たちは、小さな四角い箱の中で、愛情表現と自己表現が同時にできるのだから。実は、私もお弁当を作るのが好きだ。でも、これからは弁当をムリして作るのはよそう。息子は、母の弁当もコンビニのおにぎりも、両方を楽しむ術を知っているのだから。 (初出 Niftyserve Fbookc Mes6 1996年8月) |
|
人付き合いのへたな私は、子供のころから一人でいるのが好きだった。編み物、刺繍、洋裁、読書、そして書くことと描くこと。趣味といえば一人で没頭できるものばかり。でも、不器用な私が作ったものの出来は、決してよくなかった。子供時代にほめられたのは作文だけだ。 書くことを仕事にしたのは、自然の成り行きだった。大学時代に好きな男と暮らし始めて、生活費を稼がなくてはならなくなった。いろいろなアルバイトをやってみて、その中でいちばんラクに稼げて性に合っていたのが書くことだった。以来ずっと、「こう書いてほしい」「ああ書いてほしい」という注文に応じて文章を書いて暮らしている。仕事で書く楽しみは、没頭する楽しみだ。自分の役割を知り、決まった制約の中で最高のものを作ろうと考えながら文章を書き始めると、まわりの雑事はすべて消え、時間がゆっくりと流れ始める。書くことだけに集中していると、とても自由な気持ちになる。この気持ち、この解放感が味わいたくて、私は書くことを続けている。 七年前にパソコン通信を始めた。入ったその日にメッセージを書き込んで、たくさんのコメントをもらって、通信が生活の中に組み込まれるようになった。五才の息子がいて、なかなか外に出かけられない時期だったので、いつでも自由に人と話のできるパソコン通信が楽しかった。 おしゃべりの延長であるパソコン通信の中で、コラムを書く時だけは「書くこと」を意識する。でも、コラムを書く楽しみは、仕事で書く楽しみとは別のものだ。自分の本音を書くと、相手の本音を引き出すことができる。自分をさらすと、相手も心の内を見せてくれる。そんなことを繰り返していると、気の合う相手、尊敬できる相手、毒があるけど憎めない相手がわかってくる。コラムを書くことは、そうした相手を見つけ出すための有効な方法だ。読んだ人の声が聞きたくて、読んでくれる相手について知りたくて、私は自分を語るコラムを書き続けている。 (初出 Niftyserve Fbookc Mes6 1997年6月) |
 |
私は蓮の花が好き。なぜだろう。静かな水面を彩る優雅さにひかれるのかもしれない。泥水の中にすくっと立つ力強さにひかれるのかもしれない。大きな丸い葉と花の造形の妙にひかれるのかもしれない。なぜだかわからないが、毎年蓮の花の咲くころになると、体の中の血が騒ぐ。好きな男の吐息を、胸の厚みを体で感じたいと願うのと同じ気持ちで、蓮の花の吐息を肌で感じたくなる。 そこで小さな旅に出る。今年も水辺の妖精たちは、いつものように私を迎えてくれた。一面の蓮の葉、一面の蓮の花。その美しさ、その生命力を感じて、私は私の夏を呼吸する。 ふと気付くと、蓮池の周りには、私と同じように花の吐息を感じている人達がたくさんいた。日がな一日、蓮池のそばで暮らし、蓮の花を眺め、時には瞑想し、時にはのどかに眠る。もしここがインドだとしたら、彼らは修行僧、もしくはすべての煩悩を捨てたヨギとして尊敬されるかもしれない。しかし、ここは不忍の池。彼らは汚い、気味が悪い、と嫌われることの多い路上生活者だ。 同じことをやっているのに、この違いは何だろう。この違いを作り出すのは、私たちの差別意識かもしれない。そんなことを考えながら、私はゆっくりと池の周りを歩いた。彼らを見てインドの行者を連想したのも、同じことをしているだけなのにと思ったのも、花の吐息のせいかもしれない。 そう、たぶん蓮の花には、人を内省に誘う力があるのだ。夏の一日、蓮の花を眺めるのは気持ちがいい。この気持ちのよさを、私はあなたにも感じてほしい。そして、花の吐息を胸いっぱいに吸い込んだとき、あなたが何を考えたか、あとでそっと教えてほしい。 (初出 Niftyserve Fbookc Mes6 1997年9月) |
 |
「みんながマダームと呼んで大事にしてくれたのよ。もう、とってもいい気分だったわ」 でも今なら母の気持ちがわかります。イタリア男の「マダーム」は、八百屋のおじさんの「おくさーん」とけっして同じではありません。「とってもお似合いですよ、マダーム」と言いながら、母の首にネックレスをつけてくれたのが風采の上がらないみやげ物屋のおじさんだったとしても、その言葉がネックレスを売りたいだけのお世辞だったとしても、彼が母の目を見ながら言った「マダーム」には、五十歳に近い女性を女として扱う気持ちが濃密に漂っていたに違いありません。母は、それがうれしかったのでしょう。毎日マダムと呼びかけられ、いい気持ちになって、自信を持って、輝いて日本に帰ってきました。母のウキウキした気分は、帰国後一か月くらいは続いたような気がします。 男を成熟させるのは女、女を成熟させるのは男です。こんなちょっとしたことで、男性は女性を輝かすことができるのです。手始めに、あなたの奥さんに、心の中で「マダム」と呼びかけながら接してみませんか。とびっきりの笑顔とか、おいしい料理とか、「新しいパソコンを買ってもいいわよ」という言葉が返ってくれば、試みは大成功。あとはご自由にどうぞ。以後あなたが、女性を輝かせる力を奥さん以外の方に使っても、私は目をつぶっていますから。 (初出 Niftyserve Fbookc Mes6 1997年9月) |
 |
私がお気に入りの品物を並べている飾り戸棚の中に、ミニチュアの「モーリス・ミニ」がある。息子が山ほど持っていたトミカのミニチュア・カーの中の一台だ。手のひらにちょうど乗るくらいの大きさで、緑と白のツートンカラー。ずっしりと重く、ドアとトランクが開閉できるようになっている。 子供が大きくなって、ほかのミニチュア・カーは、みな人にあげてしまった。でも、この一台だけは、ずっと飾り棚の中にある。私は車にはまったく興味がない。子供のころは車酔いに苦しんだし、東京に育ち東京が好きな私は、車の必要性など全く感じない。それなのに、このミニクーパーは手放せない。 なぜなら、この車を見るたびに、ある人のある表情を思い出すから。彼は夫のジャズバンドの仲間で、ミニクーパーをこよなく愛していた。バンドの練習があると、大きなウッドベースを狭い後部座席に積んでスタジオにやってきた。うっとりとしたような視線を愛車に投げかけながら、クーラーが効かない、デイトの途中で車がエンコした、修理したいがイギリスから部品が来ない、というような苦労話をうれしそうに話した。それは、「私が彼に恋していたら、嫉妬に狂うに違いない」と思わせるような視線と語り口だった。 そんな彼がある日、車を買い替えたという。「ディーラーに車が引き取られた時は涙が出そうになりましたけどね、家族向きの車じゃないですから」と彼はつぶやいた。再婚して子供ができて幸せになった彼は、家族のために車を替えた。後悔はしていないと思う。偏屈なイギリス車への愛を捨てて、妻と息子と自分のための車を手に入れたのだから。でも私は、ミニチュアのミニクーパーが捨てられない。涙が出そうになった、と言った時の彼の表情が忘れられないから。窮屈で乗り心地の悪かったミニと彼との絆を覚えておきたいと思うから。 (初出 Niftyserve Fbookc Mes6 1997年7月) |
|
「おかあさん、これっていじめだよね」と、テレビで「機関車トーマス」を見ていた中一の息子がつぶやいた。「機関車トーマス」は『ポンキッキ』という幼児番組に登場するほんの5分ほどの話。擬人化された機関車たちが、自分の力を誇ってわがままにふるまったり、小さな機関車に意地悪をしたりする。その中で、主人公のトーマスは、大きな機関車のからかいや意地悪に負けずに、自分の仕事を懸命にこなす。幼稚園のころは「トーマス、がんばれ」と応援していた息子は、今そこに、社会のどこにもある弱いものいじめの構図を見ているようだ。おまけに、この鉄道会社のオーナーのナントカ卿も嫌いだという。機関車も運転手も、卿の言葉に一喜一憂するからだ。ここでも、息子は権力者にヘイコラする社会の縮図をみているのかもしれない。 もう彼は、「機関車トーマス」を楽しめない。もう彼は「みにくいあひるの子」を楽しめない。四歳の息子は、みにくいあひるが美しい白鳥になっただけで、手をたたいて喜んだ。でも、いまなら考えるだろう。醜いことは悪いこと?持って生まれた容姿や肌の色で相手を蔑むなんて最低じゃないか!と。 私は、絵本を楽しめなくなった息子を誇りたい。こういう物の見方ができるようになったのは、彼が成長した証拠だ。絵本を楽しむには、純真な心が必要だといわれる。でも、その純真さの中には、往々にして無知が含まれている。純真で無知な人間より、汚れを知ってそれに対処する知恵を持った人間のほうが、私は好きだ。 (初出 Niftyserve Fbookc Mes6 1997年7月) |
 |
「明日から3日間、部長以下全員で雑誌の名前入りのティッシュ配りをする」。新雑誌を刊行したばかりの某新聞社の局長会議の決定だ。次の日、雑誌にかかわりのある部の部長以下全員がハッピを着て、誌名が大きく刷り込まれたティッシュを配ることになった。なーに、昼休みのオフィス街で、たかだか1時間ほどのことだ。 しかし、長年人の上に立って仕事をしてきた管理職の男達にとって、これはつらい試練だったようだ。「ティッシュを配るために新聞社に入ったんじゃねーや」とつぶやいて雲隠れした者、「そんなもの、さっさと配っちまえばいいんだ」と、ダミ声で雑誌名を連呼しつつ、あっという間に配り終えた者、ティッシュを渡す手の角度と相手が受け取る確率から、一番効率のよい角度をみつけて楽しんだ者もいた。でも、入社以来私をかわいがってくれた吉岡課長は、「この歳になって、こんなことをさせられるなんて情けない」と肩を落とした。お人好しで、よくお茶をおごってくれる吉岡課長が意気消沈した姿に、私はちょっと同情した。ノイローゼになるかもしれないと、半ば本気で心配した。 あれ以来課長は元気がない。心配だなあと思う私を、課長はお茶に誘ってくれた。そしてコーヒーを前にして、課長はしみじみと言った。「江崎くんねー、僕は職業に貴賤はないと思っていたのに、ティッシュを配っている時こんな姿を友人に見られたら恥ずかしいと思ったんだよね。そういう自分が、なんか、いかんなあと思ってねー」 そうだったのか。課長はやっぱりいい人だ。それもただのお人好しじゃない。自分の中の"他人を見下す心"に気づいて、それを恥じる高潔さを持っている。地位も肩書きもお金もいらない、夫にするならこういう高潔な心を持った人がいいなあ、などと考えながら私は心の中で課長にエールを送っていた。 (初出 Niftyserve Fbookc Mes6 1997年6月) |
|
4月18日朝9時、高田馬場北口改札付近。人の流れに乗って、山手線高田馬場駅から、地下の東西線へと乗り換えようとするが、きょうは人の流れがみょうに滞る。「なに、これ、どうしたの」とあたりを見渡すと、混雑する人の波の中できょろきょろしたり、立ち止まったりしている若い子がいる。「そんなとこに立ってたら、じゃまだよー」「行き先の掲示板を見るなら、もっと端に寄んなきゃだめじゃない」 たまに仕事で出てくると、コレだ。こういう混雑がいやで、会社勤めを辞めたのに…。それに今日は、ふつうに歩くだけでやたらに人にぶつかりそうになる。なんで、そんなにトロトロ歩くのかなあー。苛立ちが、体の底から少しづつ沸いてくる。 「なんか、ヘン。ああ、そうか、今日は4月18日か!」気づいたとたんに、沸いた怒りがスーと引いていった。なーんだ、この若い子たちは、東京の新人だったのか。そーか、そーか、よく来たね。私も電車通学を始めた時は、あたりをキョロキョロ見回したっけ。最初は驚くことがたくさんあるけれど、そんなのにはすぐ慣れちゃうよ。慣れるっていうのはいいことだと思う。その世界で生きていくコツを身につけることだから。あなたたちの驚きと慣れのパワーが、この街の魅力を作っていくはず。歓迎しますよ、新東京人! (1996年6月) |
|
きっと、ちょっと驚いた顔をしたと思う。親友が、私に安産のお守りをくれた時のことだ。 彼女と初めて出会った高校時代に、私は神仏を信じないで生きることに決めていた。そのことを彼女は十分知っているはずなのに十年以上も、本当の友達だと思ってきたのに私のことをそんなにわかってなかったの、という言葉がのど元まで出かかった。「あなた、絶対に安産のお守りなんかもらいに行かないでしょ。だから、あたしがかわりにもらってきたのよ。嫌いだろうけど、引き出しのスミに入れておいたってバチは当たらないでしょ」 そうか、私の反応は予想していたわけね。わかった、わかった。ほんとうは気持ちだけもらっておくと言いたいところだけれど、しょうがない、引き出しのスミに放り込んでおくことにするか。 その時は妊娠七カ月。お守りのことはすぐに忘れた。仕事と家事、生まれてくる子供のための準備に忙しかったし、なによりも自分の体の変化を持てあましていたから。 月満ちて無事に息子が生まれ、病院のベッドで一息ついた時、彼女がお守りをくれたことを思い出した。けっしてお守りのおかげで無事に生まれたとは思わない。けれど、お守りをもらってきてくれた彼女の心が、どこかで私を勇気づけていてくれたような気がした。 |
|
「えー、うっそー、ヤダー、なにコレ?」都立高校に入学し、電車通学を始めた初日の世間知らずの女の子の心の声です。朝7時45分、山手線新宿駅ホーム。ホームにあふれんばかりのおじ、おじ、おじ、おじさんの群れ。スルスルと入ってくる電車。プシューと開くドア。ドドドッとドアに殺到する人の群れ。なんだかうそみたいと思いながらも負けじと電車に乗り込む女の子。「体がまっすぐに保てなーい、一度上げた足を下ろす場所がなーい、隣のおじさんが重ーい。なにコレ?」 渋谷駅で電車からはじき出され、高校へ向かう道すがら女の子は考えました。「これが世間の荒波だったか。スマン私は甘かった」 一カ月後、女の子は成長しました。電車のドアに向かってドドドっと突進したら、すぐに右折。後ろから殺到する力をかわして座席中央付近の吊り皮を確保。そして、くたびれたおじさんの顔や汗の浮いたおねえさんの顔を眺めます。夫婦で通勤するらしい男女の会話に聞き耳を立てます。後ろに痴漢の気配がすれば、クルッと向き直ってあやしいおにいさんの顔を見つめるという手も会得しました。ここにいる一人一人に違う人生があって、みんなけっこうがんばって生きているんだ、という当たり前のことに気づいて元気づけられたりもしました。 ラッシュアワーをこうやって楽しむようになった時、私は私の生まれた街東京のゴチャゴチャパワーをほんとうに好きになったような気がします。朝の通勤をまさに地獄と感じている新社会人のみなさん、一か月の辛抱です。あなたなりの満員電車の楽しみ方を見つけて下さい。そのノウハウがあれば人生はけっこう楽しめる、と私は思います。 (初出 NiftyServe Fbookc Mes6 1996年4月) |
|
あの日から一年、弟は鶏肉を食べなかった。それは、ある夏の日のこと。母の実家を訪ねた私たちの顔を見て、祖母は「大きくなったねえ」と大喜びした。そしてその日、飼っていた鶏を一羽つぶして、水炊きを作ってくれたのだ。 都心の小さな二階家に住んでいた私たちにとって、母の実家はまるで別世界だった。青々としたたんぼに降り立つ大きな白い鳥を見て目を見張った。脇の小川でどじょうを捕ったり、畑の見慣れぬ葉っぱを引っ張ってにんじんやじゃがいもが出てくると、その度に私たち兄弟三人は歓声を上げた。そしてあの日、青い顔をした弟に呼ばれて裏庭に行くと、そこには喉を裂かれた鶏が血抜きのために逆さに吊されていた。 その夜、祖母は「今日はごちそうだよ、たくさん食べなさい」とニコニコ顔で水炊きの鍋を食卓に運んできた。何も知らない下の弟はおいしそうに食べた。当時十二歳だった私は、胸に石が詰まっているような気分だったけれど、祖母の気持ちを思って黙って食べた。そして弟は一口も食べなかった。 この日の情景を鮮やかに思い出したのは、息子が初めて自分で釣った魚を刺身にして食べた時だ。大きな魚が釣れてうれしそうに帰って来た息子に、夫が魚の捌き方を教えた。呼吸するえらやビクビクッと動く尾を見て、息子は魚を殺していることを実感した。たぶん、ちょっと泣いたと思う。「この魚の命をもらうんだから、ちゃんと食べような」と夫に言われて、息子は黙って食べた。 一年後に鶏肉を食べようと決心した弟も、胸に石を抱えながら刺身を食べた息子も「食べるとは殺して生きることだ」と実感し、そのことを受け入れたのだと思う。以来、息子は食事をあまり残さなくなった。そして私の料理に対する姿勢も少し変わった。命をもらうのだから皆が残さず食べられるように、おいしく作ろうと思うようになったのだ。 (初出 NiftyServe Fbookc Mes6 1996年2月) |
|
舞台には椅子が二つ。二人の若い女性の登場。日本語と英語のセリフが交互に語られる一風変わった芝居の始まりである。一人は丸顔の日本女性。一人は金髪の小柄なイギリス人女性。二人は静かに椅子にすわる。 今日は八月十五日。敗戦記念日である。ヘソ曲がりの私は、敬老の日にだけ老人が敬われるのを苦々しく思うのと同じように、この日にだけ反戦への思いが声高に語られる風潮に、毎年すこし距離を置いて過ごしてきた。ところが今夜、私の敬愛する英語教師アンが戦争をテーマに芝居をやるという。これは見逃すわけにはいかない。 「これは私の席です。少し窮屈ですが、背もたれはまっすぐで、足もぐらぐらしていません」という英語のリフレインを聞き、戦争で踏みにじられたたくさんの席を思いながら、少し窮屈、いうのがいいと思った。ゆったりと大きな椅子を占領する人がいれば、座る場所のない人が出てくるだろうから。背もたれが真っ直ぐなのも気に入った。部屋でゴロゴロする息子にも、背筋を伸ばした生活をしろと言っているのだ。シャンと伸びた背中には、人としての矜持が感じられる。さて、足がぐらぐらしないためには何が必要だろう。愛、金、健康、教育、自由、平等、平和……? 四本の椅子の足に相当するものを選ぶのはなかなか難しい。それでも、今、自分の席があることの幸運と責任を感じていた。 こんな思いにとらわれているうちに、舞台は第二幕へ。第一幕のシリアスな雰囲気とは打って変わって、こちらは軽妙な喜劇仕立て。何でも疑問に思ったことは聞かずにいられない女の子が「なぜ戦争は起こったん?」「王さまは裸とちゃうの?」と聞きまくって、大人たちの冷笑と困惑を引き起こす。 女の子のメッセージは、「人の言葉を鵜呑にせずに、ほんと?なぜ?と疑問を持って、自分の頭で考えよう」ということ。真実を語る勇気を示す逸話としては、『裸の王様』はちょっと陳腐だ。正直を言って、またかと思った。それでも、旧ユーゴ紛争やフランスの核実験再開に揺れる世界を思うと、「王様は裸だ」と言った子供の勇気を持たなくては、そういう子供を育てなくてはと思った。 劇のタイトルは『透明の中、永遠のかなた』。アマチュアの演劇集団なので、公演は一日だけだ。久しぶりに芝居を見て熱くなった。そして今日ほど、この芝居を見て熱くなるのにふさわしい日はないと思った。 (初出 『音信』1995年10月号) |
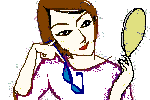
|
髪をパープルに染めた。といっても、はたから見たらほとんどわからない。太陽を背にして髪が逆光に浮かんだ時、輪郭がほのかに紫がかる程度だ。ヘア・マニキュア。「これなら二、三カ月で色が落ちるから、試しに染めてみたら」と、行きつけの美容院ですすめられて決心した。よくある栗色じゃつまらないから、ちょっと冒険心をおこして大好きな紫色にした。美容院から帰ったら必ずヘアスタイルをほめるように言い聞かせてある夫と息子は、その日もちゃんと髪をほめてくれたけれど、色については何も言わなかった。 こんなふうに、ほとんど誰も気づかないのだけれど、私はみょうにウキウキする。紫のセーターを着るといつもより映えるし、パープル系の口紅も鮮やかに感じられる。「お母さん、このごろ白髪抜いってって言わなくなったね」という十二歳の息子の言葉にも「最近、白髪が減ってきたみたい」とにっこり笑って答える。いい気分だ。 こんな気分になったことは昔もあった。十三歳で初めてストッキングをはいた時は、りっぱな大人の女になったような気がしてうれしかったっけ。初めてショートカットにした日は女優気分だった。初めて絹の下着をつけた日は誰でも誘惑できそうな気がしたし、カルバン・クラインのスーツで初出社した時はいっぱしのキャリアウーマン気取りだった。自分が背伸びしていることは十分わかっていたけれど、でも、ほんとにいい気分だった。そういえば、パソコン通信を始めた日だって特別な世界を手に入れたような気がして興奮したものだ。 ということは、これからもこういう瞬間がたくさんあると期待していいんじゃないだろうか。そう、年を重ねるのも悪くない。これからまだ何十回も、何百回も、こんなふうにいい気分になるかもしれないのだから。これを読んだ若者たちは、「中年の負け惜しみだ」と言うかもしれない。言ってもいいよ。でも私は、二十一歳の自分より今の自分の方がずっと上等だと思っている。そして、こう思えることが中年になるということだとしたら、それはなかなかステキなことじゃないかと思うのだ。 (初出 NiftyServe FBOOKC Mes6 1995年11月) |
|
「どうして女って、あんなにダイエットに 夢中になるんだろう?」 でも、だからといってりえママと同じ体型 になったりえちゃんをちやほやするだろうか? ポチャポチャよりダボダボがいいというだろうか? 多くの男たちは、そうはいわない。 できることなら、見目麗(うるわ)しくスタ イルのいい女のコと並んで歩きたいのだ。そ のことを、若い女のコたちは見抜いているの だよ。 このままでは"見た目を飾って、男に選ば れるのを待つ"という男と女の関係は二十一 世紀になっても変わらないかもしれない、と 私は嘆かわしい気分になっていた。 そんな時、近くのコンビニで"男のダイエ ット"を特集した雑誌をふと目にした。そう か、男もダイエットの時代なのだ。そういえ ば3、4年前にテレビで、たけしがダイエッ トをした話をしてたっけ。アメリカでは太っ た管理職は自分の体重を律することもできな いと、その管理能力を疑われるという。Jリ ーグの隆盛で、引き締まった男の体を目にす る機会も多い。「成人病がコワい」「管理能 力を疑われてはタイヘン」というおじさんの ダイエットから一歩すすんで、いまは「カッコいいと思われたい」という若い男のダイエ ットの時代なのだ、よしよし。 たしかに人間は見た目だけじゃない。でも 私は、見た目も自己表現の大切な部分だと思 う。少なくとも男が女を見た目で選ぶだけの 男女関係より、互いに選び合う男女関係の方 がずっといい人間関係が作れるんじゃないか な。 (初出:NiftyServe FBOOKC Mes 6 1995 年12月) |
|
うーん、これは危険だ、と思った。 しかし、こんな状況で何人の女がノーと言 えるだろう。心優しい女なら、とりあえずイ エスと返事をするだろう。「後で本心をきち んと話そう」と思いながら。でも一度喜ばせ てしまった男に、後で本当のことを言うのは 難しい。感激屋の女なら、このプロポーズの やり方にポーっとなって、ついその気になっ てしまうかもしれない。そして半年くらいた って、もう後戻りできなくなった時に「あれ は一時の気の迷いだった」と気づくのだ。 こんなプロポーズをされたら、女は人生を 誤るかもしれない。 ドアを開けたら、女がリボンを身体に巻い て「あたしをあげる」と言った時のことを想 像してほしい。恋人に、「私、あなたに会う ために生まれてきたような気がするわ」と言われた時の心のおびえを思い出してほしい。 そして、その気のない女たちも心の中でた め息をつく。 男女の仲には思いこみが多い。だからこそ、 贈り物にもプロポーズにも逃げ道を残しておいて。ちゃんと逃げ道を作っておいてこそ、 相手の真意がわかるのだから。そして、それ でも相手があなたを選んだ時、二人の関係はより深くなるのだから。 (初出:NiftyServe FBOOKC Mes 6 1995 年12月) |
バックナンバー 2003年の「ちょっと言わせて」を読む
バックナンバー 2002年の「ちょっと言わせて」を読む
「ちょっと言わせて」目次へ戻る
