

|
ロシア料理のグリヴィというのをご存じだろうか。日本名はクリームシチューの壺焼き。小振りな縦長の壺がパイ皮で蓋をされ、丸くふくらんでテーブルに出てくる。こんがりと狐色に焼けたパイ皮の中央に小ぶりのスプーンを突き立てて穴をあけると、オーブンから出されたばかりの壺の中央から、熱々の白い湯気と濃厚なバターの薫りが立ち上る。中央部のパイを指でむしり、中をのぞく。スプーンを入れて、小さな壺の半分ほどまでしか入っていないクリームシチューをすくって一口食べる。このときの幸せは筆舌に尽くしがたい。少しずつパイをむしりながら、シチューと交互に食べて行く。量が少ないので食べ終わってもすこし物足りない気がするが、味が濃厚なせいか腹持ちはいい。 私がグリヴィを最初に食べたのは子供のころで、大人になって同じ物が食べたくて家のオーブンで作ったこともあるが、味は再現できなかった。いや、味はかなりのところまで再現できたと思うが、店で食べたときのあの幸せな気持ちとはだいぶ隔たりがあった。なぜかを考えてみると、あの壺のサイズに秘密があるような気がする。私は家にあった小さめの茶碗蒸しの器で作ったのだが、厚みのある小ぶりの壺で作ってこそパイ皮は丸くきれいにふくらむし、最初に穴をあけてのぞく楽しみもあの味も、あのサイズでこそ再生できるのだろう。最近はパイシチューという名で似たような物がデパートで売っているし、ケンタッキーフライドチキンでもクリームシチューとビーフシチューの中身にパイを被せたものを食べることができる。でも、それはグリヴィとは違う物だ。 グリヴイがそれほど美味しく記憶に残っているのは、家族で食べた幸福な思い出に結びついているからかもしれない。変わった食べ物が目の前に出てくる喜び、穴を開けて中をのぞく楽しみの横には、両親の笑顔があったはずだから。私たちはこうした幸福な食べ物の記憶をどれくらい持っているものなのだろうか。 (2003年12月12日) |
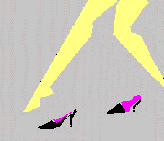 |
寒くなっても、東京の街には美しいピンヒールの靴を履いた女性たちがいる。「あんなヒールでよく歩けるね。かくっとなったら、即ねんざだ」と今の私は思うが、20代の頃なら一度は履いただろうと思うので、文句をいうつもりはない。すくっと立つ尖ったヒールには女の気合いが感じられて、どちらかというと「がんばってね」という気持ちになる。 しかし、そのピンヒールが曲がっているのはいただけない。まっすぐに立てて歩く力がなく、外側や内側に曲がった細いヒール。よちよち歩きのねじれた脚。新宿の雑踏を歩きながら、若い女性達の後ろ姿を眺め、色とりどりのコートの下のきれいな脚、そして靴へと視線が下りて行った先のピンヒールが傾いていると、悲しい気分になる。そんな歩き方しかできないのなら、ピンヒールは履いちゃいけないと思う。 もう一ついただけないのが引きずるミュールだ。最近は冬用のミュールがたくさんある。デザイン重視のせいか足先が浅いものも多いが、これをきれいに履きこなすには技がいる。へたをするとぺたぺたと音がするし、すぐに脱げそうになる。そこでずるずると引きずることになるが、その姿はかっこ悪くてミュールがかわいそうと思ってしまう。 ピンヒールもミュールも、きれいに履くとステキだけれど、だめに履くとだらしなさばかりが目立ってしまう。きれいな姿勢で優雅に歩けないのなら、そういう靴を履くのはあきらめようよ。 (2003年12月5日) |
 |
「最近、このへんにやたらに牛がいるんだよ」 道を歩いていると、歌舞伎の助六の格好をした牛、全身を唐草模様の風呂敷柄に塗られ、黄色い目がユーモラスな牛、翼を付けた空飛ぶ牛、さわやかな自然の風景を全身に映す牛、背中にピエロのような女性を乗せた牛など、様々な牛が次々に姿を現す。 これは「カウパレード」と呼ばれるパブリックアートのイベントで、日本のアーティストたちが、それぞれに腕を振るってペイントしたものらしい。第1回は1998年にスイスのチューリッヒで開催され、1999年シカゴ、2000年ニューヨーク、2001年カンザスシティ、ヒューストン、2002年ロンドンなどと続き、今年はニュージーランドのオークランドに続いて東京にやって来た。江戸開府400年と丸ビル1周年のイベントとして、「東京の中心地・丸の内に60頭以上の牛が出現!」というわけだ。 牛の形は画一的なので、芸術性を前面に出したアートというよりも楽しいお祭りという雰囲気だが、のそっとした牛が突然ビジネス街のあちこちに置かれた風景は、ちょっと不思議で、心をわくわくさせるものがある。 インターネットで「カウマップ」を手に入れたので、天気の良い日に牛見物に出かけ、気に入った牛は「カウギャラリー」でチェックした。牛たちは、約1か月の展示終了後にオークションにかけられ、収益は慈善団体に寄付されるという。 宣伝不足のせいか、周りでも知らない人が多いのがもったいないと思ったが、カウパレードは私を十分に楽しませてくれた。丸ビル隆盛の仕掛け人が次はどんなイベントを見せてくれるか楽しみだ。 (2003年10月5日) |
|
有楽町東京フォーラム前。全体に丸みを帯びた小型のシャトルバスが、新しくできたバス停の前に止まる。入り口の前扉は丸みを帯びた輪郭で、扉の開き方も都バスとは違う。運転席正面の窓も横の窓も広く、一番前の席に座れば、丸ビル、大手町のビル街、日比谷通り沿いのお堀端の緑が次々と目の前を通り過ぎて行く。 景色もいいし、すわり心地もいいが、なんといっても一番いいのは、車内が静かなことだ。モーター音もぶるぶるという揺れもない。このバスは電気で動いているのだ。乗ってみて初めて、静かな車内の心地よさを実感できた。そのうえ、排気ガスを出さないなんて、すばらしい。 銀座の会社から大手町の仕事先を訪ねる時に利用しているこのバスは、8月から運行を始めた無料のシャトルバズで、有楽町、丸の内、大手町エリアを約30分かけて巡回する。費用はこのエリアの企業数社が負担、観光客だけでなく、近隣のビジネスマンにもなかなかの人気だ。2台のバスはデンマーク製。環境問題を考え、電気自動車を採用したのだという。 丸ビルができて1周年を契機に、東京の中心で動きだした電気自動車。単なる観光名所の客寄せではなく、これからの時代を見据えた提案の一つとして、電気自動車が定着することを願っている。路上から、うるさいモーター音と排気ガスがなくなれば、それだけで都市の顔つきが変わるではないか。 (2003年10月1日) |
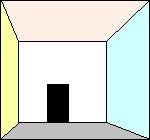 |
「キューブ」という映画を見た。カナダの女性監督が撮った映画で、正立方体の部屋が連結した巨大ビルに閉じこめられた6人の男女が出口を求めて部屋から部屋へとさまよう物語だ。各部屋にはドアがいくつかあり、隣接する部屋にもいろいろな仕掛けがある。その仕掛けを見抜けずにうっかり次の部屋に移ると、剣が飛んで来たりして死んでしまう。映画全体が、死の恐怖におびえながら安全な部屋を探して移動し、出口をみつける迷路ゲームであり、部屋の仕掛けを見抜き、対処法を考えながら次の安全な部屋に移るサバイバルゲームでもある。気持ちの悪い映像は少ないが、死への恐怖、密室の恐怖、出口なしの迷路の恐怖、なぜ自分たちがここに連れてこられたのかわからない不安感、協力したり反発したりする男女のエゴの怖さなど、人間心理をうまくついたホラー映画だ。 さて、この映画で私が感心したのが、皆の筋力だ。ひ弱な男も若い女も、華奢に見える中年の女性さえ、壁の梯子をよじ登り、天井にある扉に手をかけ、自分の体を自分の腕で引き上げる。床に電流の走る部屋は、天井に並ぶ鉄棒を運梯を渡るように伝って次の部屋へと移って行く。映画の構成上、皆がある程度生き延びてくれないと困るのは重々承知だが、この映画を見ながら「私ならすぐに先に進めなくなる、ああ、これもできない、あれもできない」と自分自身を情けなく思っていた。 ふだんやっている仕事に限っていれば、私は自分の体力にも精神力にも自信がある。どちらかといえば、集中力、持続力、自分を平静に保つ力など、自己コントロールに自信があり、それが続く間は体力も続くと思っている。 ところが、重い荷物を持つ、重い扉を押す(これでよく背中を痛める)など、単純な筋力となると全く自信がない。この部分は、人に頼む、サービスを買うという手段でしのいできたが、筋トレをして筋力をつけたら、新しい楽しみが広がるかもしれない。もっとも、それをサバイバルには使いたくないが。 (2003年9月23日) |
|
私のコラムを読んでくれた友人が「タイトルの付け方がうまい」とほめてくれた。これは、ちょっと意外だった。というのも、私自身は、「シンプルでおもしろみのないタイトルだけど、これにしよう」と思って、すなおにつけることが多いからだ。 コピーライターという仕事柄、大勢の消費者に受けるフレーズ、凝ったフレーズを作ってくれと要求されることも多いし、仕事ではそうした要望に最大限応えるように努力しているが、私自身は、シンプルで美しく、人の心の奥に響くようなフレーズが好きだ。あざといフレーズ、過激な言葉を並べたフレーズのほうが、パッと見たときのインパクトはあるにしても、よく考えられたシンプルなフレーズには、より強く人の心に残るパワーがあると思っている。 本のタイトルにしても、たとえば『バカの壁』は嫌いだ。バカという強い言葉は、見た人の心に強く残るし、内容をよく表現しているとは思う。本のタイトルとしては大成功なのだろうけれど、本屋で「バカ」「バカ」「バカ」と並ぶ本を見るときの、心がささくれ立つ感覚が嫌だ。「少なくとも相手に面と向かってバカと言ってはいけない」という礼儀が、売らんかなのために踏みにじられているような気がする。「ちゃんとした本なんだから、こんなタイトルをわざわざつけなくてもいいのに」と思う。この本の成功に便乗して、バカのついた本のタイトルや雑誌の見出しをあちこちで見るのも嫌な気分だ。 ホームページを始めたばかりの頃、来訪者を増やすためには表紙のタイトルもコラムの題も工夫したほうがいいというアドバイスをもらった。具体的に言えば、女性が書いていることをわからせる、内容にそぐわなくてもエッチぽいタイトルをつける、などだ。メルマガのタイトルと購読者数を見て、このアドバイスは正しいと思ったし、大勢の人に読みにきてほしいとも思ったが、私自身はこのアドバイスに従わなかった。こうした風潮に対する反発もあったし、好き勝手に自分の思いを書くコラムなのだから、タイトルもぱっと頭に浮かんだものを付けよう、と単純に考えた。 こうして書き続けて並んだコラムのタイトルを見て、芸がないと思うこともあるが、シンプルでよしと思うこともある。そんな気持ちで付けたタイトルをほめてもらえると、心の通う読者をみつけたようでうれしい。 (2003年9月22日) |
|
毎日、銀座の会社に通う道筋で、駅貼りのポスターを眺める。少し前の私の注目作は、サントリーのグレープフルーツ飲料「ゴクリ」の巨大ポスターだった。 そもそも「ゴクリ」の容器はあざやかな群青色のアルミペットボトルで、ボトルの中央にグレープフルーツの黄色が目立つように配置されている。グレープフルーツのつぶつぶが味わえるようにと、飲み口の直径は普通のペットボトルより大きい。 ポスターは、地色がその美しい群青色で、横たわる巨大な「ゴクリ」に体をもたせかけ、同じく群青色のボティースーツを着た白人の美女が「ゴクリ」をごくりと飲んでいる。コピーはMichi tono so good! これは「道との遭遇」のダジャレで、あまり好きではないが、色と構図の美しさで目を引く作品だった。 最近、これに続く連作の巨大ポスターが張ってある。一枚は、横たわる「ゴクリ」の大きめの飲み口に、白地に赤の模様のはいった金魚が大きな口を開けて吸いついている。もう一枚は、金魚に代わって緑色の雨蛙が大きな口を開けて吸いついている。両方とも、とてもきれいなポスターだ。「ゴクリ」の群青色に金魚の陶器のような艶のある白と鮮やかな赤、同じ群青色に雨蛙の濃い黄緑。色のコントラストが美しく、大口の金魚と蛙の写真も目を引く。 でも、この2枚のポスターを見たときの私の第一印象は、生臭さだった。金魚や蛙とキスするときの冷たく生臭い感触が連想して、「ゴクリ」が全然おいしく感じられない。他の女性はどう思うのだろう? アイデアを出したのは男の人? 色の美しさからはいったデザイナー? などと考えながらポスターの前を通り、きれいだとは思うが商品には手が伸びない。他の人がどう感じているか、感想を聞いてみたい。 (2003年9月22日)・金魚とゴクリはここで見られます。 |
|
フランスで行われている世界陸上を見ていると、筋肉は美しいと思う。長距離、走り高跳び、棒高跳びなどの伸びやかな筋肉だけでなく、ハンマー投げや砲丸投げの「これでもか」というような筋肉の盛り上がりを見ていても、あんな体を持つのは快感だろうなと思う。スポーツとは縁のない私でさえそう思うのだから、若い男の子たちはきちんと筋肉のついた頑丈な体に憧れるのではないかと思うのだが、実際に電車のなかの男の子たちを眺めていても、ひ弱か太りすぎが多く、きちんと運動して食事をしていると思えるのは10人に1人くらいだ。 きちんとした筋肉を持つにはコーラを飲んで松屋の牛丼、みたいな食事ばかりじゃだめだし、毎日なにがしかの運動をしなくちゃならないし、自分の生活全般を自分で 管理する能力がいるけれど、だからこそ、もう少しきちんとした体に憧れて、そういう体を作ろうと努力してもいいのではないか? きのう(8月30日)は、渋谷のオーチャードホールで、ローラン・プティ振付の「デ ューク・エリントン・バレエ」を見てきた。デューク・エリントンのジャズの名曲に乗せて踊るダンサーやバレリーナたちの筋肉も美しかった。 女の子たちのやせ願望は今に始まったことではないが、職場のある銀座ですれちが う若い女の子たちをみていると、男の子たちはこんなやせっぽちを魅力的に思うのだ ろうか、と考えてしまう。ダイエットに向ける情熱を筋肉に向けたら、もっと美しい 体になるのではないだろうか? と、ここまで書いて我が身を振り返ると、私は子供の頃から運動が苦手で汗をかくのが嫌いだった。今になってやっと筋肉の美しさに目覚めたのだから、まず自分から始めてみようか。ちょっと本気でそんなことを考えている。 (2003年8月31日) |
|
8月から金融関係の連載記事広告を書いている。不景気、低金利、将来の年金不安などから、資産運用に対する関心が高まり、個人のお金を取り込むべく、様々な金融商品が出ている。そうした金融商品をわかりやすく説明するページなのだが、原稿を書く課程で、銀行の人たちの説明を聞いたり、ファイナンシャルプランナーに会ったり、金融セミナーに参加したりしていると、お金に対する温度はほんとうに人それぞ れ、千差万別なのを実感する。 私はフリーランスが長く収入の不安定な生活をしてきたし、友人にもまともな勤め人が少なかったので、お金と言えばその日暮らしを支える物。預貯金をどう増やすかなどと考えられる状況ではなかったのだが、安定した暮らしのサラリーマンは、子供の教育、住宅取得、老後の備えを十分以上に考えているし、金融関係者は「お金を増 やす手段があるのにそれに関心を示さないなんて信じられない」と思うようだ。 私自身は「お金が人間の醜い面をあらわにする」という局面を見たり聞いたりすることが多かったで、なるべくお金にわずらわされずに生きていきたいと思っているが、仕事のための基礎知識を得るためにいろいろ本を読みあさった。その結果思ったのは、「お金に関心があっても、正確な知識がある人は意外に少ないのではないか」ということだ。他の商品の場合、いいところの話だけ聞いても、私たちは自分で短所をみつけることができるが、金融商品の場合は短所に頭が回らないことが多い。よく考えればわかる短所も、見過ごしてしまう。 なぜだろうか。預貯金以外の金融商品に慣れていないせいか、相手のほうが専門家だからと売り込む相手に任せてしまうのだろうか。こうした状況を見ると「知識は力」を実感する。相手の説明を正しく汲み取り、自分の考え方にあったお金の貯め方を選ぶためには、個人個人が知識を持つことが必要なのだ。そうした力を得るために、しばらく本腰で知識を仕入れようと思っている。 (2003年8月31日) |
 |
8月の深夜はツール・ド・フランスをよく見ていた。ツール・ド・フランスは、約3週間でフランスを一周する世界最大の自転車レースで、うちではケーブルテレビで見ることができる。スタートからゴールまで毎日3時間以上、延々と放送があるのだが、私が見ていたのはゴール前の1時間から30分ほど。このくらいの時間帯になると、マラソンと同じで1位になるための駆け引きがいろいろあって面白いのだ。 なじみのないレースなのでチーム名や選手名もほとんど知らないのだが、フランス 語の聞き取り練習もかねて意味の取れないフランス語放送を流し、毎日レースを眺めていた。レースの楽しみと同時に私を楽しませてくれていたのが、選手のウェアとヘルメットだ。選手はそれぞれにチームジャージを着ているのだが、色はハデで特長があるし、広告ロゴがたくさんついていて独特の味がある。同じチームジャージの7、8人が縦列に並んで走る様子もきれいだ。ヘルメットは、スピードレースの日は大き く後ろへ流れるようなドロップ型の堅いヘルメット、それ以外の日はなだらかな流線形のヘルメット、山岳レースなどではヘルメットを脱いでしまうときもある。ヘルメットと一緒に見ることのできるサングラスもしゃれたデザインだ。 滑ると言うよりは飛ぶように走る自転車にも魅了されるが、機能を追求しながら同 時にファッショナブルなスポーツの装いも魅力的だ。子供を後ろに乗せる必要がなくなったので最近はほとんど自転車に乗らなくなったが、ツールを見た後では「自転車 でツーリング」もいいかもしれないと思う。できれば、あんなヘルメットを被りたいが、そのためにはそれが似合う肉体がいる。肉体が機能的でなくては、それに見合った機能美が楽しめないところが、スポーツの装いのつらいところだろう。 (2003年8月29日) |
|
最近、マッサージのかわりに鍼を打っている。そもそもはマッサージをやってもら っている担当者に「凝りがひどいから鍼を試してみては?」と言われたのがきっかけ だ。最初はちょっとこわいと思ったが、やってもらったあとの眠りの深さが違うので、なんとなく効いているような気がして続けている。 数回やっているうちに、肩凝りは緩和した気がする。私は腰が痛いと思ったことは ほとんどないのだが、鍼師は「腰が堅いから、腰に打ちましょう」と言い、最近は腰にも打っている。しかし、腰が軽くなったという自覚はまだない。ただ、腰に打つよ うになってから、足首がすこし柔らかくなった。私は毎週1回ヨガに通っていて準備運動で足首回しをやるのだが、その回り具合が違うのだ。こんな風に自分の体の関連具合を知るというのも、なかなかおもしろい。 少し効果が現れて、針治療に興味を持った。その後、インターネットで調べたり整体の本を読んだりしたが、鍼を打つ場所は鍼灸師が手探りで決めるようで、効果が出 るかどうかは鍼灸師の腕次第という要素が大きいようだ。と言うことは、偶然鍼を打つ気になり、気に入った鍼灸師がいるということは幸運なことなのだろう。しばらくはこのまま続けて、自分の体がどう変わるか見てみようと思っている。 (2003年7月30日) |
|
先月のコラムで「頭の中がフル回転感覚」について書いたが、この感覚にはどこかで覚えがあった。よく考えて見ると、それはある種のパズルをやっている時も体験できるのだった。ある種の、と書いたのは、パズルにも得手不得手があって、不得手なパズルに当たると、私の頭はまったく回転しなくなる。 苦手なパズルは3次元で考えるもの。昔流行したルービックキューブなどは全然できるようにならなかったし、サイコロが積んである絵を見てその数を推理する、なんていうゲームも苦手だ。好きなのはクロスワードパズルと数独(ナンバープレイス)と呼ばれる数字の推理パズル。こういうのをやっているときの頭の中の動きは、フランス語をなんとかひねりだそうとしているときの頭の動きと似ている。持っている知識やカンを総動員している感覚といったらいいだろうか。人と比べて特別に解くのが早いとか得意というわけではないが、没頭する感覚が心地よい。 その感覚を思い出して、久しぶりに本屋で「数独」のパズル集を買った。「簡単」と分類されているものでも解くのにけっこう時間がかかるが、計算などは必要ない推理パズルなので、じっと数字をにらんでいる時間がなかなか楽しい。ただ、これをやっていると30分があっという間に過ぎてしまうのがちょっとくやしいが。 (2003年7月3日)数独って何?という人は、こちらを見てね。 |
会社の帰り、夕食の食材を買いに銀座や新宿のデパートに寄る。地下1階には1つ500円もする美しいケーキや季節感あふれる高級和菓子、ベルギーなどから空輸してきたという1粒200円もするチョコレートが所狭しと並んでいる。私はきれいなものを見るのが好きなので、各店舗が競うように並べるケーキや和菓子のデザインや、食べる宝石といった風情でディスプレイされる高級チョコレートを見るのは楽しいし、「デパ地下スウィーツ」などと銘打った雑誌の特集を眺めるのも好きだ。 だが、しかし、待てよと思う。こうした華やかな菓子類が店に並ぶ一方で、若い女性達はやせすぎて貧弱と思えるような体を求めてダイエットに走り、玄米ごはん、全粒粉パン、やせる水、ダイエットスープなどがもてはやされているのだ。 デパートの地下で高級菓子を買うのもダイエットに懸命になるのも、同じ若い女性たちなのだろうか。それとも、若い頃にはダイエットに燃え、結婚し子育ても終えた裕福な女性達が高級菓子を買うようになるのだろうか。私の目には、どちらも極端、過剰に映る。不況と言われていても豊かな日本にいる私たちにとって、いちばん難しいのは自分の適量を知ることかもしれない。 (2003年7月2日) |
首の凝りがひどいので、マッサージと並行して最近鍼を打ってもらっています。こう書くと年寄りっぽいですが、マッサージも鍼も最近は若い女性に人気なのだそうです。鍼師のおじさん曰く、「男は恐がりだから鍼を打つ人は少ないけど、女性は多いですよ」とのこと。私もけっこう恐がりなのですが、信頼できるマッサージ師に薦められたのと、新しいことを試して見たいという好奇心にかられて、やってもらうことにしました。 最初の鍼は約15分。首と背中に刺すので自分では見えないし、刺すときの痛みもほとんどなく、なかなか気持ちのいい時間でした。それから数回、30分コースをやってもらっていますが、速効性のあるマッサージと違って、じわーっとゆっくり効いているような気がします。そもそも、中国4千年の歴史のあるツボ(経絡)治療と聞くと、それだけで効果があるような気がするし……。こういう思いこみ効果もプラスアルファに働きそうです。 私はだいたいガマンが嫌いなので、西洋医学の対処療法や薬の即効性も棄てがたいと思うのですが、最近の医療事故や研修医の過労働のニュースを聞き、父の入院で見た医者気質などを考えると、とりあえず「間違いがあっても取り返しがききそうな東洋医学を試してから」という気になりますね。ほんとうは体を動かすことで凝りをほぐすほうがいいのでしょうか、しばらくは鍼を続けてみて様子を見ようと思っています。 (2003年7月2日) |
 |
来年はパリに行く、と決めて5月からフランス語会話を始めた。毎週1回、生徒3人のグループレッスンで、テーマだけ決めて、あとは自由に話し合う。私は大学で仏文を専攻し、本はそこそこ読んで来たし翻訳もしているが、これまで会話のチャンスはほとんどなかった。レッスンの前にテーマごとに使いそうな単語をインプットして行くのだが、興が乗るにしたがって話は思わぬ方向に飛び、その場その場で言葉をひねり出さなくてはいけなくなる。 言いたいことは自然に頭に浮かぶが、それからが大変だ。必要な単語を思い出し、構文と時制を考え、文法をチェック。女性名詞か男性名詞かを考え、動詞に合った助動詞を探してからしゃべり出す。その間4〜5秒、クラスは沈黙に包まれる。おしゃべりなフランス人たちは会話の途中の沈黙を嫌うというが、フレデリックはフランス人ながら教師なので、私をじっとみつめたまま、言葉が出てくるのを辛抱強く待っている。 この4〜5秒はとても長く感じられる。この時間が短くなればなるほど会話が上達したといえるのだろうが、実は今、私はこの時間をけっこう楽しんでいる。この数秒の間、私の脳がフル回転している様子が感じられるのだ。ふだんこんなふうに、一行の言葉が出てくるまでを意識したことがないので、「おお、脳が働いている!」という感覚がなかなか面白い。まあ、こういうことを楽しまないと、できの悪い自分にいらいらしてフラストレーションがたまるという事実もあるのだが、しばらくはこのフル回転感覚を味わってみようと思っている。 (2003年6月1日) |
昨日の5月31日、上野鈴本で開かれた柳家小三治独演会に行って来た。演題は仲入り前が「かぼちゃや」、トリが「藪入り」だった。 私が小三治の落語に最初に触れたのはもう20年以上前になる。ホール落語に通い、PR誌の仕事を利用してインタビューしたこともあり、志ん朝・小三治と並び称されるようになったときも、ずっと小三治ファンだった。与太郎もののとぼけぶりや、「初天神」のような子供の出てくるものに絶妙の味があり、毎回笑って泣いて、話の妙を堪能してきた。 子供が出来たり、仕事が忙しくなったりで、しばらく落語から遠ざかっている間に小三治の評判はますます高まり、最近は独演会のチケットなどは即日完売らしい。そんな中、チケットを手配してくれる人があって、前から4列目という席で、久方ぶりに小三治の話を聞いた。「かぼちゃや」のよたろうはとぼけぶりに磨きがかかり、すばらしかった。へんに騒々しくなく、淡々としていて味がある。 同じ話をしても落語家ごとに味わいが違い、同じ落語家の話でも毎回趣が違うのが落語の楽しみと言えるだろう。語られた話には、常に落語家その人が反映されている。そう思いながらきのうの話を思い返すと、小三治は見事に歳を取ったと思う。歳を重ねたことで落語は微妙に変化し、その変化がとても美しかった。5年後、10年後の変化も楽しみだ。こんなふうに自分を投影させながら自分一人で完結し、また新たな精進のできる仕事はほんとうに楽しいだろうなと思う。小三治師匠には、大いに自分を楽しみ、私たち観客を楽しませてくれるようにエールを送りたい。 (2003年6月1日) |
息子が生まれた年に、父の行きつけのバー「ナルシス」のマダムから五月人形をもらった。子供が生まれた時、男の子だから強く、女の子だから優しく育ってほしいとは思わなかった。男でも女でも、人間として自分らしく生きる強さと他人を愛するやさしさを持つ人になってほしいと願った。青年時代からの父を知るマダムは、そんな私の思いも想像してか、鎧兜や武者人形ではなく元服前の男の子の人形を贈ってくれた。宗教を持たない私は、息子のためにお宮参りも七五三の参拝もしなかったが、この人形だけは毎年子供の日の前に押入から出して玄関横に飾っている。 父にとって、新宿のバー「ナルシス」は酒を飲むときの「品」を教わった場所ではないかと思う。文人が多く集まるそのバーで、たくさんの上品な酒飲みと下品な酒飲みを眺め、マダムと会話を重ねながら、父は自分が良しとする酒の飲み方を決めたはずだ。その店に私や夫を連れて行き、私たちもマダムと話をするようになった。そんな経緯があって贈られた人形を毎年1回飾ることで、息子にもマダムの愛が伝わるような気がした。父の酒の飲み方を認め、その父の娘だから、娘婿だから、孫だからというだけでなにがしかの愛を注いでくれたマダムの気持ちに感謝して、5月5日にはこの人形を眺めて来た。 2年前に父が亡くなり、その後すぐに数歳年長のマダムも亡くなった。無事に育った息子は来年の3月で20歳になる。願わくば父が生きていて、マダムのいる「ナルシス」で息子と二人で酒を飲む機会があればよかったと思うが、その機会は失われてしまった。この人形を眺めながらマダムのことを考えると、尊敬する女性を失望させないような酒の飲み方を息子が身につけてくれればいいが、と思う。 (2003年5月5日) |

|
最近、クレマチスの花に魅せられている。とくに青紫の一重、大輪の花がいい。庭のフェンスや垣根につるを伸ばし、段状に咲くクレマチスの花姿は華やかながら独自の静けさがあり、とてもエレガントだ。日本名を鉄線(テッセン)というが、これは本来は白い花弁に紫色のおしべを持つもので、江戸時代にに茶花として愛されたらしい。茶花らしい渋みと華やかさを合わせ持つのがこの花の魅力かもしれない。 3年前、近くの花屋で苗を見つけ、苗に添えられていた大輪の花の写真に引かれて、自宅のベランダで花を咲かせたいと思った。そこで大鉢と鉢に差し込むタイプの小さなフェンスを買い、青紫色のH.F.ヤングとクリーム色の満州黄色の2種4株を寄せ植えにした。それだけでは鉢が寂しいので手前にアイビーを植え込んだ。以来毎年、青紫の大きな花が3輪、5輪咲いて私を楽しませてくれている。今年は今まで1輪も咲かなかったクリーム色の花が開花した。 こうなると、街を歩いていてもクレマチスが気になる。最近は小さくて華やかなピンクの花や白花で、「え、これもクレマチス?」と思うような変わった品種が花屋の店先に並んでいる。これからもベランダの花の世話はするのだし、「少し花の株を増やすのもいいか」と思ったのが運の尽き。どんどん欲しい品種が出てくる。先週は花が満開のミゼット・ブルーの鉢を見つけて購入。今週は木立性の白い小花アーリー・センセーションの小株を見つけて購入。あと1色、ピンクが欲しい。「こうなったら、クレマチス栽培を極めようか」などと思いつつ、ベランダの水やりを楽しんでいる。この情熱がいつまで続くかが問題だが。 (2003年5月1日) |
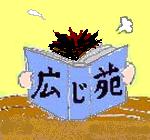 |
先日、小学館のポケットサライという新書のシリーズの1冊、「日本庭園の見方」という本を買った。中身は写真が多くて面白い本なのだが、副題の「歴史がわかる、腑に落ちる」の「腑に落ちる」が、どうにもひっかかる。 「腑に落ちない」はごく自然だが、「腑に落ちる」には違和感がある。自分の文中では決して使わないが、新書のタイトルに使われているということは、ふつうの言い方なのだろか? それとも、読者にざらっとした引っかかりを与えるための手法なのか? こういうときには私同様ことば好きの夫に、まず聞いてみる。 次にインターネットで調べてみる。検索エンジンのキーワードに「腑に落ちる」を入れて検索するとけっこう出てくる。ということは、ふつうの言い方なのかと思いながら、そのひとつに入ってみる。そこの解説によると「辞書の多くは否定形の形『落ちない』しか載せない。肯定の場合は『心に落ちる、胸に落ちる』を使う」のだそう。ただし、「腑に落ちる」もかなり使われているので、誤用と言えるかどうかわからないと書いてある。 やはり、「腑に落ちる」は少しヘンなんだ。「心や胸に落ちる」も私は使わない、使うとしたら「納得できる」だろうと私は納得した。ところが、その矢先、「エドワード・ゴーゴリーの世界」(河出書房新社)という本を読んでいたら、鼎談のなかで「すごく腑に落ちたんです」(濱中利信)「非常に腑に落ちました」(江國香織)という会話を見つけた(3人目のゴーゴリーの翻訳者・柴田元幸さんは使っていなかったが)。小学館や河出書房の編集者がOKしたということは、「腑に落ちる」の認知は進んでいるのだろう。 (2003年4月15日) |
マクドナルドのように手早く食べ物が出てくる店を新聞原稿に「ファーストフード店」と書くと、「ファストーード店」と直しが入る。なぜなら、これは、早いという意味のfastであって、第一のという意味のfirstではないので、誤解を避けるためだそうだ。 しかし、辞書を見ると、fastにはカタカナにすれば「ファスト、ファースト」の2種で書き表せそうな発音記号が載っている。インターネットのキーワード検索に「ファストフード」と入れると、「ファーストフード店」という項目がぞろぞろ出てくる。 英語をどうカタカナ表記するかは、新聞社や出版社などの独自の判断があって、それぞれ自社のスタイルブックを出しているし、その中身も時代に合わせて改定されている。たとえば私が主に広告原稿を書いている読売新聞の場合、数年前までは「コンピュータ」だったが、最近は「コンピューター」を使うという具合。雑誌の場合は、書き手の好みに任されることも多いが、昔使っていた「エンターテイメント」は「エンターテインメント」と「ン」がよけいに入ることが多くなったし、国名の「ギリシャ」も雑誌などでは「ギリシア」と書かれることが多い。というわけで、新しい雑誌に原稿を頼まれた時はカタカナ表記を統一するためにバックナンバーを繰ることになる。どこかで統一してくれればいいと思うが、古くさい頭の公の機関に統一されるのもありがたくない気がする。 (2003年4月15日) |
ガマの油売りの口上を最初に聞いたのはいつのことだろう。子供の頃、母と一緒に行った寺の縁日には、七味唐辛子や針の糸通しなどを売るおじさんや、一筆で縁起物の龍を描くお兄さんなどがいたが、ガマの油売りはいなかったと思う。 私は何を言っているのかよくわからない口上を聞きながらも、緩急自在、大声になったり、観客を笑わせたり、はらはらさせたりする口上や体の動きをじっとみつめる子供だった。紙芝居も大好きだったし、新宿の路上の果物店で繰り広げられるバナナのたたき売りも好きだった。 大人になってもこの性癖は変わらず、取材でソウルに行ったときには、飾り文字のアルファベットで名前を描いて観光客に売るおじさんの韓国語に聞き入り、銀座に夜毎に現れる人間マネキン(こちらは動かず、口も聞かないが)にも、じっと見入ってしまう。周りの人たちが、無関心に通り過ぎてしまえるのが不思議だ。こんな性癖だから、遊びや取材であちこち訪ねている途中のどこかでガマの油売りにも出会って、じーっと聞き入ったのだろう。 そして昨日、落語会仲間の花見の席で、久しぶりに「ガマの油売り」の口上を聞いた。講談師にして大道芸人という神田陽司さんが、余興に披露してくれたのだ。頭上に広がる桜の枝の下、黒紋付きの着物に袴、白はちまきに刀を差し、「手前、持ちいだしたるは四六のガマ。四六、五六はどこでわかる……」と流暢に始まった口上は、青空に向かってのびのびと枝を広げた桜の木に似合って、落語を聞くのとはまた違った趣があった。技を見せるジャグリングも楽しいが、「客の財布とひもをゆるめる」という難しいゴールを目指す口上には、人間心理をついた、より深い語りの面白さが隠れていると思う。 (2003年3月31日) |
 |
毎週月曜に新しい花の鉢を買う。会社の机の上、パソコンの横に置き、金曜に自宅に持ち帰ってベランダの大鉢に寄せ植えする。5日間日の当たらない机の上に置かれて、花が散ったり葉の勢いが弱っていくが、大鉢に植え替えてしばらくすると元気になって花を咲かせる株が多い。鉢の値段はコーヒー一杯程度と決め、月曜に小さな鉢を買うのが私の楽しみだった。 ところが、銀座という場所のせいか、ガーデニングブームが去ったせいか、私がいつも買っていた花屋が店じまいしてしまった。それと平行して、300円から500円の小さなブーケを売る店が目につくようになった。そこで花鉢の替わりのこのブーケを飾ることにした。 切り花は毎日水を替えないとすぐに弱るし、枯れた花を取り除いての活け直しがめんどうと思っていた。ところが、最近の切り花は特殊な液を水にいれておけば、そのままで一週間は持つという。私が買ったブーケも、月曜から金曜までほとんど変化なくその美しさを保った。アイビーやユーカリの葉、ワタの花やガーベラなど、日持ちのする葉や花を選んでいるせいもあるが、金曜まで花の様子はほとんど変わらない。 最初は「いつまでもきれいでいい」と思ったが、2週、3週とブーケを買い続けるうちにつまらなくなった。こんなに変化がないのでは、造花と同じではないか。切り花のよさは、蕾から花が開き、花が咲き切った後の熟れた感じや茶色く枯れていく様子など、花の移ろいゆく美を味わえるところにあるのだ。やはり切り花は、造花みたいなブーケではなく、大きな花束で花の移ろいゆく変化を楽しみたい。そう思ってからはまた、小さな鉢花を探して、私は銀座の街を歩いている。 (2003年2月3日) |

|
とくにライターになる勉強をしたわけでもなく、仕事をしながら自分の文章の書き方を作りあげて来たので、「文章の書き方」というような本を読んだことはない。子供の頃から文学書が好きで、たくさんの本を読んで来たのと、一時期、先輩のコピーライターたちが書いた作品集のようなものを読み漁った時期があり、そうした体験から、いい文章、好きな文章、自分が書きたい文章、広告の仕事で要求される文章、好きではないがうまいと思う文章などを、読み分けたり、書き分けたりしながら、月日を重ねてきた。 最近になって、「自分の書いた小説を批評してくれ」と言われる機会があった。その小説を読んで、「なんかピンと来ない」「読みにくい」「神経に引っかかる」と思うのだが、自分のこの気持ちの原因が何だかはっきりとわからない。もう少しこうしたら、と思うこともあるのだが、その部分をどういうふうに指摘すると、的確に相手に伝わるかもよくわかならい。 考えてみれば、私は人に文章の書き方を教えたことはほとんどない。「ライターになりたい」という人には、たくさん読めとか、たくさん書いているうちにうまくなるとか、そんなアドバイスしかして来なかった。そこで今回はちょっと視点を変えてみようと、文章の書き方とか、入試のための小論文の書き方などの本を読んでみたが、それぞれに説明がわかりやすく書かれていて面白かった。実際に書くのと、書き方を教えるのには別のアプローチが有効なのもなんとなくわかった。プロになるのはほんの一握りなのだから、普通の人が、前よりも少しだけ明確に自分の言いたいことが語れるようになれば、こういう本の目的は達成されたと言えるだろう。 ここで自分なりの「文章の書き方」をまとめてみるのもおもしろいかもしれない。自分が何を望んでいるのかよく分からずに仕事を発注する得意先を相手にしていると、この試みがうまくいけば、もうすこし仕事がスムーズになるのではないかとも思うし……。 (2003年2月1日) |
今年は生の落語を聞こうと思っている。去年は「生の芝居」をたくさん見ようと決めて、月に1度の割合で劇場に通ったのだが、好きな劇団が見つけられなかった。私は舞台という制約の中で心を揺さぶられる芝居が見たかったのだが、最近の芝居はお笑いに走ったり、スクリーンと融合させたりで、「劇的感興」が薄まっている気がする。私の好みが今の劇に合わないのかもしれないが、まあ仕方がない。 「今年は落語を聞こう」と思ったのにはわけがある。落語好きが集まる忘年会で新作落語を聞いた。全然おもしろくない話だったのだが、それでも目の前の生の声を聞いているうちに、「ああ、いいなあ」と思った。「これで、好きな演者好きな落語を聞いたら、さぞかしいい気分だろう」と思ったのだ。というわけで、本日昼間に柳家小三治独演会のチケットを買いに行ったのだが、前売り初日というのにS席は売り切れだった。小三治さんはずいぶん昔、よく聞きに行った落語家なのだが、年を重ね、ますます人気者になって、うれしい限りだ。しかし、こんなにあっという間にチケットがなくなるとは思わなかった。こうなったら、とりあえず寄席に行ってひいきにできそうな若手落語家をみつけて楽しもうと思う。 (2003年1月11日) |
パン屋が好きだ。焼きたてのパンの匂い、店一面に並べられたさまざまな形のパン……。パン屋でパンを選んでいると、「ああ、日本は豊かだ」と思う。デパートやブティックに並ぶ美しい服や宝石を眺めるよりも、パンを眺めるほうが豊かさが感じられるのはなぜ だろうか。「食べる」という、人間の身近な欲に働きかけるからだろうか。 そして、私は今、好きなパンを選んでトレイに乗せることができる。欲しいパンを好きなだけ買えるというのもなかなかぜいたくな状況だと思う。パンを作る材料があり、毎日パンを焼いて売る人がいる。焼きたてのパンがたくさん並ぶ店があり、そこで毎日パンを買う人びとがいる。あたりまえのようだが、これができない国や地 方があることを考えると、焼きたてのパンの匂いに満ちた空間にいることのありがたさをしみじみと感じる。 子供の頃、店をやるなら「パン屋」をやりたいと思ったが、その 思いは今も変わらない。パンのように人が毎日必要とするもので、人の心を豊かにできるものを売りたい、そんな文章を書いていけたらうれしいと思っている。 (2003年1月2日) |