
バックナンバー2003年の「ちょっと言わせて」を読む
バックナンバー2001年以前の「ちょっと言わせて」を読む
「ちょっと言わせて」目次へ戻る
|
3か月毎に通勤定期を買っている。先日も、また新しい定期を買った。駅の窓口で渡された定期には「15.3-8」の大きな文字が印字されている。毎回のことだが、この3か月先の日付を見るたびに私は一瞬はっとする。あと3か月、私は会社に通い続けるだろうか、生きているだろうか、という考えが頭をよぎる。 「いつ死んでもいいと思っている」と友人や知人に言うと、みなちょっとぎょっとしたような顔をする。正確に言えば「いいと思っている」というよりは「仕方がないと思っている」というほうが近いが、子供の頃からずっと「人間はいつ死ぬかわからない」と思ってきた。幼児期に死を身近に感じる体験があったわけではないが、祖母は自分の戦争体験や戦中戦後のつらい時期に夫や息子を亡くした話を繰り返し話してくれたし、小説家だった父は自分の戦場での体験と死をみつめた小説を書き、私は中学時代から父の作品を読んでいたので、少なからずその影響があったのだと思う。高校時代に実存主義の小説に興味を持ったのも、私の根底にあるこうした考え方にぴったり来るものを感じたからだろう。「いつ死ぬかわからないから、毎日を一生懸命生きよう」と考える人もいるのだろうが、高校生の私はそう考えるようにはならなかった。 「いつ死ぬかわからないから、やりたいこと、楽しいことから先にやろう」と考え、「死は理不尽なものなので、来たら来たで仕方がない」という妙な諦観を持って生きるようになった。今になって考えると、「開き直って、快に走る」という生意気な若者だったと思うが、そう思いながら生きてきて、悪いこともなかった。3か月後の日付を見て、その日まで生きている保証はないと一瞬でも思うと、やりたいことから優先順位をつけてやるようになる。楽しいことばかりを選んでやってきたわけではないが、やりたいことをやって今日まで生きのびてきたと思えるのは、こうした思いを持ち続けたおかげのような気がする。 (2002年12月22日) |
|
手帳を使い初めて20年以上になる。ずっと、同じものを使っていたが、昨年から気分を新たにこれまでとは違う手帳を使い始めた。深みのある赤い表紙で、左面に月曜から始まる1週間の予定が書き込めるようになっている。右面はメモページだ。私はこの手帳に家族すべての予定を書き込み、取材先や待ち合わせ場所の住所・電話、HPやメールアドレス、振り込み先など、必要事項をメモし、ともかくこの手帳さえあれば必要事項はすべてわかるようにして1年を送っている。そこで毎年暮れになると、住所録や新しい手帳に、必要事項を書き写す作業をすることになる。その都度書き写せばいいのだが、すぐに忘れるし、どれとどれを書き写したかも判然としなくなるので、正月休みにこの作業をまとめてやるほうが効率的なのだ。 先月、来年用にと同じ体裁で鮮やかなブルーの手帳を買った。大掃除をし、お節料理を作り、そして大晦日にこの手帳への書き写し作業をすることになるだろう。とくに新年への期待があるわけではないが、年の終わりに、今年もまた1年生きのびてきたなあと、しみじみ感じるのもいいことではないかと思う。 (2002年12月8日)> |
|
高校を卒業した息子が、「1年間ロサンゼルスで英語を勉強してくる」と言って旅立ってからそろそろ8カ月になる。息子の話を友人や知人、会社の同僚にすると、いろいろな反応がある。「いいですね、ぼくも勉強に行きたいな」「楽しそうですね」「でも、寂しいでしょう」「親は大変ですね」などなど。 えっ、帰って来ないよぉ。アメリカは遠いよぉ。飛行機代は高いし、たかだか1年で帰って来る予定なのに、その途中で帰って来たりしないよぉ。 私はいつもそう話すのだが、20代、30代の相手はあまり納得しない。私は東京生まれで、盆暮れに田舎に帰る経験がないのだが、帰省の習慣がある彼らにしてみれば、「盆暮れに親元に帰る」ことはごく自然なのかもしれない。たとえば、九州や北海道に帰ることを考えれば、冬のロサンゼルス-日本往復格安運賃のほうが安いくらいなので、飛行機代もそれほど障害にはならないのだろう。あとは距離感だ。1ドル360円の時代を知り、「アメリカはめったに行けない遠い国」というイメージのある私と違って、海外旅行経験の多い彼らにとって、アメリカは身近な国なのだろう。 「一回も帰って来ないんですか?」と質問されるたびに、私は彼らとの年齢差や考え方の差を感じる。世界が身近なことはいいことだ。故郷の親に顔を見せてやろうという心がけもえらいと思う。でも、初めて親から離れて言葉がほとんど通じない国で暮す決意をした息子にとって、日本は1年間は帰れない国であるほうがいい。そして、今、「毎日が楽しくて、正月に帰るなんて思いもよらない」という気持ちでいてくれれば、私はうれしいのだが。 (2002年12月14日) |
 |
ファッションのなかで、一番最初に凝り始めたのが帽子だ。中2の冬、父の友人がクリスマスプレゼントに帽子を買ってくれた。私が欲しいと言ったのか、彼が帽子をと言ったのか覚えていないが、若い編集者だった彼は私をデパートに連れて行き、黒のスエードのベレー帽を選んでくれた。売り場の年配の女性が上手なかぶり方を教えてくれ、その日1日帽子を被っていい気分だった私は、それ以来自分で帽子を買うようになった。2番目に手に入れたのはグリーンの毛糸のベレー帽で、高校時代にはカラス族といわれた黒づくめのファッションの差し色として被っていた。その後、映画でアヌーク・エーメのつば広のフェルト帽を見て憧れ、大きな帽子を被るようになった。以来ずっと帽子ファッションを楽しんできたが、30歳で子供が生まれてからはあまり帽子を被らなくなった。ところが、最近また帽子への情熱がよみがえってきている。 帽子を被ると独特の高揚感がある。年齢を重ね、自分の生活を自分でコントロールできるようになって、緊張感のない生活を送ろうと思えばできる今、帽子を被る楽しみを思い出してよかったと思う。私はファッションは生き方の表現だと思うので、背筋を伸ばしてしゃんと歩こうと思わせてくれる帽子を被ろうと考えながら、時折帽子売り場をチェックしている。 2002年11月7日) |

|
昨晩、ヨガをやってきた。週1回、1回2時間近く。体を伸ばし、呼吸を整え、しばし瞑想。長い呼吸をしながらの、ゆったりとした時間が流れる。私は体が固いので、体の隅々までが伸びたという感じはめったに味わえないが、何も考えずにヨガの指導者の声のままに体を伸ばし、呼吸し、瞑想を終えると、体全体がすがすがしい感じになる。 10年以上前にヨーガを始めた時、「ヨーガは3日目、3か月目、3年目で体が変化する」と言われた。その時は、3日目に体が伸びたのを感じ、3か月目にはやたらに眠くなった。3年目には体がぐっと柔らかくなると言われたが、それはあまり実感しなかった。もっとも、前屈して手で足の親指を持つのがやっとだった最初の頃から比べれば、多少柔らかくなってはいるが。 事情があってしばらくやめていたヨガを、昨年の8月に再開した。初回で体の芯が伸びるのを感じ、3回目でやたらに眠くなったが、その後はヨガを続けていた頃に体が戻った感じがするだけで、体が柔軟になったという実感はない。それでも、呼吸は長くなったし、座れはすっと瞑想に入れるようになった。「あんまり進歩はしないけれど、気持ちがいいから、いいか」と思いながら週1回続けてきたヨガだが、それでも最近は薄紙1枚くらいづつの進歩が感じられる。「何事も続けることがことが大事」というのは本当だなと実感しつつ、もう一歩進んで、毎日自宅で決まったポーズをやるようにすれば、体が変わるかもしれないと考えるようになった。子供の頃からスポーツが苦手だった私は、汗を流す楽しさとか体を作る喜びを感じたことがない。50歳を前にして、体を作ることに挑戦するのもおもしろいかもしれないと思い始めている。 |
|
ある日、新しい翻訳書「僕の夢、パパの愛」を持って、夫の行き付けの「ジャズバー・サムライ」に行った。本をマスターの二健さんに進呈し、さてボトルを入れようかという話になった時、クラウンロイヤルという言葉が耳に入った。 「クラウンロイヤル?どこかで聞いたような……、あっ、あっ、それってこの本の中で、主人公の息子と父が瓶からぐびっと飲むウィスキーの名前じゃない!私はこれまで見たことも聞いたこともないウィスキーだったけれど、それがここにあるの?」 ニューヨークのヤンキースタジアムで綿あめのコーンの謎が解け、新宿の片隅の小さなバーでクラウンロイヤルと出会う。一冊の翻訳書が、小さな発見と出会いを生む。こうした驚きと楽しみは、翻訳に心を注いだ私へのご褒美だ。これから先も、こんな小さな楽しみがいくつか現れるかもしれない。そう思いながらその日は紫の袋を、後日ボトルが空いた日に、手になじむ形のボトルを持ち帰って来た。 (2002年11月2日) |
|
私は物心ついてから、墓参りというものに行ったことがない。祖母は仏教徒で部屋に仏壇があり、彼女の夫や先立った息子たちの位牌を置いて彼岸には花を飾っていたが、私は無関心だった。もしも墓が東京にあれば、祖母は私たちを連れて行こうと思ったのかもしれないが、夫や子供たちの骨は九州の寺に納めてあったので、仏壇に手を合わせることで満足していたのだと思う。戦場で多くの人間の死を見て来た父は神も仏も信じないと公言していたので、そんな父に遠慮していたのかもしれない。 母方の祖父母は日蓮宗の信者だった。夏休みに遊びに行くたびに、毎朝仏壇の前で念仏を唱える祖母の姿を見ていたが、一緒に拝めと言われたことはなかったので、「あれはおばあちゃんのお務め」と思い、やはり無関心だった。 母は年に数回、弟二人と私を杉並区堀ノ内の寺に連れて行った。あとから考えるとそこは母の両親の寺らしく、「自分たちのかわりにお参りして来てくれ」と言われて通っていたらしい。しかし、子供の私にとってそこは、麦をふくらませたお菓子を買ってもらって食べ、群がる鳩にもそのお菓子をあげるところ、帰りに親子でおいしいものを食べに行くところだった。本堂に上がってお参りした覚えもないし、さい銭を投げて手を合わせたかどうかも覚えていない。母にとっても、姑と同居する家から出ての息抜きという意味合いが強かったように思う。 そんなわけで、墓参りにも先祖供養にも全く関心を持たずに成長した私は、大学に入り、地方から出て来た男子学生が「おれは長男だから、田舎に帰って墓を守らなくてはいかん」などというのを聞いてびっくりすることになる。墓へのこだわり、家へのこだわり、家族の血を残すことへのこだわりを知るにつれて、そういうものから自由に育った自分の環境に感謝するようになる。幸いに、一緒に暮す夫もそういうこだわりのない人間で、神も仏も信じない私は、これまでそういうものに距離をおいたまま暮すことができる。ありがたいことだ。 墓参りや先祖供養を否定するつもりはない。墓の前で手を合わせて心が落ち着くならそれでいいし、そこに家族が集まることに意味があると感じるならそれでいい。私は1年前に死んだ父のことを、毎日会社帰りになんとなく思い出す。父の具合が悪くなってからは、週に3回、帰りに父の家に寄っていたので、電車に乗ると自然に父のことを思い出すことが多いのだ。子供のころに「墓参りで心が落ち着く」という経験があれば違うのかもしれないが、私は墓の前で手を合わせて故人を思い出すより、こんなふうに毎日父のことを思ったり、もっと以前に亡くなった祖母や母のことを時折思い出すほうが、自分の心にしっくりくる。 (2002年11月1日) |
|
最近タティングレースを始めた。ふつうのレース編みはかぎ針を使って編むが、これはかぎ針の代わりにシャトルという舟型の道具を使う。芯となるレース糸を指にかけ、この糸にシャトルをくぐらせて結び目を作っていく結び編みだ。手芸仲間の展示会で、実際に編むところを見て興味を持った。長さ6センチ、幅2センチほどのべっこう模様の舟形シャトルが左右に動くだけで、ちょっと変わった編み模様ができる不思議さに魅力を感じ、自分でもやってみることにした。 さっそく、シャトルと英文のハウツー本、レース糸を揃え、写真通りにやってみるが、なかなかうまくいかない。数時間で結び編みの初歩をマスターし、ピコットと呼ばれる輪飾りもできるようになったが、連続編みの繋ぎがうまくいかないし、英文の模様の指示もピンと来ない。久しぶりの編み物で肩は凝るし、目も疲れる。しかし、新しい編み方を解明していくのは楽しく、当分は遊べそうだ。 タティングレースの歴史は文字よりも古く、人々が交信の符号として結んだものが発展したという説もあるという。18世紀から19世紀にかけてイギリスを中心に流行。貴婦人たちの優雅な趣味として、もてはやされたらしい。日本には明治時代初期にミッションスクールの宣教師が伝え、大正から昭和にかけて一大ブームを巻き起こしたというから、編み物が好きだった母が生きていれば知っていたかもしれない。そして今、日本でタティングレースがひそかなブームだという。実際、レース糸を買いに行った手芸材料店ではこの編み方のミニ講習会が開かれていた。 小学校時代に友達と競うようにして編んでいたレース編みだが、編まなくなってもう何十年にもなる。久しぶりにレース糸の売り場に行って見るとなんだかなつかしく、偶然出会ったこのレース編みをしばらく楽しんでみようと思っている。 (2002年11月1日) |
 |
8月に夫とニューヨークに行った。夫の好きなメジャーリーグベースボールとジャズを楽しみ、あとはホテルの周辺を歩くという、のんびりとした旅だった。さすがに人種のるつぼと言われるニューヨークだけあって、耳にする言語は多数。アメリカ各地及び世界各国からの観光客もたくさんいたが、様々な言語を話しながらニューヨークに暮す人々も大勢いた。街を歩き、公園のベンチでコーヒーを飲みながら、そうした人々を眺めるのは、おもしろい体験だった。 中でも私の目を引いたのが40代、50代の働く女性たちのファッションだ。様々な人種、様々な体型の女性たちが、思い思いにビジネスに合った服装を楽しんでいる。ウォール街近くの公園のベンチに座っていると、目の前を黒人の女性が通り過ぎていった。大きな体に胸の大きく開いた若草色のブラウス、スリットの大きく入った揃いの色のロングスカートでさっそうと歩いて行く。デザイナージーンズに赤い半袖セーターのヘソ出しファションながら、首から身分証明書を下げたランチタイムの女性もいる。ブロードウェイのカフェバーで隣に座った50代の女性は、カチっとした黒のスーツに身を包んでいたが、赤いプラスチックフレームのメガネに遊び心が感じられてステキだった。 彼女たちは太り過ぎだろうが体型が崩れていようが、自分が着たいと思う色やデザインの服を着て、胸を張って歩いている。そうした姿を見ていると、ダイエットに明け暮れる東京の若い女性たちの細すぎる体がとても貧相に思える。私自身、腕の太いのが目立つからノースリーブはやめようとか、おなかの肉が気になるからギャザースカートははけない、などと思っていたが、東京に帰ったら着たい服を好きなように着ようと思った。彼女たちのように肌を出して色っぽく、自分の体にあったサイズを堂々と着るほうが、ファッションは楽しいにちがいない。 (2002年10月3日) |
|
このホームページの「ちょっとお知らせ」のコーナーでも紹介しているが、春から翻訳していた本が出版された。『ぼくの夢、パパの愛』(ブラッド・バークレイ著角川ブックプラス)という本で、16歳の男の子を主人公に親子の愛を描いた物語だ。1975年のアメリカが舞台で、時代の雰囲気を出すため、当時流行っていた歌やテレビ番組、CM、アニメキャラクターやロゴマークなどが文中のあちこちに登場する。こういうのが翻訳者泣かせで、知らない固有名詞が出てくるたびに、特殊な事典を引いたりインターネットで検索したりして、いったいどういうものかを調べるのだが、すぐには見つからないことが多い。 ところが今回は幸運な出会いがあった。翻訳が決まる前から英語の個人教授をしてくれていたスティーブが、心強い協力者になってくれたのだ。アメリカ生まれ、1975年当時14〜15歳で、現在映像関係の仕事をしている彼は、文中に出てくるテレビ番組や歌手、歌のタイトル、ロゴマークなどをたちどころに説明してくれる。この番組はこういう内容で、これはその番組の司会者の名前、ああ、これはイーグルスの曲で、と言いつつメロディーを口ずさみ、これはハンバーガーチェーンのキャラクター人形、と言いながらサラサラと絵を描いてくれる。この本の翻訳にうってつけの時代背景の知識が豊富で、私はこの偶然を大いに利用させてもらった。自分で文章も書くスティーブは、著者の文章を吟味して、繰り返しが多いとか、ここはすごく美しいなどと感想を述べるので、文章談議にも花が咲き、物語に対する愛着も深まった。 全体を通して読みたいと言うので新しい原書を進呈し、訳書が出たときは一番に彼に手渡した。スティーブは「おお、すごいな。本当に出たのか」と言って感激してくれたが、同時に「10月からシンガポールの映像会社で働くことにした」と言うではないか。 やっと気の合う教師を見つけたと喜んでいた私にはすごく残念な話だが、やりたい仕事が出来そうなスティーブは、シンガポール行きをとても楽しみにしていた。まるで、この本の翻訳を手伝ってくれるために私の前に現れたみたいなスティーブだったが、彼の叱咤激励にはほんとうに感謝している。 (2002年10月4日) |
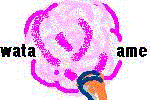
|
祭りの後、地面にはポップコーンの空き箱と綿あめのコーンが落ちていた。 こんな疑問で頭が一杯になるが、辞書を引いても綿あめの絵が出ているものはない。英語教師のスティーブに疑問をぶつけてみるが、音楽や映像には詳しい彼も、「綿あめは食べたことがないから知らない」などと頼りないことを言う。 「ええっ?子供の頃、縁日なんかで食べなかったの?」 ところが、この謎が8月のニューヨーク旅行で解けたのだ。所はヤンキースタジアム。ブルーの綿あめを頭上に掲げた売り子がやって来た時、私は思わず目を凝らした。具合よく、私の二つ前の席の高校生らしい女の子が綿あめを買い、隣の女の子と二人で手でむしりながら食べ始めた。日本のような割りばしの1本ではないが、アメリカの綿あめも棒に巻かれている。「なんだ、コーンじゃないじゃない」と、ガッカリする私。ところが、綿あめがむしり取られるにつれてコーンの謎が明らかになってきた。棒に見えたのは紙の筒で、先端に行くほど太くなっているのだ。つまり、上部が直径3センチほどの円、高さが約20センチほどの逆円錐形=coneになっている。「ああ、コーンってこういう意味だったんだ」と深く納得した。こんな些細な発見がこんなにうれしいなんて、これも翻訳の楽しみのひとつと言えるだろう。 (2002年10月5日) |

|
銀座の広告製作会社に通い始めて3年になる。最初にフルタイムの勤務を引き受けた時に2つの不安があった。1つは体力が持つだろうか、2つめは毎日会社に通う生活に飽きてしまわないだろうか、ということだった。何しろ10年以上フリーで、自分のペースで好きなように仕事をして来たのだ。人の多いオフィスの騒音の中で仕事をする体力はもうないかもしれない。それに、毎日同じ時間に家を出て、決まった場所で仕事をする生活にすぐに飽きてしまうかもしれない。 そこで私は2つのことを実行することにした。まずは健康管理。ちょっと疲れたと思ったらすぐに薬を飲む。肩が凝ればマッサージ、ずっとやめていたヨガも再開した。そしてもう1つ、銀座の街を歩くことにした。銀座は情報の宝庫だ。ブランド店の並ぶ通りを歩いていても、デパートや書店を巡っていても、美しいデザインとしゃれた言葉が目に飛び込んでくる。多くの店がお客の心を掴むためにしのぎを削っている。そんな中を毎日歩くのは、楽しい刺激だ。仕事は仕事で面白いが、私が通勤することに飽きずにいるのは、銀座の魅力に依るところが大きい。 なかでも私の心を掴んだのが、この街で見かける年配の女性たちのファッションだ。観劇だろうか、買い物だろうか、数人で集う50代、60代の女性たちはみな思い思いのおしゃれをしていて、ステキな人が多い。アートっぽいイアリング、アンティーク調のブローチなど、身につけているアクセサリーもステキで、擦れ違いざまにちらっと眺めてしまう。女性同士で集まっていても、同年配の男性にエスコートされていても、にこやかな笑顔の人が多いのは、銀座の華やかさのせいかもしれない。 働く女性たちのファッションもステキだ。とくに年配の女性たちは、地味な黒のスーツに身を包みながら白髪の髪に豪華な珊瑚細工の髪飾りをつけていたり、上品なキャメル色のグラデーョンで全体をまとめていたり、仕事服ながら上手におしゃれを楽しんでいる様子が窺える。 私はファッションは自己表現だと思うが、銀座の街では年配の女性たちの上質な自己表現が数多く見られる。彼女たちの年齢に近い私自身、毎日のファッションを楽しみながら、まわりの人たちの服装を楽しんで眺めている。365日飽きずにそういう楽しみを味わえるのが、銀座の街の魅力といえるだろう。 (2002年9月29日) |
|
東京・上野にマルク・シャガール展を見に行った。日曜の午後に行ったので館内は混んでいたが、大きな絵が多く、まあまあの見やすさ。人の頭越しにではあるが、シャガールの空を浮く楽しげなモチーフと夢のような華やかな色彩を楽しんできた。中年の夫婦連れが多いのも微笑ましく、若い女性たちのファッションもちょっととんがっていて、それらを眺めるのも私の楽しみのひとつだ。 ゆっくりと人の動きに合わせて二階の展示会場に進んで行くと、すぐそばで「おすどり」という声がした。横を見ると高校生とおぼしき女の子の二人連れがいて、片側の女の子がパンフレットを片手に、もう一人の子にタイトルを読みあげている。その子の前にある作品には「雄鶏」の文字が……。 同じ年頃の子供がいる私としては、思わず「おんどり」と訂正してあげたくなったが、人込みの中で突然、「おんどり」とささやかれるのも体裁が悪いだろうと思い黙っていた。考えて見れば、東京生まれの高校生にとって、身近でニワトリを見る機会は少ないだろうし(小学校のウサギ小屋にはニワトリもいるのだろうか)、子供の頃に絵本などを読んでもらって「おんどり、めんどり」という言葉を聞く機会がなければ、そのまま知らずに成長してしまうことも大いに考えられる。 高校生二人で連れだって、わざわざ上野までシャガールを見に来るなんて、いい子たちじゃないか。人間知らないことはいろいろある。彼女たちも何かの機会に「おんどり」の読み方を覚えればいいじゃないか、と思うが、その一方で、「あの場でこそっとささやいて変な顔をされても、やっぱり教えてあげればよかったかな」という気持ちも捨て切れない。彼女たちがなにかのはずみのこのホームページを訪れて、雄鶏の読み方を知ってくれるとうれしいのだが……。 (2002年7月21日) |
 |
私が花を見にあちこち出かけるようになったのは、いつ頃からだろうか? 花の嫌いな人はいないだろうが、花が好きというのと、わざわざ電車に乗って花を見に出かける心とは別物のような気がする。 私が最初に花に心を奪われたのは、小学生の頃だ。真夏の校庭の隅に咲いていたカンナの花。影一つ無い正午の校庭。照りつけるの太陽の下で、深紅の花が、褐色の大きな葉の重なりの中から燃え立つように咲いていた。校庭には誰もいない。教室の窓からその光景を見た私は、昼間なのに闇に通じるような静けさと、カンナの力強さに心を打たれた。 二度目に、この明るすぎる昼間の闇のような静けさを感じたのは、一面に広がる蓮の花を見たときだった。鎌倉・鶴岡八幡宮の源平池。水面が見えないほどに生い茂る蓮の葉の間から、太い茎が立ち上がり、ニカーッと笑ったような大輪のピンクの花が、にょきにょきと顔を出している。一見すると輝く太陽の下のざわざわと騒がしい風景のようだが、じっと花を眺めていると、あたりの静けさが身に浸みてきた。 私はこの凄みのある静けさが気に入って、花を見に行っているような気がする。この静けさは、輝く太陽と強いイメージの花が醸し出すもののようで、柔らかな雨に濡れる花菖蒲や紫陽花、木漏れ日の下の曼珠沙華の穏やかな風情とは別のものだ。残念ながらカンナの群落は見たことがないので、今年もまた、あの静けさを求めて蓮の花を見に行こうと心に決めている。 (2002年7月4日) |

|
カフェ戦争なのだそうだ。十年前なら、アメリカンではない濃くてまあまあおいしいブラックコーヒーの飲めるところは「ドトール」しかなかった。ところが四、五年前から東京のあちこちに「スターバックス」ができた。全店禁煙ということもあって、ドトールはたばこを吸いたいおじさんビジネスマンが集まり、スタバは学生や女性が集まるという住みわけができたようだ。最近私はたばこの煙が苦手なので、店の雰囲気はスタバのほうが圧倒的に好きだが、スタバにはごく普通の濃くておいしいブラックコーヒーがない。カフェ・ラテとかなんとか甘いのやホイップクリームが乗ったのはいろいろあるが、私は甘いコーヒーは嫌いなのだ。スタバは値段も高いので、結局禁煙フロアのあるドトールを利用していた。 そうこうするうちに、タリーズとかエクセシオールカフェとか、スタバと似たようなカフェがいろいろ目に付くようになった。私の勤め先は銀座にあるが、銀座一丁目から京橋の先までには、ドトール、スタバ、タリーズ、エクセシオールカフェ、サンマルコとカフェが並んでいるし、すぐ近くに同じチェーン店が二つあるところもある。それぞれに、サラダが食べられるとか、禁煙席がきっちりと天井までの仕切りで区切られているとか、値段が安いとか特徴があるのだが、どれも「帯びに短し、たすきに長し」で、コーヒーがおいしく、静かで、煙くない、というたった三つの条件が揃うところがない。今のところ一番のお気に入りはサンマルコで、これは砂糖、ミルクを付けないブラックだと十円安くなるのと、一七〇円という値段なので、まあ、許せるという感じだ。 東京だけで、こういうチェーン店型のカフェが何店くらいあるのだろう。こうしたカフェ戦争の蔭でつぶれていった昔ながらの喫茶店も多いのだろう。しかし、これだけの数があっても、私のように「ここなら満足」という店がみつけられない客もいる。値段が安いのだから、六十パーセントくらいの満足で妥協すべきなのかもしれないが、町を歩き、どこかで休憩したいと考えてたくさんのカフェ・チェーンの前を通り過ぎ、しかも入りたい店がない、というのもなんとなく悲しい。こうなったら、生き残っている町の喫茶店の中から早めにお気に入りの店を見つけておかなくては、と思っている。何事も、満足を得るためには努力がいるということだろうか。 (2002年7月19日) |

|
7月はバーゲンの季節だ。そして、バーゲンの度に心が騒ぐのが靴売り場だ。私は靴の中で足がのびのびできるのが好きだし、24.5cmというサイズなので、デザインが気に入り、サイズが合った靴をバーゲン売り場で見つけられることは少ない。それでも、靴売り場の前を通りかかると、ついつい熱心に見てしまうし、履いて試してみたりもする。 「女は一生のうちに何足の靴を持つのだろうか?」と嘆息した男を知っているし、結婚して運ばれてきた新妻の荷物を見て、靴の数の多さに驚いたという話も数人の男から聞いたことがある。このことから考えると、男よりも女のほうが靴への関心が高いのだろうか。しかし、様々なモデルのスニーカーを欲しがる若い男達を見ていると、あながちそうとも言えないような気がする。 女性の靴の数が多くなるのは、服のバリエーションに比例するせいとも言えそうだ。春夏秋冬の4つ季節に合わせ、フォーマルとカジュアルを揃えればそれだけで8足。それぞれにベーシックな色とカラフルな色を揃えれば16足。そのほかに、ここぞという時のセクシーなハイヒールと今年の流行の靴などを加えれば、すぐに20足近くなってしまう。そこへ行くと男の場合は茶と黒のビジネスシューズを1足ずつ、スポーツシャツに似合う靴とスニーカー、それにサンダルでもあれば事が済んでしまうだろう。 私が靴好きの理由のひとつは、靴なら自分で常に眺めていられるからだ。服やアクセサリーは来ている自分には全体像が見えないが、靴ならばちらっと足元を見れば十分、お気に入りの靴を見るだけでいい気分になれるのだから、こんな楽しみをほっておく手はない。そう思うと、ついつい靴売り場をのぞいて、いい気分になれる靴を捜してしまう。 (2002年6月29日) |
|
子供が一年間の予定でアメリカに行って二か月になる。「寂しいでしょう?」とよく訊かれるが、別に寂しくはない。だいたい、こういう質問をしてくる人間は「寂しい」という答えを期待しているので、「寂しくない」と言っても「また、強がりを言って」と端から信用しない。そういうやりとりがめんどうなので、私を知っている人間の度合いによって、「そうね」とか「まあね」とか答えることもあるが、今の私の心境は「寂しい」という喪失感とは別のものだ。 確かに家の中に活気がなくなったし、ワールドカップを夫の二人で見ている時など、「三人で見たらもっとワーワー盛り上がるかも」と思ったりはする。しかし、二人でのんびり見るのも、それはそれでいいものだ。私は人間を眺めるのが好きなので、ファッションやものの考え方など、愛しながらも違いが楽しめる人間が身近から一人減ったことで楽しみが一つ減ったと思うが、そのぶん芝居を見に行ったり人と会ったりの回数を増やして、別の楽しみを増殖させている。 今の世の中では、簡単にメール交換ができるし、電話もできる。これが行方知れずとか、帰国するつもりはないといって出て行ったのならいざ知らず、居場所も何をやっているかもだいたいわかっているのだから、私はけっこう安心して子供の不在を楽しみ、彼が向こうの暮らしを楽しんでくれればいいと思っている。 東京からいなくなったのが親しい友人なら、もっと直接的に「会えなくて寂しい」とか「声が聞きたい、話しがしたい」と思うのかもしれない。それは、東京でのつきあい方が、断続的に会って話すことで成り立ってきたからだろう。十八年一緒に暮らし、毎日を眺めてきた子供とのつきあい方とは別物だ。 私の心が騒ぐとしたら、多分帰って来てからだろう。日本に戻ってから、彼は自分でどう生きるかを決めなければならず、それを近くで見てはらはらする図は容易に想像できる。あっちが大人になり、私の心配などどこ吹く風となってくれることをひそかに期待してるのだが。 (2002年6月29日) |

|
人間を「読む人」「読まない人」の二種に分けるとしたら、私は完全に「読む人」だ。新聞は1ぺージ目の右上から律儀に目を通すし、通勤電車の中では中吊りや額面広告を読み、電車を下りてからは駅貼りのポスターを眺め、町の看板を読み、道でもらったちらしでさえ、さっと目を通してから捨てる。読書家というわけではないが、とりあえず目の前に字の書かれたものが出てくれば読まずにはいられない。 そして、私は四、五年前まで、これは別に珍しい性癖ではないと思っていた。ところがある日、息子と話していて気がついた。彼は目の前に字の書かれたものが出てきたら、「とりあえず読まない」のだ。ちらっと見て、学校のお知らせねと思ったら、それでおしまい。後から必要になったら捜して読めばいいと思うらしい。私はだめだ。何が書いてあるかその場で知りたい。 このことがあってから注意してまわりを見てみると、会議の時に議題を簡略にまとめた紙を渡しても、読まずにそこに書いてあることを聞いてくるやつとか、原稿をあまり読まないデザイナーとか、「読まない人」が思いのほか多いことに気がついた。 そう言えば、息子の小学校の参観日に、子供たちが社会の教科書をちゃんと読めないのに驚いたことがあったっけ。若者の読む力が低下しているのだろうか。携帯電話の普及で読み書きの機会が減ったのだろうか。しかし、携帯でもインターネットでもメールのやり取りは盛んだ。もっとも携帯メールなどは、読むというより見るという感覚なのかもしれないが。 電車の中でヘッドフォンをしている若者の数を考えると、「読む人」より「聞く人」が増えているのかもしれない。しかし、会議で話がきちんと聞ける人間だって少ないし、言っても覚えないから紙に書いて渡していたのに、これでは人に何かを伝えるのは大変ではないか。 ああ、しかしと、ポジティブ・シンキングな私は考える。だからこそ、物事をわかりやすくを書いて人に伝える能力は、ますます大切になるだろう。「読まない人」にも読んでもらえるような魅力のあるものを書かねば、と。 (2002年4月13日) |
 |
私の高校は、都立高校には珍しく芸術科と体育科が併設されていた。私は普通科の学生だったが、美術部に入っていたので多少芸術科の学生と接点もあり、変わり者であることがステータスのような彼らを遠巻きに眺めながら、文化祭などで作品を見るチャンスがあると眺めに行っていた。その中に一人、やたらに似顔絵のうまい女の子がいて驚いたことがある。クラスメートたちの特徴を一筆書きのような省略された線で見事に捉え、シンプルなラインなのに、どの似顔絵が誰かすぐに特定できた。山藤章二の似顔絵塾でも、デフォルメされたシンプルな線なのにモデル以外の何者でもない、というような似顔絵を目にして驚嘆することがある。 これまでいろいろの似顔絵を見てきて感じるのは、似顔絵を描く才能は絵を描く才能とは別ものではないかということだ。観察力、洞察力、批評精神、人間への興味、もっと言えば人間愛のようなものがあって初めて、人の心を打つ似顔絵ができるような気がする。 私自身は自画像を描いたこともないし、人の似顔絵を描いたこともないが、似顔絵を描いてもらったことは何度かある。そのうちの一枚は友人の邦子さんが描いてくれたもの。描かれる立場としては、照れくさいようなうれしいような気持ちだが、描いてくれる人の愛を感じずにはいられない。 (2002年4月9日) |
|
今話題になっている『声に出して読みたい日本語』という本を買った。本屋でぱらぱらめくって、「なんだ、ほとんど知っているものばかりだ」と思って一度は買うのをやめたのだけれど、その後、あちこちでこの本をみるにつけ、「まあ、手元にあってもいいか」という気になった。買う気になった大きな理由は、がまの油売りの口上をきちんと知りたかったのと、記憶には残ってはいるけれどはっきり覚えていないフレーズを確認するときに役立つだろうと思ったからだ。 がまの油売りとバナナのたたき売りは、子どものころにテレビで見て大好きになり、見よう見まねで弟たちに語ってやった。この本を買ってから最初に声を出して読んだのもがまの油売りの口上だが、しゃべり出すと自然に言葉が出てくるのに驚いた。子どもの頃に覚えたことはなかなか忘れないらしい。 「驚き桃の木山椒の木、当たりき車力車引き」などという付け足し言葉(と言うそうだ)は祖母がよく口にしていたし、「知らざぁ言って聞かせやしょう」(歌舞伎・白波五人男)、「赤城の山も今夜を限り」(国定忠治)などの芝居のせりふは、中学時代に歌舞伎好きの同級生が休み時間に語るのを聞いて覚えた。 「光る地面に竹が生え」(『竹』萩原朔太郎)、「山の動く日来る」(『そぞろごと』与謝野晶子)などの詩や、平家物語、方丈記などの古典の一節は学校教育の中で覚えたものが多い。国語の時間に生徒みんなで声を出して朗読したような気がする。こういうことを思い起こすと、学校教育も捨てたものではないと思う。息子の小学校時代も国語の時間に「いるかいないかいないかいるか」(『いるか』谷口俊太郎)などの詩を暗唱したり朗読していたから、国語教育を通して詩や古典の一節を覚える子どもたちは多いのだろう。今の子どもたちは歌舞伎や芝居のせりふは知らないかもしれないが、そのかわりにアントニオ猪木の引退時のセリフや金八先生のセリフなどを真似して遊んでいるのではないだろうか。 腹から声を出して読むと体がしゃきとするし声を出すことで言葉が記憶に残るというが、それよりもなによりも、リズムのいい言葉を味わう楽しみ、何かになり代わって演じる楽しみを、子どもたちを含め多くの人たちが知ってくれればいいなと思う。 (2002年4月11日) |
|
久しぶりにランジェリーのバーゲンに行って驚いた。昔はCカップまでが一般的だったブラジャーのバーゲンに、EカップやらFカップが並んでいる。そんなに胸の大きい子が増えたのだろうか。そう思って会社の行き帰りに擦れ違う女の子達を思い起こして見ても、痩せた子ばかりで、胸の大きい子が増えたという印象はない。同じバーゲンに並んでいた上げ底ブラの隆盛を考えると、どちらかといえば胸のない子が増えたという印象だ。それなのに大きなカップのブラがバーゲンに出ているということは、少数派も大切にされるようになったということか。そういえば、テレビでは若くてかわいい巨乳タレントが人気らしい。ブラの世界も二極分化が進んでいるのだろうか。 一方、大きなサイズが少ないのが普通の服のバーゲンだ。私は会社の帰りに駅ビルなどを見て回るのが好きだが、そもそも9号サイズしか置いていない店が多いので、気に入った服を見つけても11号サイズの私には小さ過ぎてあきらめることが多い。最近は背の高い子が多いのに、彼女たちはみな9号サイズに納まってしまうのだろうか。それとも、少し小さめの9号に向けて、はやりのダイエットに励むのだろうか。 巨乳タレント人気を考えると、男たちはあいかわらずグラマーな女の子が好きなのだろう。ところが若い女の子たちはどんどんやせて棒のような体になっていく。そこで彼女たちが意識しているのは同性の目なのだろうか。私は男と女は対等であるべきと考えるので、男に媚びない女たちの姿勢は頼もしく思うが、誇らしげに痩せる女たちを見ていると十年後の健康を心配してしまう。自分の理想の体型を目指す彼女たちが、食事と栄養の知識を正しく持って自分を律していくことを願うばかりだ。 (2002年3月3日) |
|
「私はフェミニストです」と言うと、多くの男性がぎょっとしたような顔をする。男女同権という、私にとってはごくあたり前のことを主義にしているに過ぎないのだが、三十代以上の男性の場合、フェミニスト、ウーマン・リブ、なんか文句をつけられそう、という連想があるらしい。十代、二十代だと、そもそもフェミニストの意味を「女に優しくする男」と誤解している節がある。そこで、なるべくフェミニストという言葉を避け、文章にする場合には「男女同権主義者」と書き、会話の場合には「人間は皆平等と考えている」と話すようにしている。 「人種、性別、年齢によって人を差別してはならない」と言えばみな頷くが、実際の日本社会にはさまざまな差別が横行している。同じ仕事をしている男女の賃金や昇給差別しかり、根強いアジア人差別しかりだ。 昨年十一月三十日の朝日新聞朝刊に載っていたパリからの特派員メモに以下のような文があった。 ---- これを読んで私は、残念ながら日本は差別主義の国だと思った。外国人との共存を嫌う社会と天皇家報道に厳しい自主規制をするマスコミを見ていると、日本は極右だというのも一面の真実だと思う。こうした日本の現実を変える第一歩は、日本の現状をきちんと認識することではないだろうか。そして、大人にも子供にも「差別はいけないことだ」ということをしっかり教育して行くことだと思う。 (2002年1月15日) |
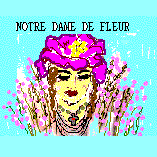
|
私のフランス文学への愛は、アルセーヌ・ルパンに始まる。子供の頃から本が好きで、しかも読むのは外国文学ばかりだった。たまたま子供向けの世界文学全集が家にあったせいもあるが、日本の小説も読もうと思えば読めたはずなのだから、私自身の中に未知の文化へのあこがれが強かったのだろう。母に連れられて見に行った芝居も西洋物ばかりだったから、単純に美しいロングドレスの世界にあこがれたのかもしれない。たくさんの外国文学なかでもルパンの洒脱さに引かれ、母が好きだった油絵の絵描きにもフランス人が多いことを知り、着る物に関心の高かった中学生のころに、ファッションの都パリのイメージを植えつけられた私にとって、フランス、とくにパリは特別の場所だった。 そして高校生になって、ジャン・ジュネ、ヴィアン、サルトル、ボーヴォワール、カミュ、ポンジュなど、きら星のごときフランス人作家たちの本を読んで、これらの美しく理知的な文章をフランス語で読みたいと痛切に思うようになる。勉強したいという意欲に燃えて大学に進学したわけではないが、4年間フランス語で本が読めたら楽しいだろうと思ってフランス文学の学べる大学に進学した。大学の講義で読んだボードレールやプルーストの文章は期待通りに美しかったし、ヌーボー・ロマンの実験小説やポンジュの詩は、言葉と文体を味わう楽しみを私に教えてくれた。 大学を出てからはフランス語を話す機会はまったくなく、ライターとしてずっと仕事をして来たが、昨年初めてフランス語の下訳をし、続いてフランス語脚本からのノベライズの仕事をさせてもらった。思えば、私がフランス文学への愛を育むことができたのは、たくさんの訳者のおかげである。大勢の先達のおかげで、私はフランス文学という珠玉の世界を知り、新しい世界観に触れ、私の生き方の芯のようなものを持つことができた。駆け出しの訳者として彼らの仲間入りができた今、翻訳を通して、これから大人になろうとする息子たちの世代に、「新しい世界観」を示すことができたらうれしい。できたての翻訳書を前に、私はそんな野望を抱いている。 (2002年2月2日) |
|
私は飽きっぽい性格なので、いろいろなことに次々に手を出してはやめていく。しかしその一方で、好きなことは細々と長く続けていく粘り強さもあって、四十八年も生きていると、「断続的に続けながら、結局もう十年もやっている」ということがいくつも出てくる。どれも最初の一、二年は進歩を感じるが、あとは十年一日。やっている時は楽しいけれど、技術的にうまくなったという充実感はほとんどない。 長年続けているヨガもそうで、週一回、けっこう熱心に通っているにもかかわらず、いかにもヨガらしいポーズはできるようにならずに終わっている。そんな私のような生徒を視野に入れてか、私のヨガの師は、「繰り返しやっていると、ある日、量が質になる」と言う。こう言われてはっと気づいたのだが、私は若いライターに「どうしたら文章がうまくなりますか?」と聞かれると、「たくさん書くと、書いてるうちにうまくなる」と言ってきた。そうか、これと同じことなのかと思うと、納得がいった。しかし、この場合の「たくさん書く」とは、真剣勝負で山ほどの仕事をこなすという含みがあるわけで、進歩するためには半端じゃない繰り返しが必要ということになる。考えて見れば、私が毎日やっても飽きないことは書くことだけなので、それを仕事にしていることは、なんという幸せかと思う。そして、息子の世代の若者たちが、毎日やっても飽きずに、しかも繰り返しが進歩となる仕事を見つけることを切に願っている。 (2002年2月3日) |
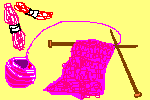 |
久しぶりに編み物を始めた。今編んでいるのは、白黒の毛糸を編み込んだノルティック模様のマフラーだ。早く編めて、作ったという満足感が味わえるものにしたかったので、ちょっと凝った編み込み模様を選んだ。編み物をするたびに思うのだが、編み物は瞑想に似ている。編み目を眺めながら手を動かしている間はよけいなことは考えられない。自然に無心となって、模様の目数を数えながら編み進むことになる。単純な編み目の場合は、テレビを見ながら編むということもできるが、それもテレビをちらっと見たり、言葉の断片を聞いているだけで、意識は編むほうにいっている。 編み込みや模様編みのセーターは、寒さの厳しい北の地で漁のできない冬に編まれた歴史のあるものが多い。ノルデック、アランなど伝統の編み物には独特の模様があって美しいが、それらの模様は家紋のようなもので、海で溺死した時にセーターを見ればどこの家の者かわかるようにという配慮だという。 模様に秘められた歴史を思い、いまこうして心静かに編み物ができる環境に感謝しつつ正月休みを過ごしていると、世界が平和であってほしいと思う。今年の年頭のあいさつには世界の平和を願うものが多かったが、そのために自分に何ができるかを考え、一人一人が行動を起こすことが大事だと思う。 (2002年1月7日) |
|
この頃、店に入るたびにアナウンスやBGMの音量の大きさが気になる。 家の近くにビデオ屋ができて、一泊100円セールをやっているので何回か借りに行った。私は店の中を巡りながら、何を借りようかと考え、「これが第一候補。これが第二候補。でも他にもっといいのがあるかも」と思いながら別の棚を捜すのだが、そのうちに何を第一候補にしていたか、そのビデオがどこの棚にあったかを忘れてしまう。「こんなに忘れっぽいはずはないのだが。どうしたんだろう?」と、自分の頭の具合を疑ったところで、ハッと気づいた。この店のBGMで流れている音楽の音量がやたらに大きいのだ。大音量を耳にしながら店の中を巡るうちに私の思考は停止し、何も考えられなくなってしまう。 若い子たちは、こんな大きな音の中でも平気なのだろうか?電車の中でCDを聞いている若者の音漏れ具合から考えると、慣れて平気になっているか、どんどん思考が停止しているかのどちらかだろう。 そして別の日。近くにあるスーパーに行ったところ、本日のお買い得品を告げる店内アナウンスの音量がやたらと大きい。隣の夫の話し声も聞こえないほどで、すっかり食欲が減退して、必要最小限のものだけ買って帰って来た。私は大きな音の中で物を食べると、味がわからなくなるが、若い子たちはどうなのだろう?私がどんどん気難しくなっているのか、若者の五感がどんどん鈍くなっているのか、どちらかわからないが、私の居心地のいい場所はどんどん減っている。 (2002年1月4日) |
|
毎年、お節料理を作って来た。私のお節は祖母から教わったものなので、祖母の故郷・九州の料理が多い。鳥のレバーと野菜を煮たがめ煮、ゆで卵の黄身の中に白身を刻んで入れた切り口が美しい岩石卵、百合根やくわいの甘煮、ひき肉だんご、蒸しエビ、数の子、いんげんのごま和えあたりまでを作り、かまぼこ、昆布巻き、こはだの酢漬、田作り、黒豆などは市販のものを買って、重箱に並べる。これに夫が家で食べていたという掛川風のシンプルなお雑煮を添えるのが毎年恒例の正月料理だ。 しかし、これらの料理は夫や息子にはあまり歓迎されない。夫はビールのつまみに一通り食べるが、二日続けて食べるのは飽きるし、子供はすぐに「ソーセージないの?カレーは?」などと言い出す。それでも作り続けていたのは、店がほとんど閉まってしまう一月一日に、一人暮らしの父が訪ねてくるか家族三人でお節を持って訪ねるかが、ここ十年以上の正月行事だったからだ。夫の母が東京にいた時期には正月に泊まりに来てくれたので、料理を作る張り合いも倍あった。夫の母はだいぶ前に郷里の掛川に居を移し、父は昨年亡くなったので、今年はお節をほんの形ばかりしか用意しなかった。 振り返ってみると、私がお節を作ってきたのは、「今年も変わりなく元気ですよ」というメッセージだったような気がする。夫の母や私の父は、毎年代わりばえのしないお節を食べ、新年恒例のこまごまとしたことを繰り返すことで、なんとなく安心していたのではないだろうか。今年は息子も高校を卒業して旅立って行く。そうすれば、とりあえず安心させたい相手は身近にいなくなるので、何か冒険したいと漠然と思っている。 (2002年1月3日) |
|
ヨガを始めて、十五年以上になる。そもそものきっかけは、前に住んでいた飯田橋駅前にヨガ教室があって、電車の乗り降りのたびに教室の看板が目に入ったからだ。当時は一歳半の息子の相手をするだけで疲れ果てる生活で、なんとか体力をつけたいと思っていた。子供のころから運動が嫌いだったので、スポーツジムに行く気にはならない。そんな 時に看板を見て、「ヨガならできそう」と思った。 以来、池袋、荻窪と、引っ越すたびに近くにヨガ教室を見つけて続け てきた。四、五年目までは、体が柔らかくなったりと進歩もあったが、そこからは「やれば気持ちがいい」というだけで、体の調子はほとんど 変わらない。呼吸法もだいたい覚えたし、座ればすっと瞑想にも入れるようになった。毎回やるポーズも決まっているので、わざわざ教室に通わなくても、自宅で一人で十分にできるはずだ。 それなのに、なぜ教室に通い続けているかというと、声のパワーなのだ。同じ姿勢で体を伸ばすにしても、部屋に静かに響く「体が伸びる、伸びる、伸びる」というヨガ教師の声が聞こえるのと聞こえないのでは 体の伸び方が全然違う。静かな低いゆっくりとした声、発声と発声の間 の独特の間に身を任せて伸ばす部分に神経を向けると、一人でやるのと は全然違った体の伸び方、緩み方を体験できる。暗示の力なのだろうか、声のバイブレーションが体に影響を与えるのだろうか、教師によって 、声の質、テンポ、声を出すタイミンクが違うので、声が聞こえても体 があまり伸びない声と、ほんとうに体の芯まで効いた、と感じる声があ る。 |
バックナンバー2003年の「ちょっと言わせて」を読む
バックナンバー2001年以前の「ちょっと言わせて」を読む
「ちょっと言わせて」目次へ戻る