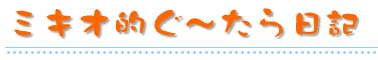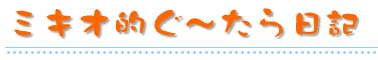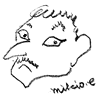|
■女性作家好きの正体
読書嫌いというワケではない。読書になかなか集中できない、あるいは滅多に本など読まないという自分の正体を正直に明かすと、時々知的な女性たちから軽蔑と非難の視線を浴びる。そんな僕でも、ここ10年に遡って考えてみると、読書履歴のそのほとんどが女性の書いた小説なり評論であることに気づく。理由はよく分からない。
澤地久枝さんの一連のノンフィクションを読んだ延長線で「天皇の逝く国で」のノーマ・フィールドさんを知った。どちらが最初だったか忘れたが、多和田葉子さんと板東眞沙子さんの小説と出会ったのはほぼ同じ時期だった。多和田さんの作品はいつも実験小説的なアプローチで目の前に現れるので、読めない時には1ページで降参する。ツボにハマると夢中にさせられる。彼女がドイツ在住で、ドイツ語で書いた作品でも彼の地で絶大な評価を受けていると知ったのは、ずいぶん後になってからのことだ。それでもまるで驚かなかったのは、作品の質がすでに国境などという陳腐なモノを超えてしまっていたからだ。
板東さんの作品と最初に出会ったのは「19xx年度現代日本作家選」とでもいうような1冊にたくさんの作家とその作品が集められた本で、図書館で借りたものだから作品名もすでに忘れた。四国のどこか片田舎に嫁いだ若い女の放つ強烈なエロティシズムとその存在故に導かれる破綻までを濃密に描いた短編で、「普遍的」土着感の強さに惹かれた。彼女もまたイタリア留学なのか遊学なのか滞在中という情報を、僕は何かで得ていた。長編の「死国」では、四国を舞台にした「いかにも」のオカルティズム臭が好きではなかったが、彼女はそれによって有名作家の仲間入りを果たしたはずだ。
昨日の朝日新聞夕刊に、第15回柴田錬三郎賞受賞の記事で板東さんが紹介され、彼女が4年前からタヒチに移り住んでいるということを初めて知った。それについて、「日本という国、日本という社会に精神的にいられなくなった」とか、「なぜ自分が日本にいられないのかを探る」、「日本人的なもののいやらしさ、日本という国のいやらしさ」などを書くことが彼女の文学的テーマなのだと知った。
結局、僕のちっぽけな読書志向というのは、板東さんの文学的テーマに通じるところがあって、前出4人の女性作家は、いずれも島国国家日本や日本民族幻想から突出なすっているのだった。
さあ。今日こそベイスボール英語辞典アップするゾォ〜!!
●今日の1句 こちとら東京徘徊さえもままならぬ
●今日のもう1句 農耕土着文芸に近づいちゃったなぁ〜
|