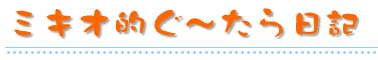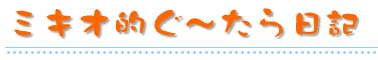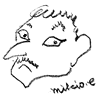|
■報道規制への坂道
昨日夕刻のニュースで知った「週刊金曜日」という雑誌の報道問題。メディアのありようとかジャーナリズムというものの本質的な理解が、この国にはまだ欠落しているんだナの思いを新たにした。あたかも「自由に発言できない北朝鮮でインタビュー取材した記事をこの期に報道することは、けしからん」の論調。どれほど考えた論理なのかは分からないが、それらの論調がそのまま罷り通れば、この国もまた北朝鮮みたいな国になってしまうことを、まず最初の前提に論議しなくてはならないはずだ。
お帰りになった拉致被害者の内の2組のご夫婦は、不幸中の幸いにも夫婦という結束する別人格同士の励まし合いが想像以上に大きな力となって生きてこられたのだと思う。それに対して、今回の「一時帰国」と言われた当初から、曽我ひとみさんの立場は圧倒的に苦悩に満ちたもので、今回の記事を見た曽我さんが号泣の挙げ句に報道に対する抗議をなすった旨の、これまた報道があった。後見人役の県議は、その様子を記者団に報告しながら、自らも感情を高ぶらせ声を詰まらせるパフォーマンスまでやってのけた。「情において忍びない悪辣報道」と、彼はほぼ断じていたように思う。拉致被害の家族会もまた、今回の報道のありように怒りと批判を表明している。家族会のお立場において、それはもちろん理解できるし、僕も共感はできる。
しかし、週刊金曜日が行い、掲載した取材記事や取材対象、手法そのものが「タブー視」されることだけは、絶対にあってはならない。案の定、政治家どもが口を揃えて報道規制の必要性を説く材料にしている。朝日新聞朝刊で、件の記事の要旨に目を通したが、今日の日本人の誰もそこで発言している曽我さんご家族のコトバを鵜呑みにする読者はいないはずだ。まだほんの十数年前、テンノーの病状報道に関して日本中に閉塞感が蔓延したあの空気は、日本という国が本当の言論や報道の自由が保証されていないことを露呈したばかりだったではないか。民主主義のみの字もない北朝鮮という最悪国家との違いは、まさにこうした言論・報道の自由を許容することにこそある。そのことと曽我ひとみさんの個人の哀しみは、まったく別次元のものである。
●今日の1句 気をつけようタブーの坂はまっしぐら
●今日のもう1句 清濁も陰影もないのが美しいのか
|