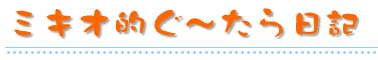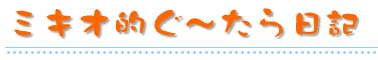■教材になるらしいゾ
ある進学用教材編集社から依頼があって、拙著「おけちゅう」利用の許諾に関するものだった。小川未明文学賞ってのは、受賞と同時に著作権だか版権利用だかの権利が文学賞選考委員会だか事務局だかに10年間預け置かれることを条件にしているので、多分、僕に許されるのは拒否権行使と傍観ぐらいのものだと思う。以前、英訳してアメリカでの出版を考えないかという打診をしてきたヒトがいて、そのための下交渉を事務局としたことがあったのだが、そういうケースでは「好きにおやんなさい」と言われた。どちらにしても英訳の専門家に委ねる前に「お前自身で下訳をしろ」と言われ、頓挫した。そんな英語力はない。
今回の依頼は、小学生向け教材としての利用ということらしいのだが、それにしても考えるところはある。「傍線部分で作者が言いたいことは何でしょう」って、こういう設問はホントに子供時代から馬鹿馬鹿しさが先に立って、困惑した思い出がある。「傍線部分で作者が言いたかったこと」はそのまま「傍線部分に書いてある」のがホントの答えであり、それを第三者が勝手に解釈したり理解した気になってもらっては困るのである。子供のための国語力養成というのは、一にも二にも素読、音読の繰り返し、短文理解や毛色の変わった文章にどれほど出会えるかにかかっていると思うのだ。粗読家にして文章コンプレックス持ちの僕が言えた筋合いじゃないか。がはは。
拙著では、小学校5年生ぐらいの高学年向けに編集段階で意を砕いたが、本来僕らが書籍と出会った当時には、かなりオトナ向けの書籍にも豊富にルビが付いていて、たとえ子供であっても意味なんぞ分からなくても平気で深山幽谷に分け入って行くことができたように思う。テレビ文化全盛から活字離れが起こりという文脈の他にも、出版界の勝手な読者想定によるセグメントの結果、あまりに編集の効率化やご都合主義が蔓延し、獲得できたはずの読者さえも逃がしてしまった側面もあるに違いない。
●今日の1句 どんと重い脚に雲のやつらを睨む |