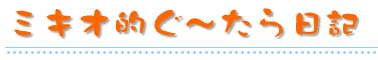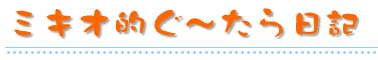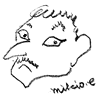|
■田舎のポルカ
オーケストラの楽団員とは、即ち「下僕」である。2003年1月1日もここ十数年間変わらぬウィーン・フィルのニュー・イヤー・コンサート聴きつつほろ酔いだ。昨年までと変わったのは、セガレがいなくなって親子3人麻雀やりながら聴くってコトがなかったのだった。ほんでもってオーストリアのウィーンとは、ホントに世界的田舎都市なのだとゆーコトに気づくのだった。化石のよーなオーケストラが、貴族趣味で選民趣味で懐古趣味で自惚れ趣味の古めかしくも快適なヨハン・シュトラウスを中心とした音楽を奏でるのであった。コレを気持ちイイと言わずして、何が気持ちイイんだ。
2002年の小沢征爾とは違って、今年のナントカ言う指揮者のオジサンはヨカッタ。それでもやっぱり何年か前のズービン・メータが出色だった。小沢はイヤ味なスノッブ、今年のオジサンはちょいとエキセントリック、メータがイイのは「あっぱらぱ〜」だったからである。きゃはは。
で、冒頭書いた「下僕」のコトだけんど、毎年毎年スター指揮者を「王」として迎えながら、その王の指図だったら何でも言うコトを聞いちゃうマゾヒスティックで貴族趣味の聴衆からも、結局楽団員は「サービス業者」として軽んじられるのだ。クラシックと呼ばれる音楽とは、結局そーゆーモノだと思っている。
今年のハイライトは、ヨハン・シュトラウスの「田舎のポルカ」で、楽団員が演奏しながらヒ〜コラ歌いまくる図は壮観であった。遊び心の発露。
ところで、ああ。こんな貴族趣味は身にそぐわないから、来年から見ないでガマンしちゃおーかナ。ところが、ウィーン・フィルが終わったら、今度は3大テノール番組があって、パバロッティ大好きな僕はやっぱり延々TVに食らいついていたのだった。ここでは、ドミンゴは弦楽器、カレーラスは木管楽器、パバロッティは金管楽器なのであった。パバロッティは数年前までより少し声量が落ちたが、「女たらし」は相変わらずで、そこが僕が彼を好きな理由だ。歌屋はゲージツ家気取りじゃダメなんだから。
●今日の1句 また別の新しい1日が始まっただけのことだ
●今日の1句 とりたてて新しい1日でもないじゃないか
|