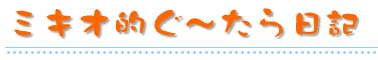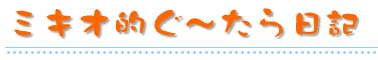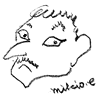■詩歌のヒトの言葉の深み
昨日アップした岡田幸生さんの「さっ」中、第1行目に引っかかりがあり、僕はお約束通り無条件で本HPに作品掲載すると言いながら、ご注進のつもりでメールを出した。
1行目「のぼせる」は「のぼらせる」なのでは?と。早速岡田さんからのご返事。
「ややこしくてすいませんです。身につかないことばをちょっと変則的に使ってみたのでした」とのこと。引用する。
大辞林に、 のぼ・す【上す】€(動サ五[四]) 「上せる」に同じ。「話題に―・す」「意識に―・す」「梓(シ)に―・す(=
出版スル)」「これを筆舌に―・すときは/即興詩人(鴎外)」「花車が―・ す一句あり/浮世草子・禁短気」 (動サ下二) ⇒のぼせる とあって、お目こぼしくだされば天にものぼる僕なのでしたが。
でもここはすっきり「意識にのぼす」としたほうがいいかしら。
いかん。読み手の僕がアサハカであった。僕の言語感覚または言語引き出しにないものを即座に書き違いなのではと考えたワケで、日頃の粗読家ぶりを露呈した。先頃僕は、他人様のコメントをわざわざ「きょうはくである」と評し、「強迫」と「脅迫」の二重の意味を持たせようと試みたばかりだったのに。あ〜。詩歌のヒトの言葉は深いゾ。
●今日の1句 パソ通で打つソバ(回文)
●今日のもう1句 ねえ仮乗り換えね(回文)
●今日のもうもう1句 打ち上げと称しお出掛けうれしいナ
●今日のもうもうもう1句 抑圧の憂さは晴れたか赤い衆 |